この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもの成長を見てきた経験から、家庭で実践できる防災体験を解説します。
「防災グッズを完璧に揃えるのは大変」「訓練は子どもが嫌がる」——そう感じて、つい防災を後回しにしていませんか。忙しい毎日の中で、いつ来るか分からない災害のことを具体的に考える余裕はなかなか持てないものです。
けれども、本当に大切なのは「特別な訓練を完璧にこなすこと」ではなく、日常の中で少しずつ「自分の命を守る力」を育てていくことです。防災は、テストのために覚える知識ではなく、暮らしの中でくり返し身につけていく「生きるための教科」と言えます。
夕食の準備をしながら「もしガスが使えなくなったら?」「水が出なくなったら?」と話してみる。そんな何気ない会話が、子どもにとっての大切な学びになります。家族で過ごす時間が増える夏休みは、「もしものとき」を親子で話し合い、少し試してみる絶好の機会です。
この記事で紹介する内容は、「家庭での学びと体験」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。
→子ども主体のおうち夏祭り|自己肯定感につながる家庭イベントの工夫
夏休みに見えたわが家の防災の弱点と“気づき”
ある夏の日、テレビで豪雨による停電のニュースを一緒に見ていたときのことです。真っ暗になった街並みの映像を見て、息子が不安そうな顔で「うちも停電したらどうするの?」と聞いてきました。
そこで私たちは、思い切って夕方に「停電ごっこ」をしてみることにしました。
ブレーカーを落とすと、部屋は一瞬で真っ暗に。「こわい!」「何も見えない!」と子どもたちは声を上げ、私自身も少し緊張しました。
懐中電灯を探そうとして「あれ、どこだっけ?」と慌ててしまい、日ごろからすぐに手に取れる場所に防災用品を準備していなかったことに気づかされました。
懐中電灯の明かりがつくと、子どもたちの表情は少しずつ落ち着き、「影ができるね」「壁に映るよ」と、恐怖心よりも好奇心が前に出てきました。
暗い部屋で簡単な夕食を囲み、「電子レンジが使えないと不便だね」「毎日これだったら大変だね」と話し合う中で、子どもたちは電気のありがたさと災害時の不便さを実感していきました。
ブレーカーを戻した瞬間、「わあ!」という歓声とともに、いつもの明るさが戻ってきました。
この小さな体験を通して、防災は頭で知るだけでなく、暮らしの中で体で確かめる経験から深まっていくことを、親子で実感することができました。
こうした体験が、子どもにとって「防災は特別なことではなく、日常の延長線上で考えてよいものだ」と感じる入口になります。
親の落ち着きが子どもの判断力を育てる:防災教育の基本原理
学校現場で多くの子どもたちと関わってきた経験からも、災害時に子どもの行動を大きく左右するのは「どれだけ知識を覚えているか」だけではありません。
子どもは状況そのものよりも、まず親や周りの大人の表情や声のトーンを敏感に感じ取ります。
大人が慌てて右往左往していると、子どもの不安は一気に高まり、「どう動いていいか分からない」という状態になりがちです。
反対に、内心は不安を感じていても、できるだけ落ち着いて状況を言葉にし、「一緒にこうしよう」と伝えることで、子どもは「自分も動ける」と感じやすくなります。
ここには、子どもの心の安全基地としての親の役割が色濃く表れます。
防災教育は、単に「〇〇のときは△△する」と暗記させることではなく、状況を判断し、自分で行動を選び取るための土台——つまり冷静さや自己コントロール、状況判断力といった非認知能力を育てる営みでもあります。
そのためには、「危ないからダメ」「こうしなさい」と一方的に伝えるのではなく、「どう思う?」「どこが危なさそう?」と問いかけながら、子どもの考えを引き出す関わりが大切です。
親が落ち着いて状況を説明し、一緒に考える姿を見せること自体が、防災教育になります。
「こわいけれど、こうすれば少し安心だね」と言語化していくことで、子どもは感情と行動をつなげて理解できるようになり、もしものときの判断力にもつながっていきます。
今日から始める親子防災:家庭でできる3つの実践
「時間もないし、どこから手をつけてよいか分からない」というときは、すべてを一度に整えようとしなくて大丈夫です。
まずは、日常生活の中でできる範囲から、今日から始められる小さな実践を一つずつ積み重ねていきましょう。
ここでは、わが家で実際に行ってきた3つの取り組みをご紹介します。
実践①:停電ごっこと防災探検マップで「危険に気づく目」を育てる
最初の一歩としておすすめなのが、短時間の停電ごっこと、防災探検マップづくりです。
停電ごっこでは、暗くなった部屋の中で「懐中電灯はどこにある?」「足元に危ないものはないかな?」と一緒に確かめます。
その後、家の間取り図を簡単に描き、「地震のときに倒れそうな家具はあるかな」「逃げ道をふさいでいるものはないかな」と親子で話しながらマップに印をつけていきます。
子どもは背の高さや動き方が大人と違うため、冷蔵庫の上の物や、廊下の棚の出っ張りなど、大人が見落としがちなところに目を向けてくれます。
「よく見つけたね」「そこに気づいたのはすごいね」と伝えることで、「自分の気づきが家族の役に立った」という感覚が生まれ、危険に気づく目を育てることにつながります。
作ったマップは、リビングなど家族が目にしやすい場所に貼り、時々見直したり書き足したりしていくと、意識も自然と継続します。
実践②:“心の安心”も入れるわが家の防災リュックづくり
次のステップとして、防災リュックの中身を子どもと一緒に見直してみましょう。
水や非常食、救急セットなどの基本的な備えに加え、「何が入っていると安心できるかな?」と子どもに尋ねてみると、ぬいぐるみや家族写真、好きな本など、意外な答えが返ってくることがあります。
大人の目線だけで「必要・不要」を決めてしまうのではなく、子どもの提案を受け入れながら中身を一緒に選ぶことは、不安な状況でも自分で心を落ち着かせる方法を持つ練習にもなります。
また、「これは賞味期限が切れていないかな?」「季節に合っているかな?」と、定期的にチェックする役割を子どもに任せると、「自分も家族の備えを支えている」という意識が育っていきます。
このように、防災リュックを「命を守る物」だけでなく心の安心も一緒に備える道具として位置づけていくと、備えが義務ではなく、家族で支え合う取り組みとして感じられるようになります。
実践③:おうちキャンプや防災センター体験で防災を“自分ごと”にする
防災を机の上の知識で終わらせないためには、体験を通して「自分ごと」として感じられる場面をつくることも大切です。
家で行う簡単なおうちキャンプでは、カセットコンロでお湯を沸かしたり、ランタンの明かりだけで過ごしてみたりしながら、「電気やガスが止まったらどうする?」を実際に考えることができます。
さらに、地域の防災センターを訪れることも大きな学びになります。
私たち家族が訪れた市の防災センターでは、地震や強風などいくつかの体験コーナーがありました。
職員の方の説明を聞いたあと、震度7相当の揺れを体験する装置に乗ると、子どもたちはテーブルにつかまりながら動くこともできず、「本当に立てないね」「家具が倒れてきたらもっと怖いね」と口にしていました。

展示フロアには、過去の大きな地震の様子を伝えるパネルも並んでいました。
写真や文章を読みながら、「このときの人たちはどんな気持ちだったかな」「自分たちが住んでいる地域で地震が起きたらどうなるだろう」と親子で話し合うことで、テレビのニュースより一歩踏み込んだ学びが生まれます。
こうした体験は、単に情報を覚えるだけでなく、「自分だったらどうするか」を考えるきっかけになります。
家に帰ってから「今日見てきたことを、わが家の備えにどう生かそうか?」と話し合うことで、防災センターが一度きりのイベントではなく、日常の防災教育へとつながります。
防災でうまくいかなかった日の学び:親子でつくるやり直しの力
ここまで読むと、「うちはこんなふうにうまくできないかもしれない」「怖がりな子なので心配」という思いが浮かぶかもしれません。
実際、わが家でも最初からすべて順調だったわけではなく、停電ごっこをしたときには、娘が真っ暗になった瞬間に固まってしまい、「もうやりたくない」と涙目になってしまったことがあります。
そのときの私は、「大丈夫だよ」「こわくないよ」と声をかけることで精一杯で、娘が何を一番怖いと感じたのか、じっくり聞く余裕がありませんでした。
後になって、「急に真っ暗になるのが一番こわかった」「どこに行けばいいか分からなかった」と教えてくれたことで、次にやるときは「この部屋で一緒に懐中電灯を持ってから始めようね」と、子どもの怖さを言葉で教えてもらい、それに合わせてやり方を変えることの大切さに気づきました。
また、防災家族会議を始めた当初は、大人ばかりが話して、子どもたちがどこか他人事のような表情をしていた時期もありました。
そのときに質問タイムを長くして、親が話す時間は短くしてみると、子どもたちは「冬に地震が来たら?」「おじいちゃんの家にいる時は?」と、自分で場面を想像して質問してくれるようになりました。
防災教育は、一度の体験や一度の話し合いで完成するものではありません。
大切なのは、うまくいかなかった経験を「失敗」と切り捨てず、「次はこうしよう」と親子で話し合う材料にすること。
「一緒に少しずつやり方を見つけていこうね」と伝えることで、子どもに「失敗してもやり直せる」という安心感を与えることができます。
今日から始める“わが家の防災と心の備蓄”の第一歩
防災教育は、「もしものときにも、自分で動ける」という自信と、家族で支え合えるという信頼感を育てていく営みです。
それは、命を守る力だけでなく、自己肯定感や判断力、他者を思いやる心にもつながります。
”防災グッズ”をフル装備するより、懐中電灯を家族で確認する、寝る前に「今地震が来たら何で頭を守る?」と会話してみる。
数分でできる小さな行動の積み重ねが、話し合って備えた経験として記憶されます。
防災は家族みんなで作っていく習慣。「あなたはどう思う?」「もしこうなったらどうする?」と問いかけながら、「あなたの命が大切だよ」というメッセージを日々の会話で伝えていきましょう。
まずはこの夏、防災の話をして、わが家だけの安心アイテムを一つ決める一日をつくってみましょう。その一歩が、いつか家族にとって大きな安心へとつながっていきます。
【執筆者:まさこ先生】
元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。
→筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら
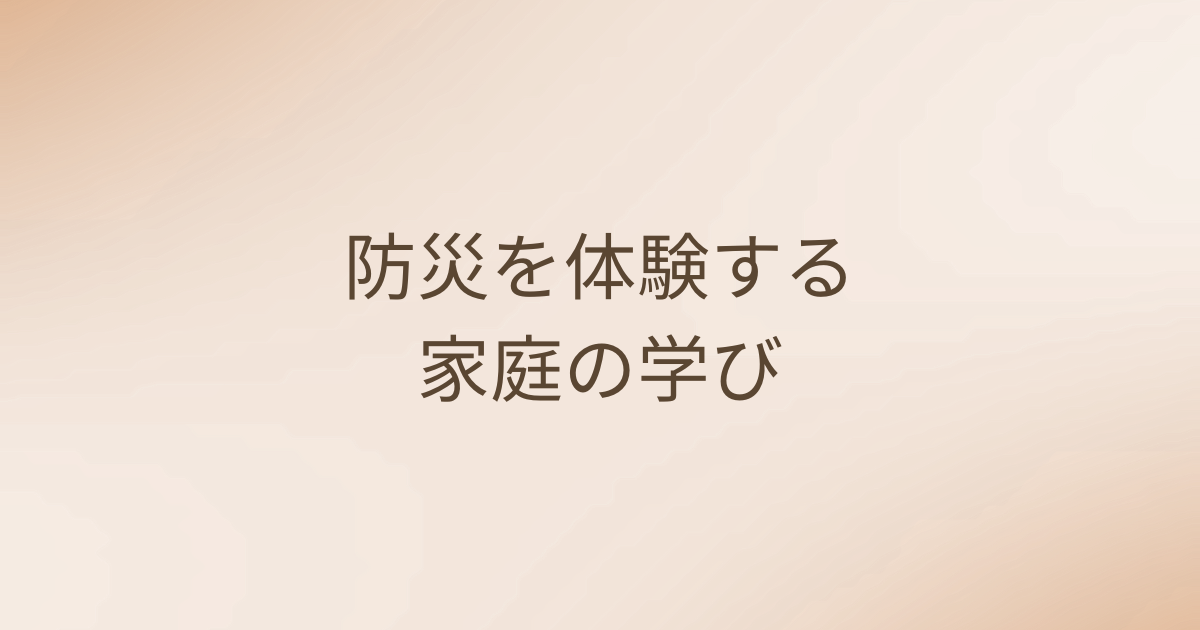
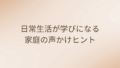

コメント