この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもの成長を見てきた経験から、家庭で実践できるキャリア教育の方法のうち、「働くことの意味」の伝え方について解説します。
「お母さん、働くって何?」息子が小学3年生の時に突然投げかけたこの質問に、小学校教員として長年子どもたちと接してきた私でも、一瞬言葉に詰まりました。
働くことについて考える機会は、子どもの将来への第一歩です。特に夏休みは、親子でじっくり話し合ったり体験したりする絶好のチャンスとなります。
しかし「お金をもらうため」といった表面的な理解だけでは、働くことの本当の価値は伝わりません。
この記事で紹介する内容は、「家庭での学びと体験」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。
→子ども主体のおうち夏祭り|自己肯定感につながる家庭イベントの工夫
仕事の価値を子どもに響かせる「たった一つの伝え方」
「働くって何?」というシンプルな問いに対し、「お金を得るため」という表面的な回答で終わらせないことが、キャリア教育の第一歩となります。
働くことは、単にお金を得る活動ではありません。人の役に立つ、自分の持っている力を使う、学んだことを社会で活かすなど、もっと豊かな意味があるのです。
教員時代、私は子どもたちに「働くことは、人を助け、喜ばせる活動である」という働くことの本当の意味を伝えていました。
例えば、コンビニの店員は、レジでお金をもらうだけでなく、商品を整理したり、困っている人に道を教えたりして、お客さんが気持ちよく買い物できるように人を助けています。
自分の仕事の動機を伝える際も、「子どもたちが『できた!』って嬉しそうな顔を見るのが大好きだからだよ」と、自分の喜びと他者の貢献を結びつけて話すことで、子どもは自然と「誰かを喜ばせる仕事がしたい」という利他的な価値観を持つようになります。
意気込んで話す必要はありません。何気ない普段の会話こそが、「働くことは人を喜ばせること」という利他的な価値観を子どもの心の中に育てていきます。
親は意識的に、自分の仕事の「誰かの役に立った点」を一つだけ具体的に話す習慣をつけましょう。この利他の精神こそが将来のモチベーションの源泉となります。
お手伝いは最高の職業体験!「働く喜び」を教える家庭での実践ステップ
家庭でのお手伝いは、自己有用感を育む最高の機会であり、働くことを体験する最初のステップです。
息子が小学2年生の頃に任せた食器洗いの例では、単に「お皿をきれいにする」だけでなく、「きれいなお皿で明日の朝ごはんが食べられる」と、家族への貢献を具体的に伝えました。
娘には洗濯物をたたむ中で「どうやったらシワにならないか」を自分で発見する機会を与え、「家族みんなが気持ちよく着られるね」と感謝と貢献を言葉にしたのです。
こうした日常の小さな体験が、責任感と自己肯定感を伴う、働くことの本当の意味を教えてくれます。
お手伝いで「働く喜び」を伝えるには、いくつかのポイントがあります。
結果だけでなく、過程での工夫や努力を認めること。「誰のために」「どんな役に立つのか」を具体的に伝えること。失敗を許容し、やり方を自分で発見する機会を与えること。そして、家庭内での役割意識を持たせることです。
特に、失敗を許容し、やり方を自分で発見する機会を与えることは、将来の問題解決能力を育みます。
この日常の小さな体験こそが、責任感と自己肯定感を伴う、働くことの本当の意味を教えてくれるのです。
「なぜ働くの?」を解決!【6・9・11歳別】親の正しい回答例と会話術
子どもからの素直な疑問には、子どもの認知発達段階に合わせて、伝える内容を段階的に変える必要があります。
6~8歳の子どもは「なぜお金がいるの?」という疑問を持ちます。
この時期には「家族がごはんを食べ、お家に住むために必要」と身近な生活に限定して答え、生活の維持とお金の結びつきを伝えましょう。
9~10歳になると「どうして色んな仕事があるの?」と視野が広がります。
「みんなが困らないように、助け合いながら役割分担している」と社会の構造を教え、社会の相互扶助について理解を促します。
11~12歳では「将来何をすべき?」という自己への問いが生まれます。
「自分の得意なことや好きなことで、みんなに喜んでもらえるのが働く楽しさ」と自己実現と貢献の結びつきを伝え、内発的動機を促しましょう。
このように、子どもの認知発達段階に合わせて働くことの意味を段階的に伝えることで、内発的な動機付けによる将来への興味や関心を自然に育てていくことができます。
この段階的アプローチは、発達心理学における「職業選択の準備段階」を支える土台となるのです。
将来の夢を育む!夕食の会話で「親の仕事」をキャリア教育につなげるコツ
日常の中で働くことについて話し合う習慣を作ることは、社会で求められる問題解決や協力の大切さを、家族という安全な場で伝えることにつながります。
わが家では夕食の準備をしながら「今日は誰かのために頑張ったことある?」と聞くようにしていました。
子どもが「友達に消しゴムを貸した」「給食の配膳を手伝った」と話したら、「ありがとうと言われてどんな気持ちだった?」と感情に共感することが重要です。
親自身の仕事の話も「今日は仕事で困ったことがあったけど、みんなで協力して解決できたよ。チームワークって大切だね」というように、チームワークや問題解決という抽象的な概念を、具体的なエピソードで伝えます。
効果的な話し合いのためには、子どもの話を最後まで聞き、「すごいね」「よく気づいたね」と認める言葉をかけましょう。
「どんな気持ちだった?」と感情に共感し、「次はどうしたいか」未来への希望を聞くことも大切です。
こうした会話の積み重ねが、社会で求められる問題解決や協力の大切さを、家族という安全な場で自然に伝えます。
「あなたがしてくれたことで、誰が、どう喜んだか」を具体的に言語化し、共感性を高めていきましょう。
SEL教育も同時に実現!お手伝いで身につく「社会性」と「問題解決力」
働くことの意味を理解することは、職業そのものだけでなく、その奥にある「人を喜ばせたい」という気持ち、すなわち向社会的行動を育む土台になります。
地域のお年寄りへのお礼にクッキーを作った体験では、「おばあちゃんはどんなクッキーが好きかな?」「どんな渡し方をしたら喜んでもらえるかな?」と、相手の気持ちを想像させる問いかけをしました。
これにより、子どもたちは「人を喜ばせるには相手を思いやる気持ちと工夫が必要だ」と学びます。
日常のお手伝いでは、身につくSEL(社会性と情動の学習)の力をまとめます。
- 自己認識:お手伝いを通して「自分にはこんなことができる」と気づく自己有用感として育ちます。
- 自己管理:責任を持って最後まで取り組む経験を積むことで、粘り強さやグリットとして身につきます。
- 社会的認識:家族や周りの人の気持ちを考えることで、共感性や利他性として養われます。
- 対人関係スキル:協力して作業することで相手との関わり方を学ぶチームワークとして発展します。
- 責任ある意思決定:「どうしたら上手くできるか」を考える習慣をつけることで、問題解決能力として磨かれます。
家庭でのお手伝いや地域との交流は、非認知能力を無理なく身につける貴重な機会です。
特に、「誰かの役に立ちたい」という利他的な動機こそ、困難を乗り越える強い意志の源泉となります。日常の行動を意識的にSELに結びつけて語りかけましょう。
まとめ:次のステップへ
働くことの意味を理解することから、家庭でのキャリア教育は始まります。
お金をもらうためだけでなく、人の役に立つ喜び、自分の力を活かす楽しさ、みんなで協力する大切さなど、働くことの豊かな意味を子どもに伝えていきましょう。
今日からできる具体的な実践として、子どもに簡単なお手伝いをお願いしてみてください。
「ありがとう、助かったよ」と具体的に感謝を伝えましょう。「今日は誰かのために何かした?」と聞いてみるのも効果的です。親自身の仕事の話を誰が喜んだかに焦点を当てて話してみることもおすすめします。
家庭での小さな体験や日常的な会話が、子どもの価値観を育て、将来への夢や目標を考える土台になります。
親も一緒に楽しみながら、働くことについて考える時間を作ってみてください。
働くことの意味が分かったら、次は親自身の仕事について子どもに分かりやすく伝える方法を学びましょう。→親の仕事を年齢別に分かりやすく伝えるコツ
【執筆者:まさこ先生】
元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。
→筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら
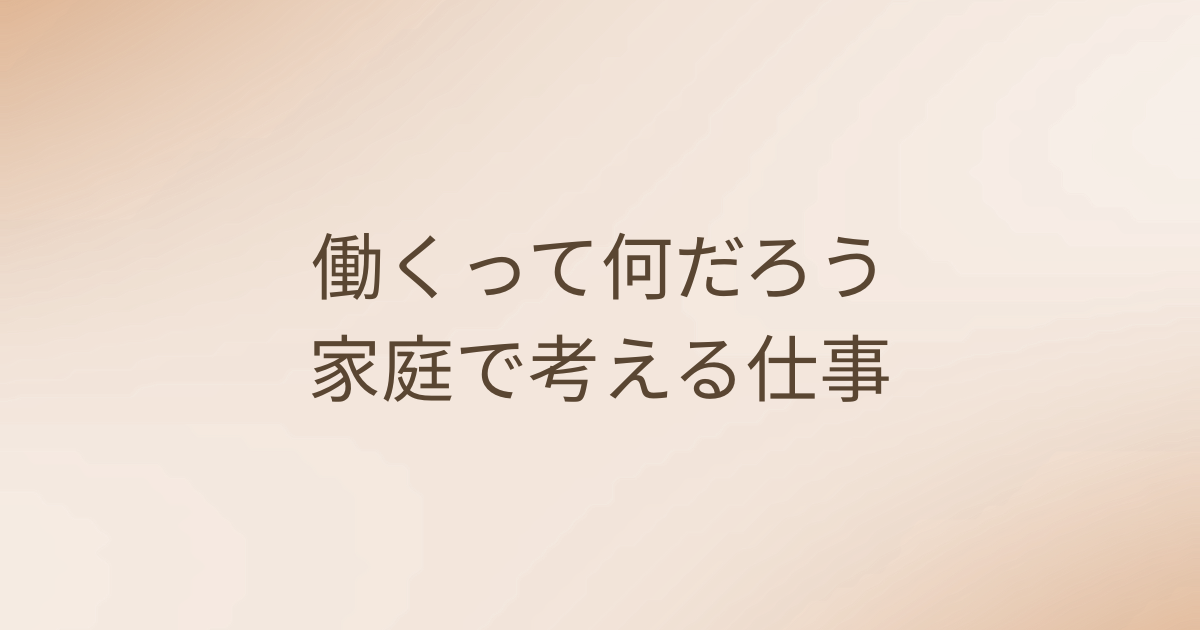
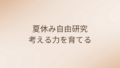
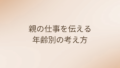
コメント