この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもの成長を見てきた経験から、家庭で実践できるキャリア教育のうち、体験を将来の夢へとつなげる親子の会話の工夫ついて解説します。
外部体験や家庭内での試み(家事分担など)で得られた気づきは、日常会話の積み重ねの中で静かに芽吹きはじめます。朝の支度中、夕食の時間、寝る前のほんの数分。
そうした何気ない瞬間に交わす会話の中で、子どもは自分の興味や可能性を語り始めるのです。
この記事で紹介する内容は、「家庭での学びと体験」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。
→子ども主体のおうち夏祭り|自己肯定感につながる家庭イベントの工夫
【習慣化】日常の「5分」で夢を深掘りする3つの質問
特別な時間を設けなくても、生活のあちこちに会話のチャンスは転がっています。
朝ご飯のときには「今日はどんな発見があるかな?」と一日への期待を膨らませる会話から始めましょう。
習い事帰りの車の中では「今日一番面白かったことは?」「もし時間が無限にあったら、何をやりたい?」といった妄想を広げる問いかけも効果的です。そして寝る前の5分には「将来やってみたいことはある?」とゆったり聞いてみてください。
子どもがまだ具体的でなくても、「面白そうだね」と肯定することで、自分の考えを表現する安心感が生まれます。この安心感こそが、自己認識を育てる土台になるのです。
子どもは親に受け入れられることで、「自分はこれが好きなんだ」「こういうことに興味があるんだ」と自分自身を理解していきます。
大切なのは、親も答える側になること。
「お母さんが子どもの頃はね…」「お父さんも実は…」と自分の経験や夢を語ることで、会話は一方的な質問ではなく、信頼に基づく双方向のコミュニケーションになります。
さらに「どんな○○?」「そのために何が必要?」という質問を重ねることで、子どもは漠然とした興味から具体的なイメージへと思考を深め、責任ある意思決定の力を養います。
自己肯定感を育む!「面白そうだね」で主体性を引き出すコーチング
「そんなことできるわけない」ではなく、「それは面白そうだね、やってみたら?」と肯定的に受け止めることで、自己効力感が育ちます。
「自分はできる」という自信は、困難に直面したときに諦めずに取り組む力の源になるのです。
さらに子どものやりたいことを膨らませるには、親自身のワクワクも混ぜ込んでみましょう。
「ロボットを作りたいんだ」と言われたら、「お母さんなら、お掃除を手伝ってくれるロボットがいたら嬉しいな!」と自分の想像を重ねることで、会話が一方通行ではなく、共に夢を描く時間になります。
そして、コーチング的な質問で子どもの主体性を引き出します。
「それを実現するために、何ができると思う?」「どうすれば実現できそう?」「誰と相談したい?」——こうした問いかけによって、子どもは漠然とした夢から具体的な行動や計画を考え始めます。
また、小さな成功体験を「昨日は○○を頑張ったね」「今日のお手伝い、すごく丁寧だったね」と具体的に認めることで、子どもは「やればできる」と感じ、次の挑戦に前向きになります。
ノートに一言メモする「成長ジャーナル」を作って、親子で振り返るのも効果的です。
- 9月15日:初めて自分で卵焼きを作った
- 10月3日:妹に折り紙を教えてあげた
自分の行動を振り返り記録する習慣は自己管理力を育て、体験を文章にまとめることで言語化能力が磨かれます。
また、過去の記録を見返すことで自己肯定感が高まり、「自分はこんなにできるようになった」という達成感を実感できるでしょう。
さらに、親子で一緒に振り返る時間は、子どもが自分の成長を客観的に認識するメタ認知能力の発達も促します。
今日から使える!シーン・年齢別「NG/OKフレーズ」完全保存版
将来の夢を引き出す会話:価値観に注目する
ここでは、夢を具体化し、子どもの自己認識を深めるための会話例を紹介します。
興味の芽を見つける
子どもが何に興味を持っているかを探る会話では、具体的な活動から、その奥にある価値観を見つけることが大切です。
たとえば、「最近、何が一番楽しい?」と聞いたとき、子どもが「図工で絵を描くこと」と答えたとします。「どんな絵を描くのが好き?」とさらに掘り下げると、「動物の絵。見た人が笑顔になるような絵」という答えが返ってくるかもしれません。
ここで親が「人を喜ばせるのが好きなんだね。他にもそういうことある?」と価値観に注目すると、子どもは「お祭りで飲み物配ったときも、喜んでもらえてうれしかった」など、別の場面を思い出します。
こうした会話を通じて、「『人を喜ばせる』っていうのが、あなたの好きなことかもしれないね」と本質的な価値観を言語化してあげることで、子ども自身が自分の興味の核心に気づくことができるのです。
具体的にイメージさせる
漠然とした夢を具体的にイメージさせ、今できることを考えさせることで、将来の目標を現在の行動につなげます。
子どもが「ロボットを作る人になりたい」と夢を語ったら、まず親は「どんなロボット?」と具体的に掘り下げます。「お年寄りの人を助けるロボット!」と答えたら、「そのロボットは何ができるの?」と機能や役割を質問しましょう。
年齢・性格別「問いかけフレーズ」
子どもの学年だけでなく、性格タイプやコミュニケーションの得意・苦手も考慮した声かけが大切です。
また、短所からも芽を伸ばす視点や、成長を実感させる問いかけを取り入れることで、多様な子どもたちの可能性を引き出すことができます。
年齢別の声掛け
低学年向け(6~8歳)
具体的で短い言葉で、行動と結果を具体的に結びつけることで、自己認識を深めます。
- 「今日は誰かを助けた?」
- 「どんな気持ちだった?」
- 「お手伝いしてくれてありがとう。みんな助かったよ」
- 「あなたのおかげで家族が笑顔になったね」
- 「すごいね!よく気づいたね」
中学年向け(9~10歳)
どう考えたか、どう工夫したかを言語化させることで、思考力と自己管理の力を育てます。
- 「今日の工夫、教えて」
- 「どうやって解決したの?」
- 「その考え、面白いね。どうしてそう思ったの?」
- 「チームで協力できたね。どんなふうに協力したの?」
- 「問題を見つけて解決するのが仕事の一つだよ」
高学年向け(11~12歳)
自分の興味や得意なことを言語化することで、自己認識を深め、責任ある意思決定の力を育てます。
- 「将来どんな仕事に興味ある?」
- 「そのために今できることは何だと思う?」
- 「その経験から何を学んだ?」
- 「自分の得意なことって何だと思う?」
- 「それを将来どう活かせると思う?」
- 「仕事を通じて社会を支えるんだよ」
性格タイプ別
発達段階や個性の違いを尊重しながら、一人ひとりに合った声かけを工夫することで、すべての子どもが自分らしく夢を描けるようになります。
コミュニケーションが得意な子向け
積極的に話す子には、より深く考える問いかけで思考を広げます。
- 「それって、どういうこと? もっと詳しく教えて」
- 「他の人はどう思うと思う?」
- 「その意見、すごくいいね。違う角度からも考えてみようか」
- 「みんなをまとめる力があるね。リーダーとして大切なことって何だと思う?」
コミュニケーションが苦手な子向け
ゆっくり、安心して表現できる環境を作ります。
- 「うまくいかなかったね。でも何が分かった?」
- 「言葉じゃなくても、描いてみる? 書いてみる?」
- 「ゆっくり考えていいよ。お母さんは待ってるから」
- 「一年前と比べて、何ができるようになった?」
- 「静かに観察する力、すごいね。それも大事な才能だよ」
慎重派・失敗を恐れる子向け
小さな挑戦を肯定し、失敗からの学びを強調します。
- 「やってみたこと自体がすごいよ」
- 「失敗したときに何が分かった? それが宝物だね」
- 「最初はみんなできないものだよ。お母さんもそうだった」
- 「挑戦したことで、何か新しい発見があった?」
活発で行動的な子向け
エネルギーを認めつつ、振り返りの習慣をつけます。
- 「たくさん動いたね! 一番楽しかったのはどれ?」
- 「次はどんなことに挑戦したい?」
- 「今日の経験で、何か気づいたことある?」
- 「行動力があるね。それを計画的に使えたらもっとすごいよ」
忙しい毎日でも”極短1フレーズ”で夢を応援
特別な時間を作らなくても、日常の何気ない瞬間が子どもの夢を育てる機会になります。
保護者が忙しくても使える、シンプルで効果的な「夢応援ワード」を場面別にご紹介します。
朝の一言(5秒でOK)
親が応援していることを感じることで、安心して挑戦できる心の土台ができます。
- 「今日は何が楽しみ?」
- 「応援してるよ!」
- 「いってらっシャイン!(家庭独自の掛け声例)」
- 「キミならできる」
帰宅時の一言(玄関先で)
- 「おかえり。今日のMVPは?」
- 「何か発見あった?」
- 「誰かを笑顔にした?」
- 「困ったことあった? どうした?」
「誰かを助けた?」と聞くことで、「働くことは人の役に立つこと」という意識を日常的に育てます。
夕食時の一言(食卓で)
- 「今日のグッドニュースは?」
- 「明日はどんなことしたい?」
- 「お父さんは今日こんな失敗したよ(笑)」
- 「それ、面白いアイデアだね!」
親自身の体験も共有することで、社会的認識を育てます。
寝る前の一言(布団の中で)
- 「今日、よく頑張ったね」
- 「あなたの工夫、すごかったよ」
- 「明日も楽しみだね」
- 「いい夢見てね。夢の冒険、行ってらっしゃい!」
小さな成果を認めることで、自己肯定感が育ちます。
家庭ごとにカスタマイズ:「我が家の応援スタイル」を作ろう
各家庭で独自の掛け声を作ってみるのもおすすめです。「ファイトだファイト!」「チャレンジャー出発!」など、家族だけの合言葉があると、それ自体が絆になります。
また、子ども自身に「家族応援カード」を作ってもらうのも効果的です。
画用紙に「パパが疲れているときに言ってほしい言葉」「ママが頑張ったときにかけたい言葉」「兄弟を応援する魔法の言葉」を書いてもらい、冷蔵庫に貼っておきます。
親が応援されることで、子どもは「応援する側」の喜びも知り、双方向のコミュニケーションが自然に生まれます。
NGフレーズとOKフレーズ:肯定的な言葉を選ぶ
会話の中で、つい言ってしまいがちなNGフレーズと、代わりに使いたいOKフレーズを対比してご紹介します。
親自身も完璧ではなく、一緒に成長していく「伴走者」であることが大切です。評価する立場ではなく、寄り添う姿勢が、子どもの多様な職業観や変化を前向きに受け止める力を育てます。
以下、「つい言ってしまう度合い別」に整理しました。自分がどのフレーズを使いがちか、振り返ってみてください。
夢を語ったとき
子どもの夢を否定せず、具体的に考えるきっかけを与えることで、想像力と計画力を育てます。
- NG「そんなの無理だよ」「現実的に考えなさい」「お金にならないよ」
- OK「面白そうだね。どんなふうになりたいの?」「そのために何ができると思う?」「お母さんも応援するよ」
失敗したとき
失敗を責めるのではなく、改善を一緒に考える姿勢が、挑戦意欲と問題解決力を育てます。
- NG「だから言ったでしょ」「何やってるの!」「ちゃんとしなさい」「前にも同じ失敗したよね」
- OK「どうすればうまくいくと思う?」「次はどう工夫する?」「お母さんも一緒に考えよう」「失敗から学べることがあるね」
難しいことに挑戦するとき
挑戦を応援する言葉が、自己効力感を育てます。親がサポートすることを伝えることで、安心して挑戦できます。
- NG「それは早すぎる」「まだ無理だよ」「危ないからダメ」
- OK「挑戦してみよう。お母さんも手伝うよ」「失敗してもいいから、やってみようか」「どんな準備が必要かな?」
比較してしまうとき
他者との比較ではなく、子ども自身の成長に注目することで、自己認識と自己肯定感が育ちます。
- NG「お兄ちゃんはできたのに」「○○ちゃんはもっと上手だよ」「あなただけできないね」「みんなできてるのに」
- OK「昨日のあなたより成長してるね」「あなたなりの工夫があるね」「前よりできるようになったね」
夢が変わったとき
小学生の夢は変わりやすいもの。その変化を肯定することで、自分の興味を探求する自由を感じられます。時代とともに職業も変わり、親も不安だけど一緒に進む姿勢が大切です。
- NG「すぐ変わるんだから」「また変わるでしょ」「いい加減にしなさい」
- OK「新しい興味が出てきたんだね」「どうしてそう思ったの?」「色々試していいんだよ」
結果だけを見るとき
結果だけでなく過程を認めることで、継続する力と自己管理の力が育ちます。
- NG「結果が出なきゃ意味がない」「もっと頑張りなさい」「そんなんじゃダメ」
- OK「過程での工夫が素晴らしいね」「努力してる姿を見てたよ」「頑張ってる途中だね」
忙しいとき
子どもが話したいタイミングを大切にすることで、信頼関係が育ちます。
- NG「今忙しいから後にして」「そんなことどうでもいい」「また今度ね(結局聞かない)」
- OK「ちょっと待ってね。5分後に聞かせて」「今は手が離せないけど、夕飯のときに教えて」「聞きたいから、後でゆっくり話そう」
LINEやメールでの会話
対面と同じように肯定的な言葉を選びましょう。短文やスタンプだけでは誤解を招くこともあります。
- NG「ふーん」(スタンプのみ)「忙しい」(既読スルー)
- OK「すごいね!帰ったら詳しく聞かせて」「応援してるよ」「写真見たよ。頑張ったね!」
評価者から「伴走者」へ:親の3つの基本姿勢
ここまで、具体的な会話の工夫についてお話ししてきました。しかし、どんなに良いフレーズを知っていても、親の基本的な姿勢が伴わなければ、子どもの夢は育ちません。
最後に、夢を育てる親として大切にしたい3つの姿勢についてお話しします。
夢は変わっていい:「価値観」に注目する
小学生の夢は流動的で当然です。「ケーキ屋さん」から「看護師」へ、「看護師」から「先生」へと変化することを、むしろ肯定しましょう。大切なのは職業そのものより、その奥にある価値観です。
職業が変わっても、「人を喜ばせたい」「誰かの役に立ちたい」という気持ちが一貫していれば、それが子どもの軸になります。
「なぜそう思ったの?」と聞くことで、共通する価値観を一緒に見つけることができます。
具体的には、家庭内の具体的な感情や出来事に置き換えて確認します。たとえば、「人を喜ばせたいんだね。それは、『おばあちゃんにクッキーをあげた時』と似た気持ちかな?『新しいゲームをクリアした時の達成感』とは違う?」と問いかけてみましょう。
価値観が定まったら、「この価値観を活かせる職業リスト」を親子で一緒に作成しましょう。
次は「人を喜ばせたい」という価値観(10年後の未来予想)の一例です。子どもが興味を持ちやすい最新の職業も含めることで、視野が広がります。
- イベントプランナー
- 介護士・看護師
- YouTuber・配信者
- カフェ店員・パティシエ
- 保育士・先生
- ゲームクリエイター
夢が変わることは、子どもが成長し、視野が広がっている証拠です。親はその変化を肯定し、「いろいろ考えているんだね」「新しいことに興味を持てるのは素敵だね」と応援しましょう。
また、夢を諦めたときこそ、価値観で肯定することが大切です。
「夢はケーキ屋さんじゃなくなったけど、『人を笑顔にしたい』っていう君の軸は全然ブレてないよ」と、職業の変化ではなく、一貫する価値観を認めることで、子どもの自信を育てます。
親は評価者ではなく「伴走者」になる:完璧でなくていい
子どもの夢を聞いたとき、親はつい評価者になってしまいがちですが、親の役割は、評価することではなく、一緒に考え、応援することです。
評価者ではなく、伴走者になる言葉の選び方
子どもの夢に対する反応を少し変えるだけで、子どもの挑戦意欲は大きく変わります。
次はNGフレーズ(評価者の言葉)、OKフレーズ(伴走者の言葉)の一例です。
- 「そんな夢、食べていけないよ」
「面白そうだね!食べていけるか一緒に調べてみようか?」 - 「もっと現実的な仕事を考えなさい」
「そのためにどんな準備ができるかな?」 - 「才能がないとダメだよ」
「その仕事をしている人に話を聞いてみる?」
このように、否定ではなく「一緒に考える」姿勢が、子どもの挑戦意欲を育てます。
「逆張り質問」で問題解決能力を育てる
夢を応援するだけでなく、あえて「その夢を実現しないとしたら、どんな理由が考えられる?」と逆の質問を投げかけるのも効果的です。
たとえば、「パティシエになりたい」という子どもに「もしパティシエになれなかったとしたら、どんな理由が考えられるかな?」と尋ねると、子どもは「練習が足りない」「体力がない」「お店を出すお金がない」などと考え始めます。
この質問により、子どもは自分で課題を発見し、それに対する対策を考える力(リスクヘッジと問題解決能力)を身につけます。
否定するのではなく、現実的な視点を子ども自身が持てるよう導くのです。
たとえ最終的にその職業に就かなくても、そのために努力したことはすべて子どもの財産になります。
親自身が「完璧でない姿」を見せる
親が完璧でないことを見せることも大切です。親も一緒に学び、成長している姿を見せることが、最高の伴走者としての役割です。
親が自分の失敗や改善の過程を具体的に話すことで、子どもは「失敗は恥ずかしいことではなく、成長のチャンス」だと学びます。
次は親の具体的な失敗と改善の過程をオープンにする例です。
- 「お母さんもこの前、新しいパソコンの使い方を間違えて怒られちゃったんだ。でも、そこから新しいやり方を学んだよ」
- 「お父さん、昨日プレゼンで緊張して言葉が詰まっちゃった。次はもっと練習してから臨むつもりだよ」
- 「料理で失敗しちゃった。でも、失敗したから次はもっと美味しくできると思うんだ」
長期的な視点を持つ:目の前の結果より「過程の成長」に注目
子どもの夢は、すぐに実現するものではありません。小学生の今は、様々な体験を通して興味を広げ、自分の可能性を探る時期です。
「失敗→改善」のサイクルや「小さな成功体験」が積み重なることで、子どもは困難に直面したときに諦めずに取り組む力を身につけます。
親として大切なのは、目の前の結果だけを見るのではなく、子どもが身につけている力に注目することです。
うまくいかなかったときでも、計画を立てる力、工夫する力、諦めない力など、過程での成長を認めましょう。
子どもの成長を「スキル名」で承認する
子どもの小さな変化に気づいたら、それを将来役立つ「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」として言語化してあげましょう。
こうした承認の仕方は、子どもに「今やっていることが将来につながっている」という実感を与え、自己肯定感と将来への自信を育てます。
- 「最近、お手伝いが丁寧になったね」
→「これは『品質管理能力』が上がった証拠だね!」 - 「困っている人に声をかけられるようになったね」
→「それは社会で通用する『ホスピタリティ』だよ」 - 「失敗しても次に挑戦できるようになったね」
→「これはビジネスで一番大切な『レジリエンス(回復力)』だ!」
親自身の長期目標を子どもと共有する
子どもだけでなく、親自身が「10年後にどんな大人になりたいか」を子どもに伝えることも効果的です。
「お母さんは10年後、地域の人の役に立てるような仕事ができる人になりたいな」「お父さんは、もっと新しいことに挑戦できる大人になりたいと思ってるんだ」
親が自分の成長目標を語ることで、子どもは「大人も成長し続けるんだ」と理解し、長期的な視点で自分の成長を捉えられるようになります。
親子で互いの目標を共有する習慣は、家庭全体を「成長を支え合う場」に変えていきます。
結び:評価者から「伴走者」へ。さあ、今日から会話を楽しもう!
夢を育てる親子会話に、特別な時間を作る必要はありません。
親自身が楽しみながら、子どもと一緒に失敗し、一緒に笑い、一緒に成長する過程すべてが、子どもの夢を育てる貴重な時間です。
長い視点で子どもの成長を見守るために、こんな工夫もおすすめです。
親子の成長日記:ノートに一言ずつメモ
- 今日の会話:「ケーキ屋さんになりたい」
- 子どもの言葉:「みんなを笑顔にしたいから」
- 親の気づき:人を喜ばせたい気持ちが強い子なんだ
数年後に読み返すと、「2023年10月:ケーキ屋さん→2025年10月:お菓子の研究者に興味」といった変化も成長の証として見えてきます。
10年後の家族手紙:親子それぞれが「10年後の自分」「10年後の家族」へ手紙を書き、封筒に保管
- 子ども:「10年後の僕へ。今はロボットが作りたいです。できるようになったかな?」
- 親:「10年後の私へ。今日、子どもの夢を笑顔で聞けた自分を褒めたい」
家庭でのキャリア教育に、特別な費用も専門的な知識も必要ありません。
少しだけ意識を変え、少しだけ工夫することで、子どもは確実に「働く力」と「生きる力」を身につけていきます。
今日から、子どもとの会話を楽しんでみてください。その積み重ねが、10年後、20年後の子どもの姿を作っていくのです。
【執筆者:まさこ先生】
元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。
→筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら
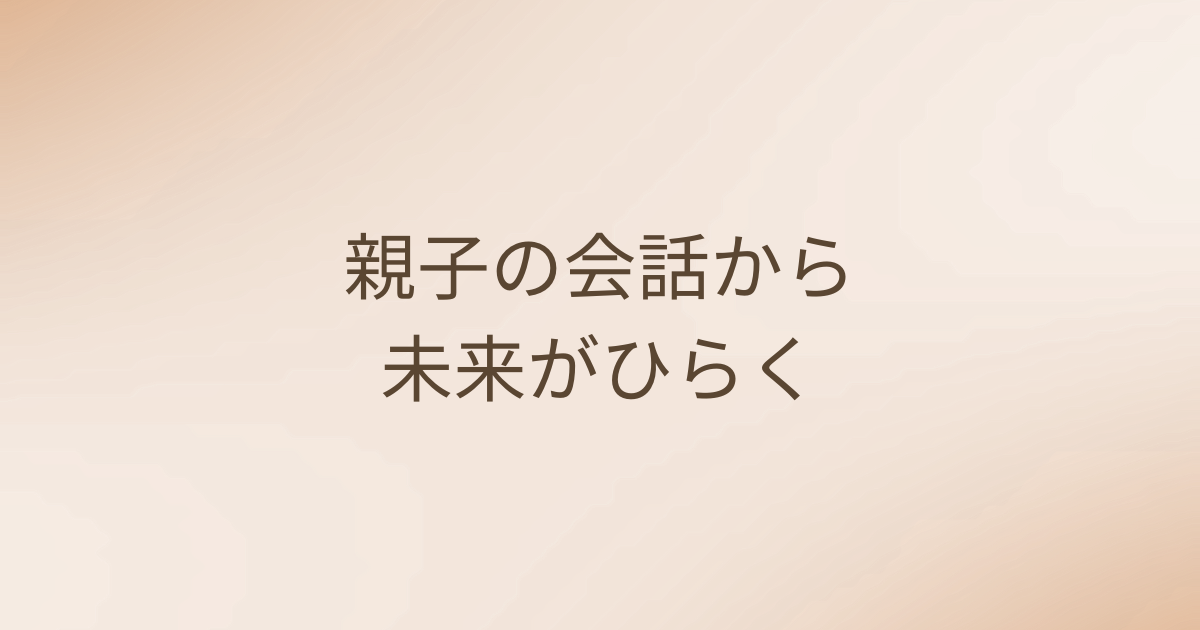
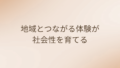
コメント