この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもの成長を見てきた経験から、家庭で実践できる親の小さな挑戦とそれが子どもの自発性につながることについて解説します。
「子どもに『挑戦しなさい』と言っても響かない。むしろ萎縮させてしまう…」そんなジレンマを抱えていませんか。
私自身も、共働きでの子育ての中で、そんなジレンマを抱えていました。新しいことを避ける子どもたちに、私は短歌を詠む姿を見せ続けました。
特別な才能や環境がなくても、”挑戦する背中”を見せること。それが、内向的だった子どもたちを「失敗してもいいから挑戦したい!」と変える奇跡を起こしました。
この記事で紹介する内容は、「家庭での学びと体験」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。
→子ども主体のおうち夏祭り|自己肯定感につながる家庭イベントの工夫
ステップ1: 子どもに「自分にもできる」自信を育む、親の小さな挑戦の宣言
子どもの挑戦意欲を引き出すため、まず、親が自ら挑戦する姿を見せましょう。
私はある夏、「短歌を毎日詠む」という小さな目標を掲げました。
水彩画や料理ではなく、あえて短歌を選んだのは、道具が要らず、日常をすぐに「成果」にできる手軽さと、五七五七七という制約が逆に試行錯誤を生むと考えたからです。
最初は五七五七七に言葉をはめる難しさに悪戦苦闘し、正直3日坊主になりそうな瞬間もありました。しかし、とにかく「挑戦することそのもの」を子どもたちに見せ続けることを意識しました。
うまくいかない日もありましたが、懸命に言葉を探す親の姿を見て、子どもたちの反応が変わっていきました。
親が、まず小さな一歩を踏み出す姿を見せることが、子どもたちの「自分もやってみたい」という自発性を引き出す最も大きな刺激となりました。
「私、今日から毎日5分だけ〇〇に挑戦する!」と、子どもに聞こえるよう宣言してみましょう。
この行動は、子どもの「自分にもできるかも」という自信(代理的経験)を引き出す上で最も有効な手段です。
目標を小さくすることで、成功体験を得やすくし、万が一失敗しても立ち直りやすい環境を作ることが大切です。
ステップ2: 親の「失敗と葛藤」をあえて見せる!家族の信頼を深める対話術
親だからといって、常に完璧である必要はありません。
むしろ、挑戦の結果が芳しくなかった時や、難しいと感じている葛藤を隠さずに分かち合うことが、家庭内の空気と子どもの心に大きな変化をもたらしました。
短歌がうまくいかず、「今日はピンとくるものができなかったな」と正直な気持ちを口に出すと、子どもたちは励ましや共感の言葉を返してくれました。
挑戦の結果や努力の過程を一人で抱え込まず、開示することで、家庭が「頑張ることが当たり前で、失敗しても大丈夫」という安心感のある空間に変わっていきました。
親の失敗の開示は、子どもにとって「親も人間である」という安心感を与え、親子間の信頼関係を深めます。
失敗した際には、「お母さん/お父さんも、これ難しいよ。でも、次はこうしてみる!」と具体的な改善のプロセスを言葉にして伝えましょう。
学校でも、自分の失敗を正直に認める教師は、子どもたちの信頼を集めます。
ステップ3: 自己肯定感を高める!「結果」より「努力の過程」を褒める可視化術
挑戦において、結果の良し悪しにこだわる必要はありません。大切なのは、結果に至るまでのプロセス(過程)を記録し、家族で楽しむことです。
私は、夏の食卓での料理の失敗といった形にならない「思い出の断片」も積極的に短歌のネタに変えていきました。
よし、1首できたぞと、「豆板醤 まちがえ辛き 中華鍋 家族の笑顔 絆深めり」と詠むこともありました。
進捗が誰にでも分かるように、作品をノートに貼ったり、テーマごとに色シールを使って分類したりと、努力の過程を視覚的に可視化しました。
例えば「食」にまつわる歌ばかりの日には、親子で爆笑し、思い出を共有しました。
大人がプロセスを心底楽しむ姿は、子どもに「努力そのものが価値あるものだ」と伝わり、子どもの自分を知る力や、感情をコントロールする力を自然と育んでくれました。
小さな成功体験や、試行錯誤のプロセスを家族の見える場所に「努力の記録(例:ノート)」として意図的に開いておくことは、自己肯定感を育む上で極めて有効です。
お子さんが新しいことに取り組む際は、完璧な結果ではなく、失敗した工夫や粘り強い試行錯誤のプロセスを具体的に褒めましょう。
その姿勢が、将来困難に立ち向かう「主体性」の土台となります。
ステップ4: 子どもの表現力が爆発!家族で「言葉の壁打ち」を日課にする方法
短歌挑戦を始めて以降、家族の言葉の「壁打ち」が日常的な習慣となりました。
「今日の単語は何にしよう?」といったアイデア出しを家族みんなで日課にすることで、親子のコミュニケーションが倍増しました。
親が率直に「今日はなかなかいい言葉が思い浮かばなくて四苦八苦したよ」と苦労を語り合うことで、子どもたちからも積極的な提案が生まれます。
「青空」「向日葵」など、子どもならではの新鮮な視点に触れる機会が増え、さらには夫も便乗して川柳などの新しい”言葉遊び”に挑戦する流れができました。
短歌は、単なる作品作りではなく、家族の感受性を分かち合うツールとなったのです。
子どもたちは、親の苦闘や日々の気づきを分かち合う過程で、語彙力や創造力を刺激されます。夕食後など、リラックスしている時間に「今日の感情を五七五で表現してみない?」と遊び心のある提案をしてみましょう。
共通の言語活動で、言葉による思考力と家族の共感性が同時に高まります。
ステップ5: 三日坊主を防ぐ!親の挑戦を「日常の習慣サイクル」に変える継続術
どんな小さな挑戦でも、継続には困難が伴います。挑戦が苦しいと感じる時こそ、家族の声や姿を受け入れることが、継続のための強力なサポートとなることを実感しました。
短歌を毎日続ける中で、自然と子どもたちが応援団となってくれました。短歌をあえて家族に見せていたことで、私も無意識のうちに「続けるための環境」を作り出していました。
小さな挑戦を単発イベントで終わらせず、日常リズムの中に上手に組み込むことで、「継続の壁」を乗り越えやすくなります。
何かに取り組むことは、一人で背負い込むよりも、習慣として定着させて周囲に見守られながら続ける方がずっと容易になるのです。
挑戦が一段落したら、家族で振り返りミーティングを開き、親が先に次の目標や継続方法を宣言しましょう。
親が継続とサイクルを見せることで、子どもに「行動は続いていくもの」という価値観が伝わります。
学校での指導経験から、目標を誰にも話さない子は「三日坊主」になる傾向があります。挑戦をオープンにすることで、家族を「継続のための外部支援」に変えるのです。
ステップ6:自発性を加速!親の「次の挑戦宣言」で子どもの目標設定力を引き出す
挑戦の最大の成果は、「行動のサイクル」を家族全体に定着させることです。
私の家庭では、取り組みの区切りごとに振り返りの時間を作り、「今度はこんなこともしてみたいね!」と自由に語り合うのが恒例となりました。
この振り返りの場で、親が次の挑戦を宣言することが、子どもたちの自発的な目標設定を促す決定的なきっかけとなりました。
「今度は俳句にも挑戦してみようかな」と私が次の挑戦宣言をすることで、子どもたちも自ら目標を言葉にするようになりました。
特に、それまで何事にも消極的だった娘が、「失敗してもいいから、みんながやらないことに挑戦したい」と昆虫採集を始めたことは、大きな変化でした。
親の行動のサイクルが続くことで、挑戦は「特別な時だけのものではなく、毎日の中にある自分らしい習慣」へと変わっていきました。
大人が取り組みを振り返って新たな目標を設定する姿は、子どもに「行動は一回きりではなく、ずっと続いていくものなんだ」という大切な価値観を与えます。
親が自ら次の目標を見つけることで、子どもたちは自分も目標を見つけることへの許可を得て、自発的な目標設定力が育まれるのです。
まとめ:親の挑戦が子どもを育てる。夏休みはその絶好のチャンス
親が挑戦する姿を見せることは、子どもに「挑戦は特別なものではなく、日常の中に存在する前向きな行動である」と伝える最良の教育法です。
大切なのは華々しい成果ではなく、挑戦し続ける姿勢そのものに子どもは学びます。
本記事で解説した6つのステップを整理します。
- 親が小さな挑戦を宣言する(子どもに「自分にもできる」という代理的経験を与える)
- 失敗や葛藤を共有する(親子の信頼関係と挑戦への安心感を育む)
- プロセスを可視化し褒める(自己肯定感と主体性を強化する)
- 言葉で壁打ちする(子どもの表現力と創造性を刺激する)
- 習慣化し家族で応援する(三日坊主を防ぎ、継続力を養う)
- 親が次の挑戦を宣言する(子どもの自発的な目標設定を加速させる)
このサイクルを親が主導して回すことで、子どもたちは自然に「困難があっても前向きに立ち向かう力(生きる力)」を身につけます。その力は、将来、社会で活躍するための揺るぎない土台となるでしょう。
夏休みなどの長期休暇は、親にとっても新たな挑戦を始める絶好の機会です。
ご自身の小さな挑戦を通じて、子どもの人生に不可欠な「生きる力」を届けながら、ご自身の人生も豊かにしていきませんか。
【執筆者:まさこ先生】
元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。
→筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら
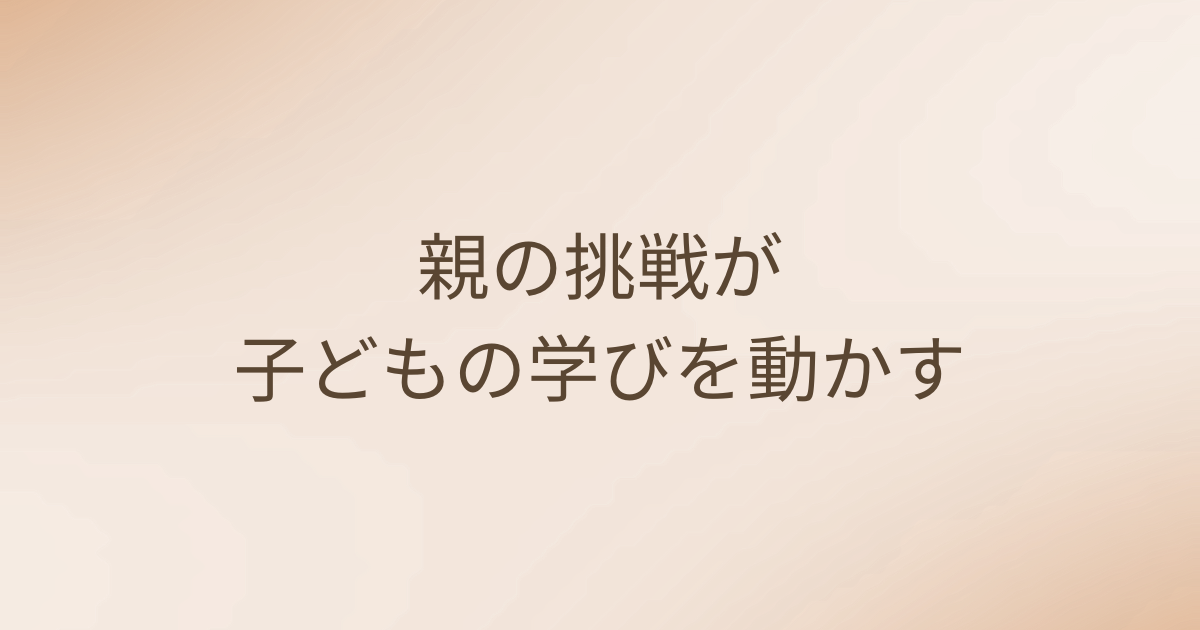
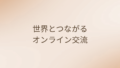
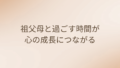
コメント