この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもと保護者に向き合ってきた経験をもとに、家庭で実践できる親の心の余裕の取り戻し方と子どもの非認知能力を育む関わり方について解説します。
夏休み明け、私は毎年のように、疲れ切った表情で学校に来るお母さん・お父さんたちと向き合ってきました。
生活リズムの乱れ、宿題や自由研究のプレッシャー、三度の食事づくり。子どもの思い出をつくりたい気持ちはあるのに、現実にはヘトヘトになってしまう親御さんがたくさんいます。
そんな中で私が強く感じてきたのは、「完璧な親でいなければ」という思い込みが、親の心を一番追い詰めているということです。
そして、そのプレッシャーが、子どもの自己肯定感や自律心といった「非認知能力」の育ちを妨げてしまう場面を、私は現場で何度も見てきました。
私自身も、わが子に「お母さん、最近怒ってばかりだね」と言われて、ハッとした一人です。
親の笑顔が減ると、家庭から安心感が失われ、子どもは「自分は大丈夫」という感覚を持ちにくくなってしまいます。
逆に言えば、「完璧さ」を手放し、親が心の余裕を取り戻していくことこそが、子どもの非認知能力を伸ばす近道になります。
この記事で紹介する内容は、「親子コミュニケーション」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。
→ 子どもが本音を話してくれる!“心を開く聴き方と問いかけ”完全ガイド
親の心の余裕がなくなったとき、家庭で起きていること
夏休みの終わりごろ、懇談でこんな声をよく聞きました。
「ついガミガミ言ってしまって、子どもの顔を見るのがしんどくなりました」
私自身も、子どもが小さい頃の夏休みは、頑張れば頑張るほど心の余裕がなくなっていく感覚を味わいました。
宿題や家庭学習が思うように進まず、つい強い口調になってしまったり、兄弟げんかが増えて「もう勝手にしなさい」と投げやりになってしまったり、家事と仕事に追われて子どもの話をゆっくり聞く余裕がなくなったり――こうしたことが重なっていきます。
そんな日が続くと、「また怒ってしまった」「いい親じゃないのかもしれない」と、親は自分を責めるようになります。
しかし、子どもの心の育ちという視点から見ると、本当の問題は「怒ってしまったこと」そのものよりも、親自身が心の余裕を失った状態が長く続いてしまうことにあります。
親が疲れ切った状態が続くと、子どもは「どうせ自分は怒られる側の存在なんだ」「家では本音を言わないほうが安心だ」「困ったときに相談しても迷惑をかけてしまうかもしれない」と感じやすくなります。
これは、自己肯定感や自律心、共感力といった非認知能力の土台である「安心感」を、少しずつ削ってしまう状態です。
だからこそ、親の心の余裕を取り戻し、「家は安心して失敗できる場所だよ」というメッセージを日常の中で伝え直していくことが、とても大切になります。
教育の視点から見る親の心の状態と子どもの非認知能力
非認知能力とは、自己肯定感や自律心、共感力、粘り強さなど、人生の土台となる力のことです。
これらは教室の中だけで育つものではなく、家庭での何気ないやりとりや、親の表情、声のトーンの積み重ねの中で育っていきます。
教育心理学では、親は子どもにとっての「安全基地」だと考えられています。
親が穏やかに話を聞き、感情を受け止める姿勢を持っていると、子どもは「ここに戻れば大丈夫」「話を聞いてもらえる自分なんだ」「失敗してもやり直していい」といった感覚を育んでいきます。
一方で、親が常にピリピリしていたり、自分を責め続けていると、その空気は言葉がなくても子どもに伝わります。
ここで鍵になるのが「マインドフルネス」という考え方です。今この瞬間の自分の状態に気づき、湧き上がった感情を否定せずに認めることです。
「またか」とイライラした自分に気づくだけでも、一呼吸おいた関わり方ができるようになります。親が自分の感情に気づきながら関わる姿は、子どもにとって感情との付き合い方の大切なお手本になります。
家庭でできる心の余裕をつくる4つの習慣
実践①:3分マインドフルネスで「自分の感情に気づく」
イライラが高まりそうなとき、心の中で「今、私は怒っているな」と言葉にして、ゆっくりと呼吸を整えます。
背筋を伸ばして鼻から息を吸い、口から吐く呼吸を3回繰り返すだけでも、感情と行動の間にほんの少し「間」が生まれます。その「間」が、反射的に怒鳴らずにすむ助けになります。
実践②:怒る前に「考える余地」を渡す
怒ってしまいそうなときほど、「どうしたかったの?」と問いかけてみることを意識しています。
感情に気づき、深呼吸し、責める言葉ではなく問いかけに変える。この流れを取り入れてから、子どもが本音を言葉にしてくれる場面が少しずつ増えていきました。
実践③:ながらマインドフルネスで「観察力」と「ねぎらい力」を育てる
洗い物の水の感触に意識を向けたり、信号待ちの空気を感じてみたり、寝る前に自分に「今日もよく頑張ったね」と声をかけたり。
こうした小さな習慣を積み重ねることで、子どもの小さな変化にも自然と気づけるようになります。「何かあったかな?」と声をかけるだけでも、子どもは安心します。
実践④:「完璧を手放す」家事とスマホの工夫
週に一度の手抜きデーを作ったり、掃除の範囲を決めたり、食後30分だけスマホを置いたり。こうした小さな工夫を取り入れるだけでも、家庭の空気は大きく変わります。
親が無理をやめる姿は、子どもにとって現実的な生き方のモデルにもなります。
失敗してもやり直せる親子関係を育てる関わり方
ある夏休み、散らかった息子の部屋を見て、私は感情を爆発させてしまいました。
怒鳴った翌日、「昨日は大きな声を出してごめんね。本当は一緒に考えたかった」と伝えると、息子は「どこから片付ければいいかわからなかった」と本音を話してくれました。
そこで「今日は机の上だけ」「明日は床の上だけ」と小さな目標を決め、少しずつやり直しました。
この経験を通して、親が失敗を認めてやり直す姿そのものが、子どもにとって大切な学びになること、そして一緒に考え直すプロセスが信頼関係を育てることを、私は強く実感しています。
今日からできる“小さなごきげん習慣”
イライラしたら深呼吸をする。週に一回は手抜きを許す。寝る前に自分をねぎらう。
こうした小さな習慣の積み重ねが、親子の心の距離を少しずつ近づけ、子どもの自己肯定感や自律心、共感力といった非認知能力を静かに育てていきます。
完璧な親ではなく、「ごきげんで、等身大の親」でいること。そこから、親子の毎日は確かに変わっていきます。
【執筆者:まさこ先生】
元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。
筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら
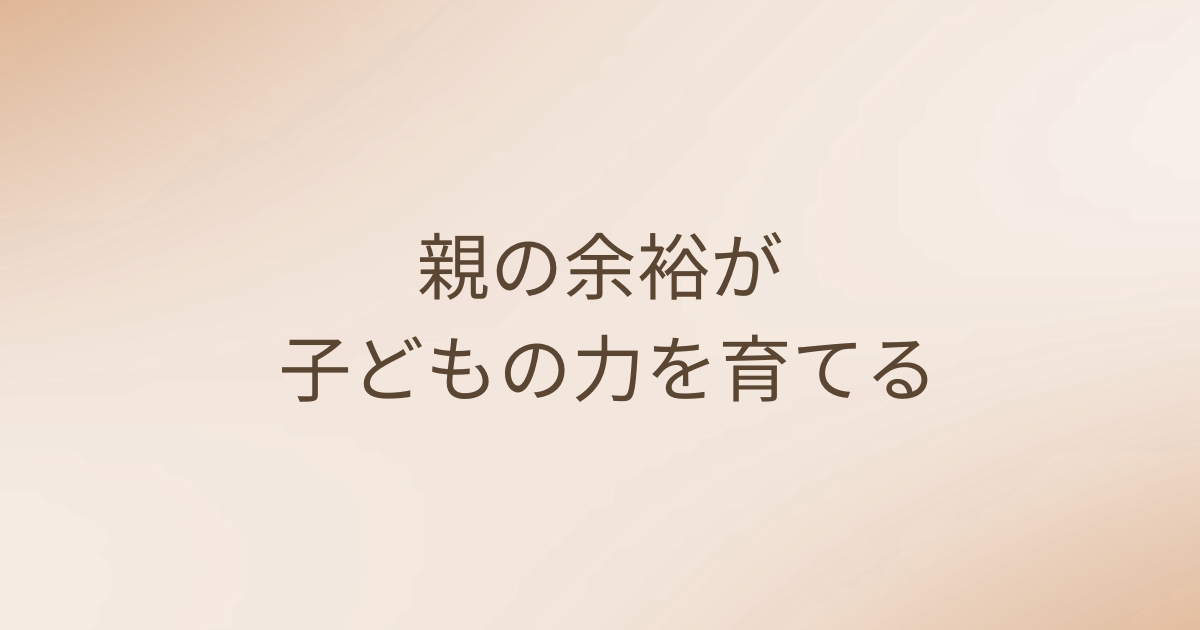
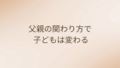
コメント