この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもと保護者に向き合ってきた経験をもとに、子どもが安心して本音を話せる親子関係を育てるための「聴き方」と「問いかけ」の考え方をまとめたものです。
親子コミュニケーションに関する記事は数多くありますが、このページでは、テクニックを並べるのではなく、なぜ子どもは話さなくなるのか、どうすれば心を閉ざさずに済むのかという全体像を整理しています。
このカテゴリ内の他の記事では、父親の関わり方、忙しい家庭での対話の工夫、感情表現の育て方など、ここで示す考え方を具体的な場面ごとに解説しています。
まずは、このページで基本となる視点を押さえてください。
会話が続かない背景と、親が整えるべき“心の余裕”
ある日の夕方、私は仕事から慌ただしく帰宅し、急いで夕食の準備をしていました。
コンロの火加減に気を配りながら、「洗濯物を取り込まなきゃ」「明日の学校の準備も…」と頭の中は予定でいっぱい。そのとき、後ろから息子が「今日ね、学校でね…」と話し始めました。
けれど私の口から出たのは「ちょっと待って。あとにして」の一言だけ。
息子はそれ以上何も言わず、自分の部屋へ静かに戻っていきました。その小さな背中を見ながら、「今、きっと話したかったんだろうな」「あの一言で気持ちの扉を閉じさせてしまったかもしれない」と胸がきゅっと痛みました。
この出来事は、「どれだけ子どもを大切に思っていても、親に余裕がないと、その思いは伝わりにくくなる」という現実を突きつけました。
現代の親は、仕事、家事、学校とのやりとりなど、たくさんの役割を担っています。心に余裕がないと、どうしても会話は「早くしなさい」「もう寝なさい」といった指示や注意に偏りがちです。
子どもは「怒られないように」と身構え、だんだんと本音を話さなくなっていきます。
親の心を整える「15分のリセット習慣」
心の余裕を一度に作ることは難しくても、「切り替える小さな時間」を持つことはできます。
あるお父さんは「家に着いて最初の15分はスマホを触らない」と決め、深呼吸をしてお茶を一口飲み、その日の出来事を静かに振り返る時間にしました。
すると、子どもから「ねえ、今日ね」と話しかけられたときに、「そうか、どんなことがあったの?」と一拍おいて返せるようになったそうです。
忙しさそのものは変わらなくても、心を整える短いバッファがあるだけで、子どもとの会話の空気は大きく変わります。
信頼を育てる“たわいない雑談”の力
教員時代、指導がうまくいかないクラスほど、子どもたちとの「雑談の時間」が少ないことに気づきました。
朝の会の前に「昨日のテレビ、誰が見た?」「今日の給食、楽しみな人?」と一分だけ話すことを続けると、表情が和らぎ、指導の言葉も届きやすくなっていきました。
家庭でも、「早くしなさい」「宿題は?」という言葉の合間に、「今日の給食はどうだった?」「帰り道で何かおもしろいことあった?」といった短い雑談を挟んでみてください。
「自分の話を聞いてもらえた」「自分の一日を気にかけてもらえた」という感覚が、子どもの心に安心の土台をつくります。
教育の視点から見える“聴き方・問いかけ”のコツ
親子の会話には、目には見えない心理的な仕組みが働いています。
教育心理学やSEL(社会性と情動の学習)の観点から見ると、子どもが安心して話せるかどうかは、親の「問いかけ方」と「聴き方」が大きな鍵を握っています。
「なぜ?」より「どうしたの?」が本音を引き出す
トラブルがあったとき、親としてはつい「どうしてそんなことをしたの?」「なぜできなかったの?」と問い詰めたくなります。
しかし、子どもにとって「なぜ?」は、責められているように感じやすい言葉です。
私が担任していたクラスにも、授業中についおしゃべりをしてしまう男の子がいました。
ある日、また友だちと話して注意したあと、「どうしていつもしゃべってしまうの?」と言いかけて、私は「さっき何を話していたの?」と聞き直しました。
すると彼は、「となりの子が休み時間の続きの話をしてて…先生の話も聞かなきゃって思ってたけど、どっちも聞きたくなって」と本音を話してくれました。
子どもが自分の行動を振り返り、次にどうしたらよいかを考えるためには、「責められている感覚」ではなく、「一緒に状況を整理してもらえている感覚」が必要です。
「どうして?」ではなく、「何があったの?」「そのときどう感じた?」と聞くことで、子どもは安心して自分の気持ちや考えを言葉にできるようになります。
聴き方が育てる“非認知能力”
近年注目されている非認知能力とは、テストの点数では測れない力の総称です。
ねばり強さ、自分の気持ちをコントロールする力、人の気持ちを想像する力、自分で考えて選ぶ力などが含まれます。
親が子どもの話をじっくり聴き、「そのとき、どんな気持ちだった?」「次はどうしてみようか」と問いかけるような会話を重ねることで、子どもは自分の感情を整理し、行動を振り返る力を養っていきます。
こうした土台は、学校生活や友だちとの関係、将来の進路選択にもつながっていきます。
家庭で実践できる“子どもが話したくなる”工夫
ここからは、忙しい共働き家庭でも今日から取り入れやすい実践アイデアをお伝えします。
どれも特別な道具は必要なく、「いつもの時間の使い方を少し変えるだけ」で始められるものばかりです。
実践1:親子インタビューごっこで「質問する力」と「自己表現」を育てる
教員時代、「うちの子は『ふつう』『べつに』しか言わないんです」と相談してきたお母さんに、私はよく「親子インタビューごっこ」を提案していました。
休日のゆったりした時間に、親と子どもが交互にインタビュアー役と答える側を交代するだけのシンプルな遊びです。
最初は「好きな食べ物は?」「子どものころ、どんな遊びが好きだった?」といった軽い質問から始めます。
親が笑顔で答える様子を見ているうちに、子どもはだんだんと表情をほころばせ、「次はぼくが聞いてみる」と自分から質問を考え始めます。たとえば、次のような質問です。
- 「お母さんの仕事でいちばん大変なことは何?」
- 「お父さんは小学生のころ、どんなことで怒られた?」
- 「友だちとけんかしたとき、どうやって仲直りした?」
この遊びを続けることで、子どもは相手の気持ちに関心を向けながら質問する力、自分の考えや経験を言葉にする力を自然と身につけていきます。
また、親が自分の失敗談や子ども時代の気持ちを話すことで、親子の心の距離がぐっと近づきます。
実践2:「3分だけ聞く時間」を生活の中に決める
「ゆっくり話を聞きたいけれど、毎日は時間が取れない」という声もよく聞きます。
その場合は、あえて長い時間を目指すのではなく、「3分だけの特別な時間」を生活の中に決めてしまうのがおすすめです。
たとえば、寝る前の布団の中、夕食後の食卓、車や自転車での移動時間など、「ここだけは子どもの話を遮らずに聞く」と決めてしまいます。
その3分だけは、親は自分の意見やアドバイスをいったん脇に置き、「へえ、そうだったんだね」「それでどうなったの?」と相づちを打ちながら聴くことに集中します。
短い時間でも、「この時間だけは自分の話を受け止めてもらえる」と子どもが感じられるようになると、次第に自分から話題を持ってくるようになります。
うまくいかない日こそ“やり直せる関係”を育てるチャンス
ここまで、聴き方や問いかけ方の工夫についてお話ししてきましたが、私自身も常にうまくできてきたわけではありません。
ときには感情的になって叱りすぎてしまい、「あんな言い方をしなければよかった」と後悔したことも何度もあります。
きょうだいげんかを“成長の教材”として捉え直す
わが家では、二歳違いの兄と妹のけんかがよく起こっていました。ある日、兄が読んでいた本を妹が急に取り上げ、兄は「まだ読んでいたのに!」と大きな声を出しました。
思わず「もう、二人ともいい加減にしなさい」と言いかけましたが、一度深呼吸をして、まず兄を別の場所に連れていきました。
「びっくりしたね。どうしてそんなに怒ったの?」と聞くと、「やっと読める時間だったのに取られて悲しかった」と涙ながらに話してくれました。
次に妹に「どうして本を取りたくなったの?」と聞くと、「おにいちゃんばっかり読んでて、わたしも一緒に見たかった」と小さな声で教えてくれました。
落ち着いてから二人を向かい合わせ、「お兄ちゃんはこう感じていたんだね。妹はこうしたかったんだね」と気持ちを言葉にして伝えると、兄が「じゃあ、ここから一緒に読む?」と提案してきました。
この経験から、きょうだいげんかは「気持ちを言葉にして伝え合う練習の場」にもなるのだと感じました。
失敗したあとの“ひと言”が信頼を深める
私が保護者の方々にいつもお伝えしているのは、「完璧な親であろうとしなくて大丈夫です」ということです。大切なのは、うまくいかなかったあとにどう関わり直すかです。
感情的に叱ってしまったとき、「さっきは怒りすぎたね。びっくりさせてごめんね」とひと言伝えるだけで、子どもは「自分の気持ちをわかろうとしてくれている」と感じます。
親が自分の非を認める姿は、子どもにとって「失敗してもやり直せる」「大人でも間違えることがある」という大きなメッセージになります。
これは、子どもの自己肯定感や、挑戦する勇気につながっていきます。
結論:今日からできる一歩で、親子の会話は変わっていく
親子の会話を変えるのに、特別な知識や長い時間は要りません。「これなら今日からできそう」という一歩を選んで続けることが大切です。
- 帰宅後の15分だけ、スマホを置いて心を整えてみる
- 「どうして?」を「何があったの?」「どう感じたの?」に言い換えてみる
- 寝る前の3分だけ、子どもの話を遮らずに聴く時間をつくる
- うまくいかなかった日は、「さっきは言いすぎたね」と正直に伝えてみる
どれか一つでも、心に残ったことから試してみてください。親の関わり方が少し変わるだけで、子どもの表情や言葉は驚くほど変わっていきます。
今日の夜、いつもの「おやすみ」に「話してくれてありがとう」とひと言添えてみる。その小さな一歩が、親子の新しい対話の扉を開くきっかけになります。
- 表現する力を高める方法についてまとめています。
→ 家庭で育てる“感情表現力”と寄り添い方 - 忙しい親が子どもとかかわるポイントについてまとめています。
→ 忙しくてもできる高密度対話の習慣 - 父親の関わり方についてまとめています。
→ パパ育児3つのポイント - 親の心の余裕を生み出す方法についてまとめています。
→ 親の心の余裕
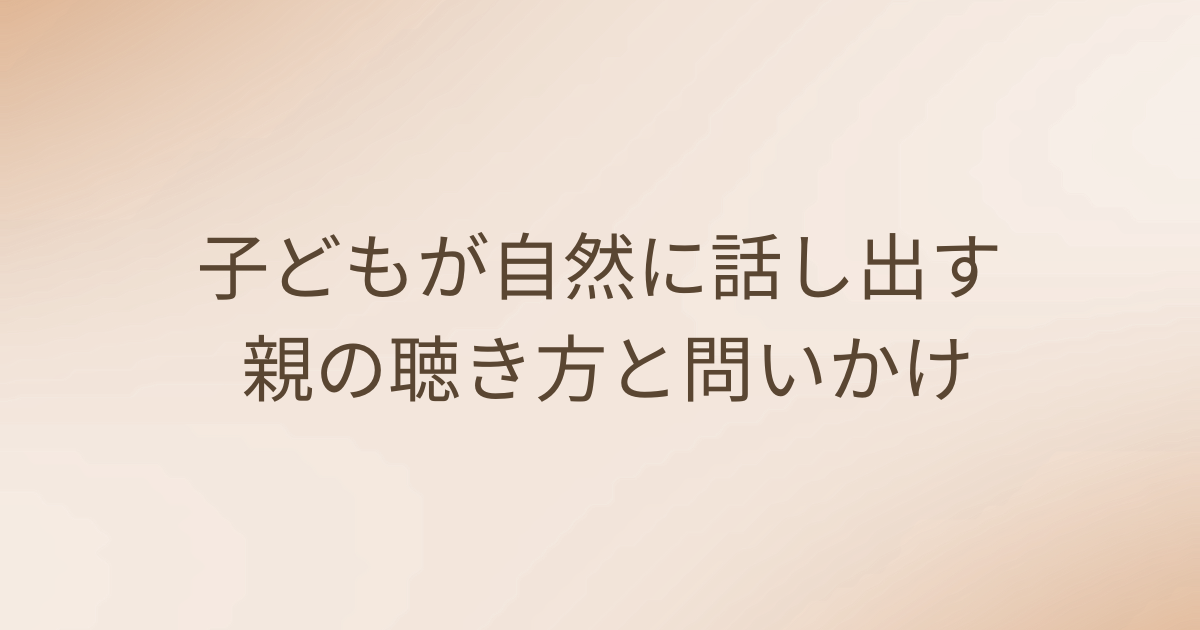
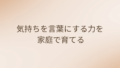
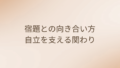
コメント