この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもの成長を見てきた経験から、家庭で実践できる、昔遊びとなぜ今の子どもたちに必要なのかを、教育的な視点でお伝えします。
連日の強い日差しや突然の大雨で外遊びが減る夏休み。子どもがついスマホやゲームに手を伸ばし、「集中力が続かない」「イライラしている」と心配していませんか。
こうした悩みに、今改めて注目されているのが”昔ながらの遊び”です。
けん玉やお手玉、あやとりや折り紙といった懐かしい遊びは、集中力や工夫する力、忍耐力といった子どもの成長に欠かせない力を育てます。
デジタル機器が身近な現代だからこそ、手を使い、考え、試行錯誤する体験は貴重です。また、親子や祖父母との会話を通して、世代を超えたつながりを深めるきっかけにもなります。
この記事で紹介する内容は、「家庭での学びと体験」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。
→子ども主体のおうち夏祭り|自己肯定感につながる家庭イベントの工夫
なぜ今「昔遊び」なのか? デジタル時代に失われゆく5つの重要能力と元教員の事例
今や小学生の約7割が日常的にタブレットやYouTubeを使う時代。
「分からない→検索」の習慣が定着し、答えが一瞬で表示される反面、忍耐力や創意工夫する時間が減ることに危機感を持つ教育現場の声が増えています。
昔遊びは、答えがすぐには出ません。だからこそ、自分をコントロールする力や粘り強さが自然と身に付きます。
しかも手を使う遊びは、考える力の土台を作ります。脳科学の視点から見ても、とても理にかなった活動です。
教員時代、答えが”すぐに分からない”けん玉やあやとりなどの昔遊びに夢中になることで、失敗・挑戦・自己修正を繰り返しながら、子どもたちに「自分の頭と体で解決する力」が自然と育っていったのを何度も目の当たりにしました。
今こそ、家庭の”遊び”を見直す好機です。
私が子供たちと実践してきた中で、昔遊びが特に伸ばすのは次の5つの非認知力です。
1. 集中力
けん玉の一発成功を目指す過程で、目の前の動作に全神経を注ぐ習慣が身につきます。「今この瞬間に意識を向ける」練習は、リラックス脳波(α波)との相関が教育分野の研究で示されています。
2. 工夫・創造力
お手玉や折り紙で失敗→試行錯誤を繰り返し、「なぜうまくいかないか」「どうしたらもっとよくなるか」を自分で考え抜く力が育ちます。「正解がない世界」で生きていくための思考の柔軟性を養います。
3. 忍耐力と達成感
竹馬やコマは最初からうまくいかないもの。くじけず挑戦し、実現した瞬間に得られる達成感・自己肯定感は、教室では与えられません。この「やり遂げる力(Grit)」が学習意欲の土台となります。
4. 指先の器用さと身体感覚
切る、折る、巻く、回す…手や指を細かく動かす経験が、語彙獲得や論理思考の基礎に有益という最新の発達心理学報告もあります。指先は「第2の脳」と呼ばれるほど、知的好奇心と深く関連しています。
5. 社会性
みんなでルールを決めて遊ぶ過程で”負けてもやり直す心”や”相手の成功を認めること”が自然に学べます。これは「共感性」や「協調性」といった、集団生活で最も求められる能力の基礎となります。
猛暑・雨の日でも大丈夫!集中力と指先の器用さを鍛える昔遊び4選
猛暑・ゲリラ豪雨、あるいは在宅勤務中の昼休みでも、家の中で日常的に親子で取り組めるアレンジ昔遊びをピックアップ。
それぞれ「準備ゼロ」「代用品OK」「会話の糸口」として使える実践例をご紹介します。
指先の緻密さと空間認識を磨く:「あやとり」で鍛えるプログラミング的思考
あやとりは、使い古しの毛糸や荷造り紐が1本あれば、思い立ったその瞬間から始められる遊びです。
材料を一緒に探すところから「この紐どうする?」「これくらいの長さでいいかな?」と、準備段階からすでに親子の会話が生まれます。
さらに、あやとりをしながら、どの糸を引くかなどの会話を交えながら進めると、子どもは「次はこうしてみたい」「違う形にしてみたい」と、自ら考えて行動する意欲を持ちます。
最初は「ほうき」や「糸車」など基本の形から始めましょう。少しずつ難易度を上げ、達成感を積むことで、自己効力感が高まり、他の学習や活動にも良い影響を与えます。
特に、親が「正しいやり方」を教えるだけでなく、「どうしたらできるかな?」と問いかけることで、子どもが自分で手順を組み立てる思考力も育ちます。
あやとりは、手順を覚えて正確に繰り返す力を鍛えます。糸の動きを頭の中でイメージする練習は、算数の図形問題や理科の立体を考えるときにも役立ちます。
また、段階を追って操作を覚えることは、物事を順序立てて考える力の基礎になります。
リズム感と脳の協調性を高める:「お手玉」で鍛える左右脳連動と代替材料のアイデア
お手玉は、昔ながらの遊びの中でも、親子で一緒に”作る・遊ぶ・挑戦する”という3段階の楽しみを味わえる貴重な遊びです。
身体面だけでなく、記録する・比べる・分析するという”思考の運動”に発展させられる面白さがあります。
現職時代に体育の一環としてお手玉を取り入れたところ、運動が得意でない子が、「数えるのが楽しい」「昨日より上手くなった」と喜んで取り組むようになりました。
「昨日は7回成功だったね。今日は10回挑戦!どこが難しかった?」と問いかけ、答えが返ってきたら「じゃあ、次はどうしたらうまくいくかな?」と促します。
親は答えを教えるのではなく、「どうしたらいいと思う?」と問いかけ、子ども自身が課題を言語化し、解決策を考える習慣を育てましょう。
お手玉遊びは単純に見えますが、実は多面的な発達を促します。両手を別々に動かす練習は脳の左右をつなぐ部分を活発にし、運動能力だけでなく学習能力も高めます。
リズムよく投げて受け取る動作は手と目の協応を鍛え、集中力やワーキングメモリを高めるとともに、音楽やダンスの基礎となる体の使い方も自然と身につきます。
加えて、落としたときに「もう一度やってみよう!」と繰り返す過程で失敗から立ち直る力(レジリエンス)が育まれ、小さな目標を達成する経験が子どもの自己効力感を高めます。
お手玉は家にある材料で簡単に始められることも魅力のひとつ。
使わなくなった靴下を切って袋状にし、中に乾燥豆やペットボトルキャップを入れれば、即席のお手玉が完成します。
裁縫が得意なら布を選んで手作りしてもよいですし、工作感覚で子どもと一緒にデザインしても構いません。
「どんな柄にしようか?」「軽いのと重いの、どっちが投げやすい?」など、制作の段階から親子の対話が生まれます。
算数と創造性の土台:親子で試行錯誤する「折り紙」の問いかけ
折り紙は、1枚の紙から無限の形を生み出せる”思考の遊び”であり、家庭でもっとも身近なSTEAM(科学・技術・工学・芸術・数学)教育の入り口です。
紙を折るというシンプルな動作の中に、図形感覚・空間認知・集中力・計画性といった学習の基礎が自然に詰まっています。
特別な教材を用意しなくても、1枚の折り紙さえあれば、どの家庭でもすぐに始められるのが魅力です。
教員として多くの子どもたちを見てきた中で、折り紙が得意な子ほど図形の授業に強く、空間イメージの形成が早い傾向がありました。
折り紙を通して”折り目=対称線”や”角度の感覚”を手で体験しているため、教科書の図形を見たときに「この部分は半分だ」「ここを折ると同じ形になる」と、頭の中で立体的に考えられるのです。
わが家でも、子どもたちが幼児期から折り紙に親しんできました。特に印象的だったのは、「よく飛ぶ紙飛行機」の折り方を探究したときのことです。
最初は単に「遠くまで飛ばしたい」という気持ちでしたが、何度も試していくうちに「翼の幅を広げたら安定する」「角をきっちり折ったら真っすぐ飛んだ」と、自然と”実験→結果→考察”のプロセスを踏むようになっていきました。
「どの形が一番飛びそう?」と問いかけ、娘の答えに対して、「じゃあ角度を変えて折ってみよう。どっちが飛ぶかな?」とやり取りを重ねることで、折り紙が”親子の研究テーマ”に。
成功や失敗を共有しながら、「なぜうまくいったのか」「次は何を変えるか」を一緒に考える過程に、まさに学びの核心があるのです。
折り紙では、対称や角度、半分や4分の1といった算数の考え方を、実際に手を動かしながら学べます。
完成形を想像して、どう折ればいいか考える過程は、プログラミングで使う「逆から考える力」にもつながります。
また、子ども自身のアイデアを尊重することで、創造性と問題解決能力が同時に育まれます。
近年の教育現場では、折り紙が数学や図形教育の教材として再評価されています。
文部科学省の学習指導要領でも「図形の性質を操作的に理解する学習活動」が推奨されており、折り紙はその代表例とされています。
聴覚記憶と「笑い」の共有:「かるた・福笑い」で失敗を恐れない心を育む
かるたと福笑いは、昔ながらの遊びの中でも”言葉と笑い”を通して心を育てる二大名作です。どちらも道具がシンプルで、家族みんなが世代を超えて楽しめるのが特徴です。
かるたは「聴覚で情報を捉え、視覚で探し、手で反応する」という3つの動作を一瞬で行う、耳・目・手・脳を同時に使う”全身の知育運動”。読み札の最初の1音に集中し、瞬時に反応する練習を積むことで、聴覚処理速度や集中力が飛躍的に向上します。
かるたは、言葉の音を聞き分ける力を高め、読む力の土台を作ります。耳で聞いた情報をすばやく処理して動く活動は、記憶力を鍛えるのに効果的です。
また、ことわざかるた・都道府県かるた・英単語かるたなどを使えば、楽しみながら知識を増やすことができ、遊びながら家庭内の話題や思い出が交わされるのが魅力です。
勝ち負けを経験することで「悔しさを乗り越える力」「次こそがんばる意欲」も育ちます。
「福笑い」は目を隠して行うので、子どもは「鼻は真ん中かな?」「口は少し下?」と頭の中で位置をイメージすることに。
わが家では祖父母が作った”手作り福笑い”を3世代で遊びました。祖父の顔のパーツを紙に描いて切り取り、孫たちが目隠しで並べると、とんでもない顔になって大笑い。
その笑いの中に、「失敗も面白い」「うまくいかなくても大丈夫」という肯定感が自然に育まれていました。
福笑いは、失敗しても笑って楽しめる経験を通じて、失敗を恐れない心と立ち直る力を育てます。こうした「遊びの中の失敗」が、子どもの心を強くし、挑戦する勇気を養うのです。
屋外遊びの価値と、室内で体を動かすための「手作り工夫」戦略
屋外で体を動かす昔遊びが持つ価値も見逃せません。
ただし、猛暑期には無理に屋外で遊ばせないこと、時間帯を朝夕に限定すること、水分補給の徹底を呼びかけることが大切です。
全身のバランスと再挑戦の心:「竹馬」が教える困難克服のプロセス
竹馬は見た目以上に、子どもの「全身バランス感覚」「挑戦する心」「失敗しても立ち上がる力」を同時に育てる奥深い遊びです。
最初の一歩がなかなか踏み出せない子も、親が「できるまで見守るよ」と声をかけるだけで、何度も挑戦を繰り返します。
転んで泣きそうになった時、「転んでも大丈夫」「もう一回やってみよう」と寄り添う言葉が、子どもの自己効力感を高める重要な支えになります。
教員時代、学校のイベントで竹馬に挑戦する子どもたちを見ていると、最初はわずか数歩で転んでいた子が1週間後には校庭を1周できるようになるなど、目に見える成長がありました。
うまくいかない瞬間に「ここを少し高く持ってみよう」「足の位置をずらしてみよう」と声掛けすることで、失敗を恐れずに前向きに取り組む姿勢が育まれます。
心理学では、こうした体験を通して「レジリエンス(逆境から立ち直る力)」が養われると言われています。体のいろいろな部分を連携させて動かす力は、スポーツや日常動作の土台になります。
できないことに挑戦し続け、できるようになる過程そのものが、子どもの自己肯定感と粘り強さを培う貴重な学びなのです。
まずは室内や庭で安全に挑戦してみませんか?転んでも励まし合いながら少しずつ進めると、子どもの「できた!」の瞬間を一緒に味わえます。
手先の協調運動と根気:「こま回し」が教える試行錯誤のプロセス
コマ回しは、昔遊びの中でも特に「集中力」「手先の巧緻性」「観察力」「粘り強さ」を同時に育てられる万能な遊びです。
単に回すだけでなく、どうすれば長く回るか、どんな形や素材がよく回るかを親子で探究することで、自然と理科的な思考や探究心が育ちます。
私が教員として関わったクラスでも、最初は糸をうまく巻けず、何度も失敗していた子が、数日後には「どうやったら10秒回せるか」を自分で考え始めるようになりました。
試行錯誤を繰り返すうちに、「強く引くとバランスが崩れる」「コマの先を少し尖らせると安定する」など、自らの経験を言語化し、他の子に教えるまでに成長しました。
こうした過程が、まさに「思考力」「表現力」「学びに向かう力」を総合的に育てます。”仮説→実験→検証”の流れを親子で楽しむと、自然に理科的思考が身につきます。
こま回しは手首の微妙な動きを鍛え、根気強さを育てます。手先の細かな動作は、脳の運動を司る部分を刺激し、書字や楽器演奏などの技能習得にも良い影響を与えます。
また、すぐには成功しない遊びを繰り返すことで、目標に向かって努力する力が自然と身に付きます。試行錯誤を楽しむ姿勢こそが、学習全般に通じる大切な力なのです。
力加減と戦略的思考:「メンコ・紙相撲」で学ぶ物理感覚と社会性
めんこは、昔から子どもたちの手で作り、遊びながら工夫する遊びの代表格です。小さな厚紙や紙、プラスチック板など身近な材料で作れるため、昔は家庭で自分だけのめんこを作って遊ぶのが一般的でした。
「投げてひっくり返す」という単純なルールの中にも、子どもたちの創意工夫と学びの要素が詰まっています。
私が教員時代に見たクラスでは、最初は「ただ投げて遊ぶ」だけだった子どもたちが、やがて「どうやったら長くひっくり返せるか」「めんこの形や重さを変えたらどうなるか」と考えるようになりました。
この過程で、手先の器用さや集中力、空間認識力が自然に養われるのです。
どうやったらうまくいくか親子で考えるやりとりは、単なる遊びのサポートではなく、「考えるプロセス」に寄り添う教育的な時間になります。
失敗しても一緒に考え直すことで、挑戦する心と忍耐力が育まれます。
メンコや紙相撲は、力加減や戦略を考える遊びです。物理的な力加減を体で覚える経験は、力の強弱や空気の流れといった理科的な感覚を養います。
また、友だちとルールを確認したり、勝ち負けを受け入れたりする中で、社会性やスポーツマンシップの基礎が形成されます。
遊びを通じた対人関係の学びは、教室での学びとは違う貴重な成長の機会なのです。
遊びを最大限に進化させる現代的アレンジ術と工夫集
工作やデジタル、家庭や遠方の家族との交流など、現代の環境に合わせた工夫を加えることで、昔遊びは「新しい昔遊び」として楽しむことができます。
ここでは、遊びを進化させるための具体的なヒントと応用例をご紹介します。
工作が学びの入口に!「身近な素材」で自作する遊びと問題解決力
昔遊びは「与えられた遊び」ではなく、本来「自分たちで作り出す遊び」。
竹馬もコマもお手玉も、かつては家庭の中で身近な材料を使い、子どもたち自身が工夫して作っていました。その原点に立ち返る体験こそ、現代の子どもたちに最も必要な”創造する力”を育てる機会になります。
新聞紙や段ボールは、その入り口にぴったりの素材です。特別な道具がなくても、折る・丸める・つなげる・重ねるなど、シンプルな動作の中に「構造」「力のバランス」「形の安定」などの理科的な学びが詰まっています。
完成したもので遊ぶより、作る過程そのものが学びの宝庫です。失敗しても「次はどうしたらうまくいく?」と考えることで、自己解決力や粘り強さが養われます。
コマの場合、ペットボトルキャップ・段ボール・牛乳パックなど身近な素材で自作可能。軸には割り箸やストローを使い、中心の位置を少しずらすと、回転の動きが変化することも体験できます。
また、色塗りや模様付けを工夫すれば、回転した時に現れる模様の変化を観察でき、アートと科学の融合体験にもなります。
めんこを作る際も、厚紙や段ボールに好きな絵を描いたり、色を塗ったり、テープで補強するだけで十分です。
小さくても重さや形を少し変えるだけで、跳ね方やひっくり返り方が変わることに子どもはすぐ気づきます。
作る過程から遊びまでを一貫して体験することで、「計画→実行→振り返り」という問題解決の基本サイクルが身に付きます。
また、材料を工夫して作る経験は、創造性や資源を有効活用する意識を育てます。親子で協力しながら工作してから遊ぶことで、会話が増え、共同作業を通じた学びも深まるのです。
小学4年生の息子が「お手玉を作りたい」と言い出したので、家にあった布を広げて、一緒に選ぶことに。
息子は不器用ながらも一針ずつ縫い進め、小豆を入れて袋を閉じ、完成。翌週、今度は「ビーズも試したい」と言うので、もう一つ作り、二つを比べながら「小豆のほうが投げやすい」と自分なりの発見も。
その後はペットボトルのキャップで簡易けん玉を作り、色を塗って楽しんでいました。
素材を選ぶところから子どもに関わらせることで、感覚や判断力が育ちます。
裁断や縫い合わせの作業を通じて、手先の器用さだけでなく計画力ややり遂げる力も身につきます。
試行錯誤しながら工夫する過程が創造力と観察力を育て、完成したものを使って遊ぶことで、学びと遊びが自然に結びつくのです。
遊びに記録と分析を!「デジタル機器」を活用した挑戦と振り返り
デジタルは昔遊びの強力な味方になります。技の細かい動きを何度も確認できる動画、手順を視覚的に示すアプリなどを上達への近道として、賢く活用しましょう。
夕食後、小学5年生の娘が何度やってもけん玉の玉が皿に乗らず、苦戦していました。
娘はタブレットで技の解説動画を見つけ、膝の使い方やタイミングを確認。動画を一時停止して手の位置を、巻き戻して姿勢を真似するを繰り返し、10分後、ついに玉が皿に乗りました。
動画やアプリは、視覚的に理解しやすく上達への近道になります。ただし、視聴だけで終わらせず、必ず実践することが重要です。
デジタルを「学びの補助線」として使い、実際に手を動かす体験と組み合わせることで、理解が深まり技能が定着します。
現代の子どもたちにとって、デジタルと実体験を統合する力こそが大切なのです。
成功動画を撮影してフォームを改良したり、スローモーション動画で回転フォームや技の動きを分析したりすることもできます。
また、お手玉や竹馬、こま回しの成功回数を数字で記録し、今日と昨日を比べることで、遊んだ記録をグラフ化して進歩を確認できます。
記録ノートで自己評価と改善のサイクルを楽しむこともできます。
世代の壁を越える会話術と交流の実践
「祖父母の知恵」を引き出すコミュニケーション
距離は問題ではなくなりました。ビデオ通話があれば、遠方の祖父母とも一緒に遊べます。画面越しに教え合う体験は、単なる遊びを超えて、世代をつなぐ貴重な時間です。
日曜日の午後、小学3年生の息子が折り紙を遠方に住む義母に見せたいと言うので、ビデオ通話をつなぎました。
手裏剣を見せ、作り方を説明します。普段教わる立場が一転、教える側に。得意げな表情が画面に映ります。
義母も「むずかしいわね」と言いながら、楽しそうに折り進め、30分後、二人で完成した手裏剣を見せ合い、声を上げて喜んでいました。
子どもが教える経験は、理解を深め、自己肯定感を高めます。また、祖父母から教わることで、世代を超えた知恵や文化が継承されます。
教え合う関係性が、双方向の学びと心のつながりを生み、家族の絆を深める貴重な機会となるのです。
地域とつながる!「昔遊びの継承者」になるための交流実践とヒント
地域や学校のイベントでは、異なる年齢の子どもたちが集まり、教え合い、競い合います。家庭だけでは得られない学びがあります。
夏休みの終わり、地域の公民館で「昔遊び体験会」が開催され、小学6年生の息子と一緒に参加することにしました。
息子は小学1年生の子にけん玉を教えていました。年下の子に教える経験を通じて、自信をつけている様子でした。
一方で、地域のおじいさんからこま回しの技を教わり、「すごい!」と目を輝かせ、帰り道で「また行きたい」と言っていました。
地域での昔遊びイベントは、年齢の違う仲間と遊び、ルールを調整する貴重な経験の場です。年下の子への思いやりや年上への憧れが育ち、教え合いや助け合いの心が自然に生まれます。
また、地域の大人との交流は、学校や家庭以外の「第三の居場所」として、子どもの社会性を広げる大切な機会となるのです。
まとめ:「続かない」を解決する!昔遊び成功のための親の関わり方と3ステップ
“昔遊び”は、単なる懐かしさやノスタルジーではなく、非認知能力・親子関係・実体験の三方向から子どもの学びと心を支える最強の教材です。
デジタル化が進む現在だからこそ、家庭で「自分の手と体」「親子・家族で協力」の価値が一層高く評価されています。
家庭での実践としては、まず短い時間でルーチン化すること、親が見守り褒めること、失敗を受け止めることを心がけましょう。
祖父母や地域とつなげる工夫として、ビデオ通話や一緒に作るワークショップなども効果的です。
最後に一つの提案です。今日からできる最初のステップとして、一日10分だけ、昔遊びの時間を作ってみてください。
その小さな一歩が、子どもの大きな成長につながっていきます。
【執筆者:まさこ先生】
元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。
→筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら
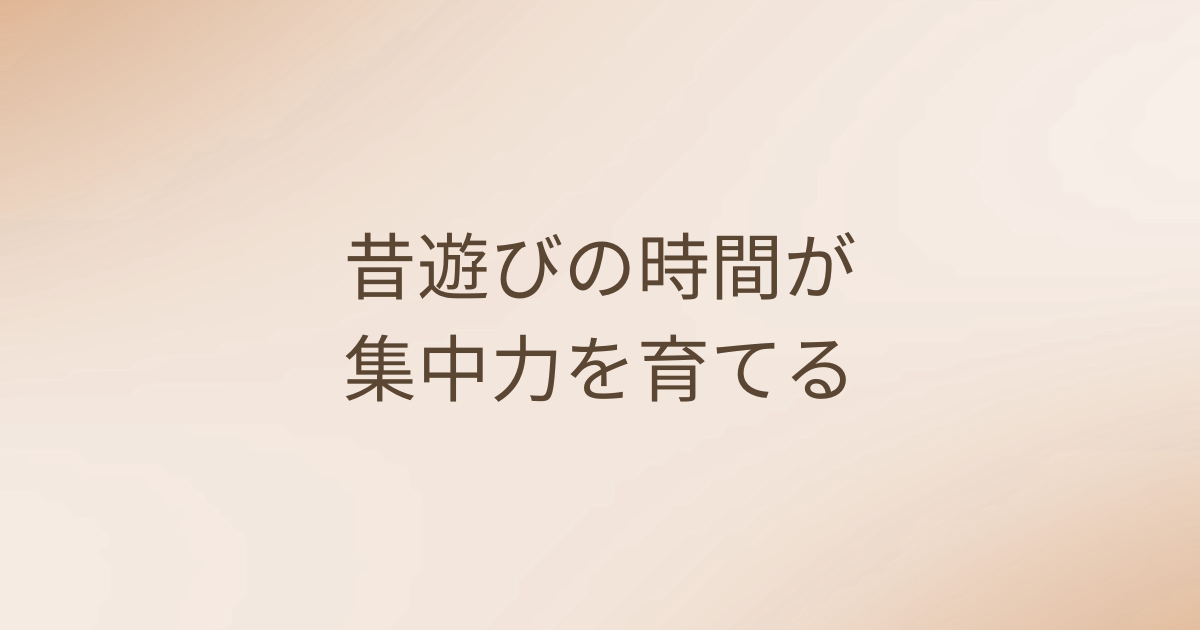
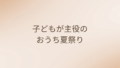
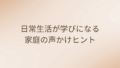
コメント