この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもの成長を見てきた経験から、家庭で実践できるキャリア教育のうち、親の仕事をわかりやすく伝える方法について解説します。
「お父さんの授業って楽しそう」「お母さんはなぜ夜遅くまで教材を作っているの?」——教員である私たち夫婦のもとで育つ子どもたちも、こうした疑問を投げかけてきました。
大切にしていたのは、年齢に合わせて話すこと、職業への誇りを伝えること。そうすることで、子どもたちは「働く」ことを前向きにとらえられたと感じています。
この記事で紹介する内容は、「家庭での学びと体験」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。
→子ども主体のおうち夏祭り|自己肯定感につながる家庭イベントの工夫
親の仕事を伝えることがキャリア教育になる理由
毎日の家庭での会話や親の働く姿勢は、子どもの職業観を形成する土台となり、子どもの未来への扉を開くきっかけになります。
親の仕事が子どもの職業観と価値観に与える影響
子どもたちが将来について考えるとき、最も身近で影響力のあるロールモデルは親です。親の仕事への向き合い方は、子どもの職業観や価値観の原点になります。
学校でも、親が仕事にやりがいを感じている子どもは、積極的に自分の将来について考える傾向があります。
親が仕事で困難に直面したとき、どのように取り組むのか、チームワークをどう大切にするのか——そうした姿勢を子どもは日々観察しています。
こうした日常に根ざした働き方の示し方は、学校のキャリア教育ではなかなか学べません。
学校では学べない!親の口から説明することが大切な理由
他人から聞く抽象的な理屈よりも、親の実感に満ちたひとことの方が子どもの心に残ります。
たとえば、「おかあさん、今日はどうだった?」という子どもの問いかけに対し、「今日は授業で子どもたちがとてもいい質問をしてくれて、私も勉強になったよ」と、喜びや学びを情緒を込めて話すこと。
この会話は単なる情報伝達を超えて、親子の信頼と子どもの情緒の安定につながり、人生の価値観や生き方そのものを伝える機会となるのです。
心理学では、親が仕事の話を情緒を込めて話すことで、子どもは「親への信頼」と「情緒の安定」を得るとされています。親の生き方そのものを通して、人生の価値観や共感性を学ぶことができるのです。
【年齢別】子どもに伝わる仕事の説明と分かりやすい工夫
親の仕事について子どもに話すとき、年齢に応じた伝え方を工夫することで、より深く理解してもらうことができます。
また、子どもが抱く疑問に対して準備しておいた答えがあると、自然で温かい対話が生まれます。
ここでは、発達段階別の説明方法と、日常でそのまま使える実用的なフレーズをご紹介します。
発達段階別!子どもが「働く」を深く理解する年齢別の伝え方
幼児〜小学校低学年向け(5〜8歳):体験と感情に結びつける言葉
この年齢の子どもは抽象的な言葉を理解できません。自分が体験したことや、「人を助ける=良いこと」という単純な価値観で仕事をとらえます。
例えば、「痛い人を助ける」「お腹がいっぱいになる」という説明なら、子ども自身の経験と結びつけて理解できます。私は教員として、「『勉強がわかってうれしい』って子どもが喜ぶようにする仕事だよ」と、喜びと感情に結びつけて伝えていました。
この時期の子どもは「具体的思考」が中心です。抽象的な職種名より、「誰かが笑顔になった」「困っていた人を助けた」といった具体的な行為と感情に結びつけることが重要となります。
以下は具体的なフレーズ例です。
- 「この仕事は人を助ける仕事だよ」
- 「今日は誰かが笑ってくれたよ」
- 「お父さん(お母さん)の仕事で、みんなが困らないようにしているんだ」
小学校中学年向け(9〜10歳):チームワークと問題解決のプロセスを伝える
9〜10歳になると、人同士の協力やチームワークの意味がわかり始めます。「看護師は医師と協力して」という説明が響くようになるのです。
私は教員として、「用務員さんや事務員さんと協力して学校をよくしてるんだ」と伝え、仕事がチームで成り立っていることを示していました。
また、この年齢は「なぜ」「どうして」という疑問をよく持つようになります。仕事の面白さや何かを創り出すことを理解できる年齢なので、「問題を解決する」「工夫をした」という仕事のプロセスを説明すると、子どもは興味を覚えます。
中学年は「集団行動」や「社会のルール」を理解し始める時期です。仕事が一人ではなく「チームの協力」で成り立っていること、そして「問題解決」のプロセスを伝えることで、社会性を育めます。
以下は具体的なフレーズ例です。
- 「問題を見つけて解決するのが仕事の一つだよ」
- 「今日はこんな工夫をしたよ」
- 「お客さんに喜んでもらうために、こんなことを考えたんだ」
小学校高学年以上向け(11歳〜):社会の仕組みと求められる力を語る
11歳以上になると、社会全体の仕組みや自分の将来について考え始めます。
個人的な関係だけでなく、社会の中での役割を理解できるようになるので、「世の中の課題を解く」「地域を支える」という広い視野での説明が適しています。
この時期は「自分には何ができるのか」「どんな力が必要なのか」に関心を持つようになるため、「求められる力」や「責任の大切さ」について語ることで、将来の職業選択を考えるきっかけを与えることができます。
たとえば、「先生になってよかったと思う?」という問いには、「子どもたちがどんな仕事に就いても必要な力を育てることに関われることが、とても誇らしいんだ」と、仕事の社会的意義を伝えることが大切です。
高学年は抽象的思考が発達し、社会全体の仕組みに関心を持ち始める時期です。
仕事の「社会的役割」や、そのために必要な「スキル」「責任」を具体的に伝え、自己のキャリアプランを考えるきっかけを与えましょう。
以下は具体的なフレーズ例です。
- 「この仕事で求められる力はこういうことだよ」
- 「仕事を通じて社会を支えるんだよ」
- 「今日の経験から、責任を持つことの大切さを学んだよ」
日常で使える!子どもの素朴な質問への「短い」答え方フレーズ集
子どもは思ったことを率直に聞いてきます。大人のように遠慮せず、「なんで働くの?」「疲れない?」といった素朴な疑問をそのまま口にします。
このような質問には、短く本質を伝える方が効果的です。
子どもの集中力は短いため、複雑な説明では途中で興味を失ってしまいます。大切なのは、仕事の意味や価値観を一言で表現することです。
たとえば、このように答えてみてください。
- 「なんで働くの」→「みんなが安心して暮らせるようにするためだよ」
- 「お母さんは何が楽しいの」→「人ができるようになるのを見てうれしいんだよ」
- 「大変じゃないの」→「大変だけどその分喜びもあるよ」
職業への誇りを伝えるのに最適な場面とタイミング
職業への誇りを伝える最も効果的なタイミングは、実は日常の何気ない瞬間です。
改まって「仕事について話そう」と座って説明されるよりも、自然な流れの中で聞く話の方が心に響きます。
例えば、帰宅時に「ただいま。今日はよい一日だったよ」と明るく報告したり、配偶者が「体育で転んだ子のけがを処置したら、『ありがとう』っていわれたよ!」と、感謝されたエピソードを報告する時など、感情が高まっているときです。
報告するときの親の表情や声色は、子どもに強い印象を与えます。嬉しそうに話す親の姿を見ることで、子どもは「人に感謝される仕事っていいな」と感じ取るのです。
感情ややりがいを言葉にする工夫
子どもは大人の感情に敏感です。仕事について話すとき、「うれしかった」「悩んだけど解決した」など感情を交えて話すと、子どもは自然に共感し、自分のことのように受け止めます。また、仕事には困難もあるが、それを乗り越える喜びもあることが分かります。
「最初は困ったけど、〇〇先生に教えてもらって解決できた。安心したよ」など、結果だけを報告するのではなく、そこに至るまでの気持ちの変化を含めて話すことで、働くことの本当の魅力が子どもに伝わるのです。
たとえば、感情を込めた表現として次のようなものがあります。
- 「今日もみんなのためにがんばったよ」
- 「大変だったけど、役に立てたのがうれしい」
失敗談や苦労も働く意味として伝えよう
仕事には成功だけでなく、失敗や困難もつきもの。
親が完璧な姿だけを見せるのではなく、失敗から学び、再び立ち上がる姿を子どもに見せることで、働くことの本当の意味を伝えることができます。
完璧な親はNG!不完全な姿が子どもの挑戦意欲を育む理由
親が不完全な姿を見せることは、子どもの健全な成長にとって重要です。完璧主義は子どもにプレッシャーを与え、挑戦を恐れる姿勢を生み出してしまいます。
親が「今日も失敗したけど、明日は気をつけよう」と話すことで、子どもは「完璧でなくても頑張ればいい」という安心感を得られます。
わが家では「おとうさんは実験で失敗したりしないの?」という子どもの問いに対し、「いいや。最初はいろいろまちがえて、うまくいかなかったよ」と正直に答えることを大切にしていました。
なぜなら、仕事では完璧な結果よりも、困難に向き合う姿勢や継続して努力することが重要だからです。
親の失敗談を聞くことで、「お父さんも最初はできなかったんだ」「練習すれば上手になるんだ」と理解し、自分のペースで成長していく自信を持てるようになります。
失敗例は短く!学び・成長・再挑戦に結びつける伝え方
失敗談を子どもに話すときは、ネガティブな部分だけで終わらせず、必ず「その後どうしたか」「何を学んだか」をセットで伝えることが大切です。
失敗から立ち直るプロセスを具体的に示すことで、子どもは問題解決の方法を学びます。
例えば、筆者が作った算数カードについて「算数カードにイラストを入れたら、黒板に注目してくれたよ」と話したところ、娘から「おかあさん、絵、へたくそ!だから、みんな注目したんじゃない?」と突っ込まれたエピソードがあります。
このユーモアあるやりとりも含め、「分からないことは人に聞く」「別の方法を試してみる」「諦めずに続ける」といった対処法を、親の体験談を通して自然に身につけることができます。
失敗から学びを得る姿勢は、近年注目されている「グロースマインドセット(成長思考)」を育みます。親の失敗談を通じて、子どもは「努力で能力は伸ばせる」という確信を持てるのです。
次は失敗を伝える表現の一例です。
- 「今日は書類を間違えてしまったけど、次は気をつけよう」
- 「うまくいかなかったけど、先輩に教えてもらって勉強になった」
- 「失敗したけど次はもっとよくできると思う」
【職業別】子どもに伝わる仕事の説明と伝える工夫
親が自分の仕事を子どもに伝える際には、職業の特徴を活かした説明の仕方を工夫することが大切です。
子どもの年齢に合わせて、具体的で身近な例を使いながら、仕事の意義や社会への貢献を伝えることで、子どもは働くことの価値を自然に理解できます。
どの職業でも共通して大切なのは、日々の体験や感情を込めて話すこと、そして失敗も含めた現実的な仕事の姿を伝えることです。
営業・販売職:「人の役に立つ」を伝える具体的なフレーズ
営業や販売の仕事は、お客様のニーズを理解し、最適な商品やサービスを提案する仕事です。
単に物を売るのではなく、相手の困りごとを解決する問題解決者としての側面を子どもに伝えましょう。
次は説明の一例です。
- 「今日はお客さんに商品を説明して喜んでもらったよ」
- 「困っているお客さんの問題を解決するお手伝いをしたんだ」
- 「お客様の役に立ててうれしかった」
- 「ありがとうって言ってもらえて、この仕事をしていて良かったと思った」
商品やサービスそのものでなく、「人の役に立った」という結果を強調することで、仕事の社会的意義が伝わります。
医療・看護職:命と健康を守る尊い仕事の伝え方
医療や看護の仕事は、人の命と健康を守る尊い職業です。
痛みや不安を抱えた人を支え、回復を見守る喜びを子どもに伝えることで、人を思いやる心の大切さも一緒に学んでもらえます。
次は説明の一例です。
- 「怪我をした人を助けたよ」
- 「病気の人が元気になるお手伝いをしたんだ」
- 「患者さんが笑顔になって安心してくれた」
- 「痛かった人が『ありがとう』って笑ってくれて、本当にうれしかった」
生命の大切さや人を思いやる気持ちを、具体的な患者さんとのやり取りを通して伝えることができます。
飲食・サービス業:食と笑顔を届ける「おもてなしの心」の伝え方
飲食・サービス業は、人の日常生活に欠かせない「食」を通じて幸せを届ける仕事です。
おいしい料理や心のこもったサービスで、お客様の大切な時間を支える喜びを子どもに伝えましょう。
次は説明の一例です。
- 「お皿をきれいにしておいしい料理を届けたよ」
- 「お客さんが笑顔で『おいしい』って言ってくれたんだ」
- 「作った料理で喜んでもらえた」
- 「家族でお祝いをしているお客さんを見て、特別な日のお手伝いができて幸せだった」
食を通じて人を幸せにする仕事の魅力を、お客さんの反応や表情を交えて伝えましょう。
技術・エンジニア職:目に見えない技術を身近な例で説明する方法
技術・エンジニア職は、目に見えない技術で社会を支える仕事です。
複雑な仕組みを身近な例に置き換えて説明し、ものづくりの楽しさや問題を解決する達成感を子どもに伝えましょう。
次は説明の一例です。
- 「電気や水道を直して家の人が安心できたよ」
- 「みんなが使うアプリやゲームを作っているんだ」
- 「新しい装置がうまく動いて役立った」
- 「長い時間かけて作ったプログラムが完成して、たくさんの人に使ってもらえそう」
目に見えない技術を身近な例に置き換えて説明し、創造性や問題解決の楽しさを伝えます。
教育・保育職:次世代を育てる喜びと責任感を伝えるヒント
教育・保育職は、未来を担う子どもたちの成長を支える重要な仕事です。
子どもが新しいことを覚えたり、できなかったことができるようになったりする瞬間に立ち会える喜びと、次世代を育てる責任感を伝えましょう。
次は説明の一例です。
- 「子どもたちに新しいことを教えて、『わかった!』って喜んでもらったよ」
- 「小さい子どもたちと一緒に遊んで、笑顔をたくさん見られたんだ」
- 「子どもが笑顔で遊んでくれた」
- 「できなかったことができるようになった子を見て、一緒に成長している気持ちになった」
次世代を育てる責任感と喜びを、具体的な子どもたちとのエピソードで伝えます。
建設・製造業:形あるもので社会を支える!「ものづくり」の価値と責任感
建設・製造業は、私たちの生活に欠かせない建物や製品を作り出す仕事です。
自分の手で形あるものを作り上げ、それが長い間多くの人に使われ続ける喜びと責任感を子どもに伝えましょう。
次は説明の一例です。
- 「みんなが住む家や学校を建てているんだよ」
- 「みんなが使う車や家具を作っているんだ」
- 「家を建てる人はみんなが安心できる家を作ってくれる」
- 「自分が作ったものが100年後も誰かの役に立つと思うと、とても誇らしい」
長期的な視点で社会への貢献を伝え、ものづくりの価値を実感できる表現を使います。
公務員・公共サービス:街の安心を守る!「社会の土台」としての役割と使命
公務員・公共サービスは、社会全体の安全と安心を支える重要な仕事です。
地域の人々の暮らしを守り、社会の基盤を支える使命感と、困った人を助けることができる喜びを子どもに伝えましょう。
次は説明の一例です。
- 「街の安全を守るお仕事をしているよ」(警察官)
- 「火事や災害から人を助けるお仕事だよ」(消防士)
- 「みんなの手紙や荷物を届けているんだ」(郵便配達員)
- 「警察官は街の安全を守ってくれる」
- 「困っている人を助けることができて、この仕事を選んで良かったと思う」
社会全体を支える使命感と、地域の人々との結びつきを具体的に伝えます。
農業・第一次産業:「命の源」を育む!自然と食を通じて伝える仕事の重要性
農業・第一次産業は、私たちの生命を支える「食」を生み出す最も基本的な仕事です。
自然と向き合いながら食材を育て、多くの人の健康と命を支えている責任感と誇りを子どもに伝えましょう。
次は説明の一例です。
- 「みんなが食べる野菜やお米を育てているんだよ」
- 「魚を取って、おいしい食事ができるようにしているんだ」
- 「農家の人が育てた野菜でおいしい食事ができる」
- 「自分が育てた野菜を『おいしい』って言って食べてくれる人がいると思うと、がんばろうと思う」
食の安全・安心や自然との関わりを通して、生命を支える仕事の重要性を伝えます。
まとめ:親が仕事への誇りを語ることが子どもの未来につながる
親が自分の仕事や働く姿を子どもに語ることは、単なる日常の会話以上の意味があります。
それは子どもにとって初めての社会体験であり、家庭内キャリア教育なのです。
親の言葉や体験の共有は、子どもが働くことの意義ややりがいを理解する手助けになり、学習意欲や社会性の育成にもつながります。
家庭での短い報告や体験を通じて、子どもは挑戦や失敗から学ぶ姿勢を身につけ、将来の選択に必要な判断力や共感力を自然に育むことができます。
毎日の何気ない会話の中で、子どもたちは働くことの意味や喜び、そして責任について深く学んでいるのです。
親の仕事を理解したら、今度は家庭で実際に体験できる活動を通して、より深く働くことを学びましょう。→家庭で体験できる活動
【執筆者:まさこ先生】
元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。
→筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら
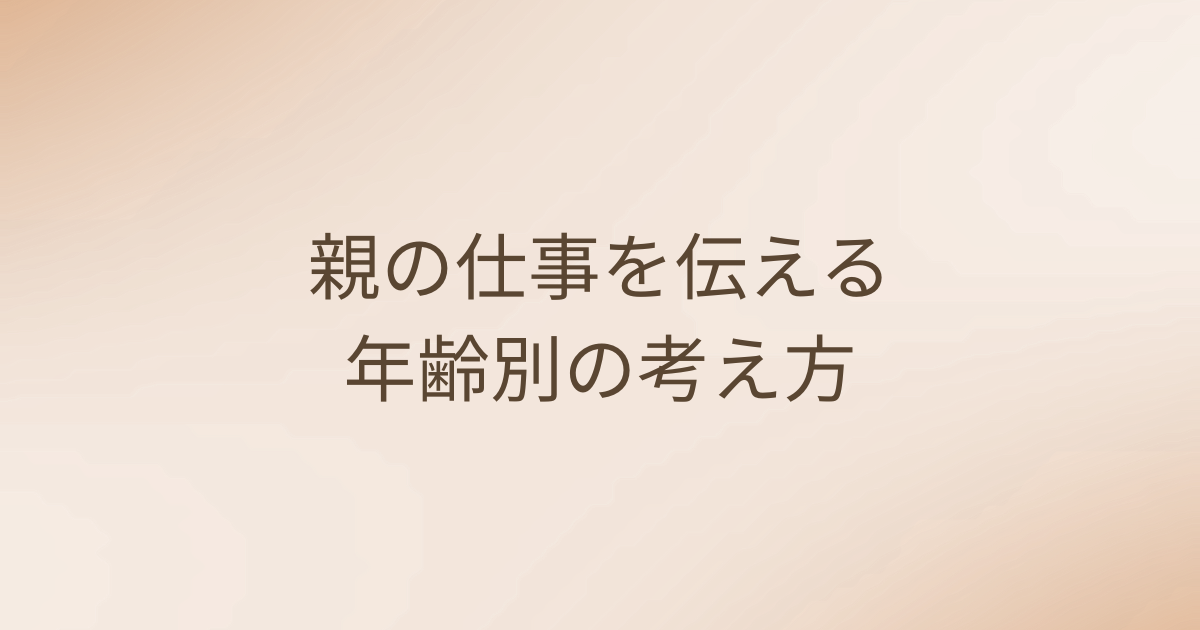
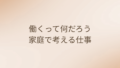
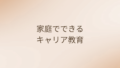
コメント