この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもと保護者に向き合ってきた経験をもとに、家庭で実践できるアイス・ジュースの減らし方ついて解説します。
夏は子どもの活動量が増える分、家庭でアイスや甘い飲み物が習慣になりがちです。
ですが、普段からジュースをよく飲んでいる子は、夏明けに急に授業へ集中できなくなったり、イライラしたりすることが多いと、長年教員として現場に立っていて気づきました。
生活リズムの乱れは多くの子に見られますが、特に甘いものの摂取が多い家庭の子ほど、感情の起伏が激しく、一度乱れると立ち直るのに時間がかかる傾向が顕著でした。
わが家でも試行錯誤がありました。最初の年は完全に禁止しようとして大喧嘩になり、結局、夫が隠れて買い置きしていて失敗したこともあります。
そこから学んだのは、「無理な制限ではなく、家族で納得できるルール作り」が大切だということでした。
この記事で紹介する内容は、「家庭マネジメント」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。
→夏休みの生活リズム崩れを防ぐ!子どもの自己管理能力を育てる実践ガイド
小学校教員目線で分かった「夏明けに集中が落ちる」子の生活共通点
長期休みが終わると、「朝からぼーっとしている」「ちょっとしたことで気分が大きく乱れる」子が一気に増えます。
実は朝ご飯がジュースだけだったり、スポーツドリンクを多用する生活が日常になっている家庭ほど、その傾向が顕著でした。
現場での観察から、「朝からだるい」と訴える子の多くが、朝食を抜いたり、甘い飲み物で済ませていたことがわかっています。
集中力の低下や感情の不安定は日々の食習慣と深く結びついており、休み時間ごとに友達とのトラブルを起こしやすかった子ほど、甘いものの摂取量が多い傾向が見られました。
糖分の多い飲み物は一時的な満足感を与えますが、精製された糖分の急激な摂取は、血糖値の急上昇とその後の急降下をもたらします。
清涼飲料水やジュースのペットボトル1本に含まれる糖分は角砂糖10個以上に相当し、小学生の1日の糖質摂取目安(200〜300g程度)の約2割を占めることになります。
この血糖値の乱高下は、子どもの体にも心にも負担が大きく、集中力の低下やイライラの原因となります。親は、もっと子どもの飲み物に関心を持つ必要があります。
コロナ以降、学校給食では黙食が長く続き、子どもたちが「味覚中心の満足」を求めやすい傾向が強まったと感じます。
給食の前に甘い物を大量に摂ってお腹が空かず、残食が増える子もいます。
※参考資料
厚生労働省「日本人の食事摂取基準」/文部科学省「学校給食摂取基準」/日本食品標準成分表2020年版(八訂)/小児科学会や栄養学の専門家による論文/文部科学省「食に関する指導の手引」
家庭でできる!摂りすぎを防ぐ5つの工夫
工夫1:スケジュールを可視化し夏休み明けの「行動ペース」をつかませる
「いつでもOK」ではなく「15時はおやつタイム」と決めるだけで、子ども自身が行動ペースをつかみやすくなります。集中力維持の土台は、規則正しい生活リズムにあります。
わが家ではホワイトボードに1日の流れを書いて、「今は水分補給の時間」「次が自由あそび」などスケジュールを見える化。
すると、だらだら間食や甘い飲料への欲求も少しずつ落ち着くようになりました。子どもと一緒に「今日のスケジュール」を作り、食のリズムを整えていく。そうした日々の工夫が、心と体の健やかさにつながっていきます。
休み時間と授業の切り替えがスムーズなクラスほど、子どもたちが落ち着いています。
チャイムが鳴る前に次の準備を始める、時計を見て行動する、時間を管理する習慣の積み重ねが、クラス全体を穏やかにしていくのです。
工夫2:「マイボトル習慣」で主体的な水分摂取を促す
ジュースをやめることに成功した最大の理由は、毎朝子ども用の小さなボトルを一緒に準備し、「自分の今日の水分を自分で選んで作る」習慣を取り入れたことです。
代替案を提示することで、子どもは禁止されたと感じることなく、健康的な選択ができるようになります。
専用のマイボトルを用意すると、自分で注ぐ達成感も得られ、「自分の飲み物」という意識が芽生えます。
氷と薄切りのレモン・オレンジなどを入れた”フルーツウォーター”は、見た目も香りも楽しいため、無理なく続けられます。
わが家では新鮮さを重視し、朝に500mlを作り、その日のうちに使い切るルールにしました。衛生面にも気を配り、大きな容器で作り置きせず「少量を毎日作る」スタイルにしました。
コロナ以降、学校では「水筒は麦茶か水に」と統一されている地域が多くなりました。家庭でも、ジュース中心にせず麦茶や水を主にするのが現実的です。
工夫3:ジュースの砂糖を「見える化」し自発的な判断力を育む
家で簡単にできる自由研究としておすすめなのが、「飲み物に入っている砂糖を調べる」実験です。
食育の転換点として、子ども自身が砂糖の量を目で見て理解することで、自発的な判断力が育まれます。
教員時代にも、この活動を授業で行いましたが、児童はとても驚きます。
実際に角砂糖を並べて見せることで、子どもたちは「こんなにたくさん入っているの!?」と驚き、冷たい飲み物は甘さを感じにくいという感覚的な発見や、普段使う角砂糖との比較から、自発的に飲む量を考えるようになります。
家庭で親子一緒に体験すると、「ジュースは飲んじゃダメ」という押しつけではなく、子ども自身の”気づき”として残ります。
数の学習や比較の学びにもつながり、自発的に飲む量を考えるきっかけになります。
- 飲み物に入っている砂糖を調べる方法
用意するものは、角砂糖、ジュースの成分表示、キッチンスケールです。ペットボトルの成分表示を確認し、100mlあたりの糖分量を調べて、実際に角砂糖を並べます。たとえば500mlのペットボトルに糖分が50g含まれていれば、角砂糖(1個約3〜4g)なら12〜17個分に相当します。

500mlのペットボトルのジュースに含まれる糖分を換算した16個の角砂糖
工夫4:手作りアイスで「量・材料・甘さ」を教える夏の実験教材
親子で手作りする楽しさを取り入れると、子どもの満足度も食への関心も高くなります。
食育の機会として、手作りアイスは「量・材料・甘さ」をコントロールできる優れた教材です。
わが家では、ヨーグルトに凍らせたフルーツと少しのはちみつを混ぜて、冷凍庫で数時間冷やすだけのアイスを作りました。
甘さを自分で調整する経験は食に対する主体性を育てます。また、熟れすぎたバナナやキウイをそのまま凍らせるだけの「お手軽アイスバー」もおすすめです。
子どもと一緒に計量スプーンを使って分量を量れば、算数の要素も加わります。「大さじ1は15ml」「2倍は30ml」など、具体的な量や倍率を教える良い機会となり、学びと遊びが結びつきます。
「手を動かす学び」は自己肯定感を高める効果があります。「自分で作った」という達成感が、子どもの表情を変えるのです。
コロナ禍で学校の調理実習が制限された時期もあり、おやつ作りは単なる間食ではなく、学びと成長の場として、家庭での食育がより重要になっています。
工夫5:「買い置きルール」で計画性と選択する力を鍛える
「冷凍庫に常にある」状態は、ついつい食べてしまう習慣化の原因になります。
自己管理能力を育てるために、わが家では週末にだけ「アイス2本までOK」という買い置きルールを設定しました。
子どもに「どの味を選ぶ?」「いつ食べる?」と相談することで、選択する力と計画性を育てる機会になります。
学校でもコロナ以降、物の管理を子ども自身に任せる活動が増えました。文具やマスクの補充、持ち物の整理など、自分で考えて準備する場面が日常的にあります。
コロナ禍で自分の持ち物を自己管理する力が育った今、「自分の食べるもの」も自分で管理する力をつけさせるのが、元教員としてのおすすめです。
学校現場で実感:子どもたちの食事に向かう変化
最近は、栄養バランスを保ちながら季節の果物やデザートを工夫して提供する給食が増えています。
家庭でも栄養面を考慮して、食事の中に冷たいものを1品取り入れるなど、バランスを考える習慣をつけるとよいでしょう。
また、コロナ禍以前のように、わいわいとにぎやかに給食を食べるのではなく、自分のペースで食べ、食材の味を感じ取る「一人で静かに味わう」子が多いと感じています。
一方で会話の機会が減ったことから、「食事の楽しさ」を家庭で補うことが不可欠になっています。
夏休みこそ、食べる時間・内容・量を整え、体と心をリセットする良い機会です。家庭での小さな工夫が、休み明けの落ち着きにもつながっていきます。
親の声かけで変わる!禁止ではなく“共感と工夫”で導く
家庭で規則正しい食事と適切な間食のルールを作ることは、情緒面の安定につながり、その結果として学習に向かう力が高まります。
禁止するよりも共感と選択肢を与えることが続けやすさの秘訣です。
まず、「今日は暑かったね。アイス食べたい?」と共感を示し、「お手伝いの後だから、手作りヨーグルトアイスにしようか!」と代替案やご褒美として提案する方法が効果的です。
子どもが納得して選ぶと、満足感が高くなります。
もし子どもが駄々をこねた時は、「今日はジュースじゃなくて、この冷たいフルーツウォーターと、アイスの代わりに小さいゼリーにしない?」のように提案してみましょう。
「アイスはダメ」では反発を招きますが、理由と代替案を示すと子どもは納得します。
また親自身が冷たい飲み物をほどほどにする姿を見せることも大切です。行動のモデルとなることで子どもは自然に学びます。
「冷たいものを楽しむ=悪」ではなく、「自分で上手に選ぶ力」を育てる意識を持ちましょう。
日々の習慣を整えることで、無理なく健康的な生活リズムを作ることができます。以下はわが家のルーティンです。参考にしてください。
- 朝:水分は常温の水か冷やした麦茶を用意。水筒は朝に満タンにして出かける
- 午前中:遊びで汗をかいたらまず水で一度口を潤す
- 午後15時:おやつタイム。手作りフルーツアイスやヨーグルトバーを用意。市販のジュースはこの時間だけに限定
- 夕方:外遊び後は麦茶。夜は糖分を控えて就寝リズムを整える
- 買い物ルール:週末に家族でアイスの本数を決める。冷凍庫に見える札を貼って残数を管理
おわりに:家庭でできる“夏の健康教育”
アイスやジュースを減らす工夫は、健康だけでなく「生きる力」を育てる教育でもあります。重要なのは「完全な禁止」ではなく「上手に付き合う力」を育てること。
コロナ以降の学校では「自分の体を自分で守る力」を重視しています。こうした学びを支えるのが日々の家庭での習慣づくりです。
元教員・母としての実感は、「食べることを通して、子どもは自分を大切にする力を学ぶ」ということです。
まずは『おやつタイムを15時に固定する』、または『冷蔵庫からジュースを1種類だけ減らす』ことから試してみませんか。
大切なのは、親子で「なぜそうするのか」を話し合い、小さな一歩を踏み出すことです。
この夏の小さな一歩が、2学期の学習に向かう姿勢という大きな変化につながります。焦らず、お子さんの成長を信じて取り組んでみてください。
【執筆者:まさこ先生】
元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。
筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら
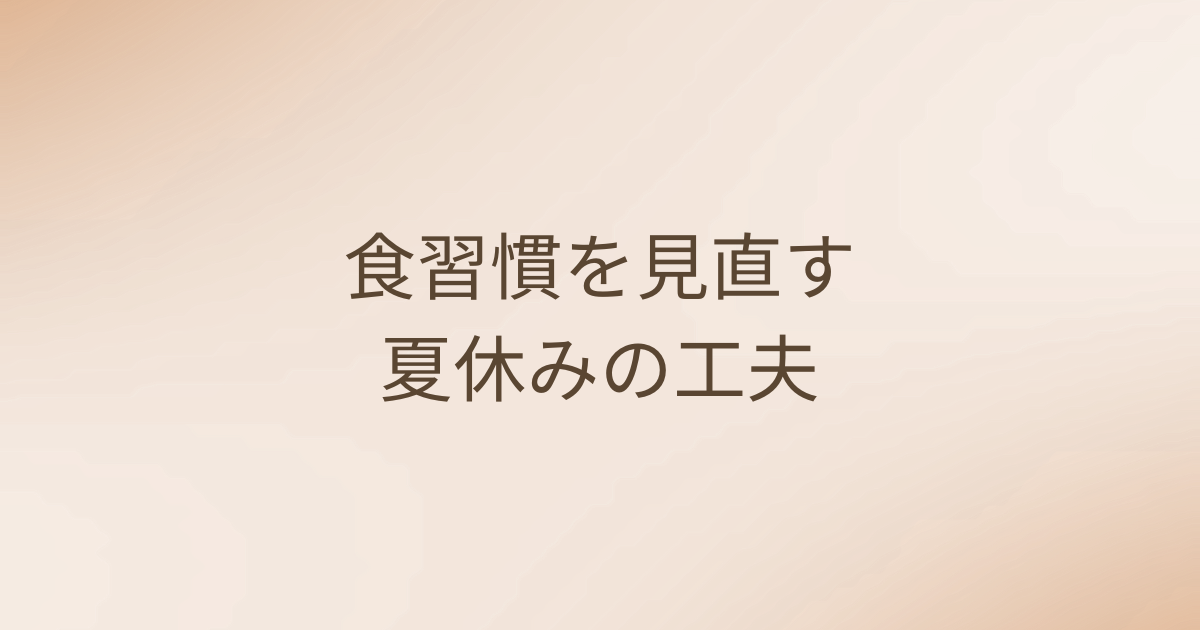
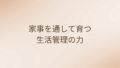
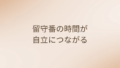
コメント