「気づけば、子どもがスマホの画面ばかり見ていて、こちらの呼びかけにも生返事…。前はもう少し話してくれたのに」——そんな戸惑いを感じたことはありませんか?
今や小学生でも友達とのやり取りをSNSで行い、中高生にもなればYouTubeやInstagram、LINEが日常の一部になっています。親の目から遠いところで、子どもたちの時間が流れているように感じて、もどかしさや寂しさを抱える親御さんは少なくないでしょう。
私自身も、息子や娘がスマホに夢中で、夕食の会話が途切れがちだった時期を経験しました。その中で学んだのは、「距離の取り方しだいで関係は変わる」ということです。
この記事では、私や周囲の保護者の体験を交えて、“SNS世代”との心地いい距離感をつくる方法をお話しします。
スマホ越しの笑顔と、家庭での沈黙
ある日、高校生の娘が帰宅してすぐ、ソファでスマホを見ながらクスクス笑っていました。「何か面白い動画でもあったの?」と聞くと、「別に」と短い返事。そのまままた画面に視線を戻します。

何か面白い動画でもあったの?

別に。
その後、Instagramをたまたま開いた私は、その日娘が友達と撮った楽しそうな写真を見つけました。そこには「今日、最高すぎ!」とコメントが添えられていたのです。家ではそっけない態度なのに、SNSでは満面の笑顔。このギャップに、小さな寂しさと不思議さを感じました。
実は、他の保護者の方からも似た話をよく耳にします。画面越しでは笑顔なのに、親との会話は最小限。それはSNS世代ならではの“外向きの顔”と“家庭での顔”の違いかもしれません。

子どもがスマホに夢中だと「話してくれない」と感じがちですが、スマホやSNSは子どもにとって友達との関係を維持する重要なツールです。特に夏休みは友達との予定や情報交換の時間が増えるため、その時間を否定せず「楽しそうだね」と短く共感するだけでも、子どもは心を開きやすくなります。
親がSNSに関わることで生まれる“近すぎる距離”
私も例外ではなく、SNSを使っています。最初は「いいね」やスタンプを送って子どもたちとつながっている実感を得ていましたが、ある日、娘から「コメントはやめてほしい」とお願いされました。

コメントはやめて。

ただ応援してるだけなのに…。
娘にとって友達とのやり取りは“自分だけの世界”。そこに親が入ることは、たとえ善意であっても、境界を越える行為になると知りました。
それ以来、私はSNSの関わり方を大きく変えました。チェックはしても口を挟まない。必要な連絡はLINEで簡潔に。それでも、疲れた様子の投稿を見つけた日は、直接「温泉でも行かない?」と声をかけるようにしました。
こうした距離感は、まるで庭の植木に水をやるようなもの。毎日ベタベタ構うより、必要な時だけそっと注ぐ方が、関係は長く保てると感じています。
親がスマホを置くと、子どもが話し出す|家庭でできる小さな工夫
ある日の夕方、料理をしながらスマートフォンでレシピを確認していた私に、娘が「ねえ、聞いてる?」と声をかけてきました。そのとき私は、返事をしながらも画面から目を離していなかったのです。

ねえ、聞いてる?

うん…。
「子どもがスマホばかり見ている」と感じていたのに、実は自分も同じように“画面の世界”に没頭していたのでは——そんな気づきがありました。
スマホは便利なツールですが、親が無意識に使い続けていると、子どもとの会話のタイミングを逃してしまうことがあります。
親がスマホに集中している姿は、子どもにとって「話しかけても意味がない」と感じさせてしまう可能性もあるのです。それ以来、私は「スマホを置く時間」を意識するようになりました。
食事中はスマホを手元に置かない。増子どもが話しかけてきたら、画面を閉じて目を合わせる。そんな小さな工夫が、親子のコミュニケーションを自然にやしてくれました。

子どものスマホ時間が増えがちな夏休みこそ、子どもと相談して家庭内ルールを作るのがおすすめです。「食事中はスマホなし」「宿題後は自由時間」など、ひとつに絞るとうまくいきます。
動画サイトに夢中な子どもとの関係づくり
ある時期、娘は学校から帰るとすぐにスマホでYouTubeやTikTokを見ていました。声をかけても気づかないほど集中している姿に、正直イラッとしたこともあります。でも一度、「何がそんなに面白いの?」と素直に聞いてみたら、「この人の話し方がすごく好きなんだ」と返ってきたんです。

何がそんなに面白いの?

この人の話し方がすごく好きなんだ。
それを機に、一緒に視聴する時間を作りました。動画の途中で「この人、説明上手だね」とか「こういうテーマが好きなんだね」と感想を言うと、娘もうれしそうに話を続けてくれます。
この経験から感じたのは、“興味を否定せず、理解しようとする姿勢”が会話の橋渡しになるということ。ルールを押し付けるだけでなく、視聴時間や内容について一緒に話し合える関係が理想だと感じています。

夏休みの自由研究を写真で共有したり、学習動画やダンス動画を一緒に見ることで、親も子どもの興味を理解できます。
親子の距離感を保つための3つの工夫
私が試してみて、効果を感じた工夫がいくつかあります。
「聞く」より「待つ」姿勢を持つ
以前は、娘が帰宅するとすぐに「今日どうだった?」と質問していました。でも、それが逆効果だったようです。「今日はどうだった?」を封印し、同じ空間にいる時間を増やしました。沈黙の5分後に「そういえば今日ね…」と娘が話し出すことも。
今は、リビングで一緒にお茶を飲んだり、テレビを見たりする中で、自然と話し始めるのを待つようにしています。すると、娘の方から「今日ね、ちょっと面白いことがあって…」と話してくれるようになりました。
SNSの話題を共有する
ある日、娘がTikTokのダンスを真似していたので、「それ、最近流行ってるの?」と聞いてみたら、嬉しそうに動画を見せてくれました。
SNSを否定せず、興味を持って聞くことで、会話が広がります。親が「SNS=悪いもの」と決めつけると、子どもは心を閉ざしてしまいます。むしろ、共通の話題として楽しむむしろ、共通の話題として楽しむことで、自然な距離感が生まれるのです。
私も娘が好きなYouTuberの動画を一緒に見たり、Instagramのストーリーを見て「この写真、いいね」と声をかけたり、TikTokダンスを一緒にやってみたりしていました。すると娘は「お母さんもわかってくれるんだ」と感じてくれたようで、以前よりも話してくれることが増えました。
親の気持ちを素直に伝える
娘がスマホばかり見ていて、会話が減ったとき、私は「寂しい」と感じていましたが、それを言葉にするのはためらっていました。ある日、思い切って「ちょっと寂しいな。話したいことがあるんだけど、いい?」と伝えてみました。

ちょっと寂しいな。
すると娘は驚いたような顔をして、

ごめん、気づかなかった。
と言ってくれ、それからは、少しずつ会話の時間が増えていきました。親の気持ちを押しつけるのではなく、正直に伝えること。それは、子どもとの距離を縮める第一歩になるのだと感じました。
完璧な親であろうとするよりも、素直な気持ちを共有することで、親子の信頼関係は深まっていくのだと思います。

孤独感や焦りを感じた時は、自分の感情を受け止めることから始めましょう。私は深呼吸をしたり、パートナーに「今日は子どもと会話が少なくて切なかった」と話すようにしています。
子どもの成長とともに変わる距離感を受け入れる
子どもの成長とともに親子の距離感は自然と変化します。小学生の頃はべったりだったのに、中学生になると急に距離を置かれる。高校生になると、親よりも友達やSNSが優先される。そんな変化に、戸惑いを感じることもあるでしょう。
でも、それは子どもが自立しようとしている証です。「距離がある=関係が悪い」と決めつけるのではなく、適度な距離を保ちながら信頼関係を築いていくことが、SNS時代の親子関係には必要なのだと思います。
私も、娘との関係に悩みながら、少しずつ距離感を調整してきました。SNSを否定せず、干渉しすぎず、でも気持ちは伝える。そのバランスが、親子の信頼を育てる鍵になると感じています。
SNS時代の親子関係に必要なのは“見守る力”と“信じる姿勢”
スマホやSNSは、親子の距離を遠ざける原因にも、つなぐ架け橋にもなります。大切なのは、近すぎず遠すぎない“呼吸しやすい距離”を保つこと。
見守る・信じる・時に寄り添う。
このバランスを意識すれば、SNS時代でも親子の心はつながり続けるはずです。
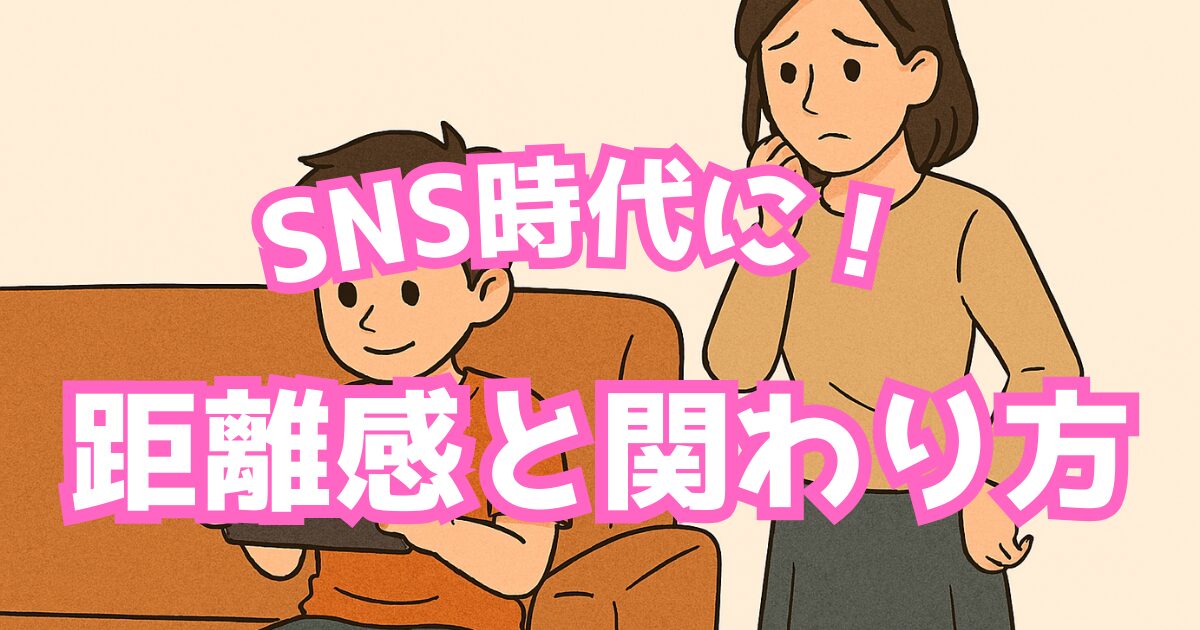


コメント