この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもと保護者に向き合ってきた経験をもとに、家庭で実践できる感情表現力の育て方と親の寄り添い方について解説します。
子どもが自分の気持ちを言葉に置き換えできるようになると、心のモヤモヤが軽くなり、友達との関係や学習への向き合い方も少しずつ前向きになっていきます。
これはテストの得点には表れにくいけれど、将来のコミュニケーション力や人間関係の土台になる、とても大切な力です。
私は、40年間の教員生活と共働きで二人の子どもを育ててきた経験の中で、「気持ちをうまくあらわせない子」が、家庭でのちょっとした遊びや関わりを通して表情豊かになっていく姿を何度も見てきました。
ここでは、忙しい共働き家庭でも無理なく続けられる「感情表現あそび」と、教育現場での経験から見えてきた「子どもの感情を育てる関わり方」をお伝えします。
短い時間の積み重ねが、親子の信頼関係を深めるきっかけになればうれしいです。
この記事で紹介する内容は、「親子コミュニケーション」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。
→ 子どもが本音を話してくれる!“心を開く聴き方と問いかけ”完全ガイド
気持ちを話してくれない子どもの背景と小さなサイン
保護者の相談を受けていると、次のような声をよく耳にしました。
- 「何を考えているのかわからない」
- 「聞いても『別に』『普通』しか言わない」
- 「かんしゃくは起こすのに、理由を話してくれない」
実は、わが家も同じで、息子が小学校低学年のころ、帰宅してから不機嫌なのに、理由を聞くと「なんでもない」とだけ答える日が続いたことがあります。
こちらが「どうしたの?」と重ねて聞くほど、口は固くなるばかり。
そこで、夕食後に手作りの「感情カード」をテーブルに並べて、「今日の気持ち」を選ぶ遊びを始めました。
「うれしい」「かなしい」「くやしい」「びっくりした」など、シンプルな表情と文字を書いたカードです。
すると、いつもは「楽しかった」しか言わない息子が、その日は「くやしい」カードを選び、「図工で思うように作れなかった」と話し始めたのです。
私が「そうだったんだね。がんばったのに思い通りにいかなくて、くやしかったんだね」と返すと、ほっとした表情でうなずきました。
このとき私は、「気持ちを言葉にできるだけで、子どもの心はこんなに軽くなるんだ」と実感しました。感情表現は日々の小さな関わりの中で育っていくものだと気づかされた瞬間でした。
子どもの感情がことばになる仕組みと、家庭で育つ力
感情を言葉にする力は、周りの大人とのやりとりの中で少しずつ育っていきます。教育心理学では、感情を認識し、表現し、整えていく力は、非認知能力の一部とされます。これは、ストレスへの耐性や友達関係の築き方、自分で気持ちを立て直す力に深く関わる土台です。
小学生の時期には、感情の世界も発達していきます。
- 低学年:はっきりした気持ちが中心(うれしい・かなしい・こわい、など)
- 中学年:混ざり合った感情が生まれる(うれしいけれど不安、好きだけど心配、など)
- 高学年:自分の気持ちを一歩引いて見つめる「メタ認知」の芽が出てくる
この時期に大切なのは、子どもの感情を「良い・悪い」で決めつけないこと。
怒りや妬み、怖さも、心からの大切なサインです。「そんなことで泣かないの」「怒るほどのことじゃない」と否定され続けると、子どもは「感じること」そのものにふたをしてしまいます。
学校現場では、感情をカードや絵、ジェスチャーなどで「見える化」することで、自己理解やメタ認知の発達を助けています。
また、物語の登場人物の心を考えたり、相手の気持ちを想像したりする活動は、「心の理論」と呼ばれる他者理解の力を支えます。
つまり、家庭でできる小さな感情表現あそびは、将来のコミュニケーション力の土台を育てる「感情教育」そのものなのです。
家庭でできる“感情ことば”を育てる実践アイデア
実践①:体の動きを使って“言葉にならない気持ち”を表す
気持ちを言葉で表すのがむずかしい子どもでも、体を使うと心の内側がふっと表に出ることがあります。ある日、娘が「さびしいらくだ」と言いながら体を小さく丸めて見せたことがありました。
続けて「怒ってるらくだはね」とポーズを変え、感情ごとの動きを即興で演じ始めました。
言葉で説明しなくても、体の動きにはその子の“今の気持ち”がにじみます。大人が「そんなふうに感じたんだね」と受け止めるだけで、子どもの心がすっと軽くなる瞬間があります。
- 「眠いらくだ」「わくわくらくだ」など感情をつけてポーズをとる
- お互いの動きを見せ合い、「どう感じた?」と一言返す
- 正解探しにしない。子どもの表現をそのまま受け止める
教育では、こうした非言語的な表現が自己理解や情動調整を助けるとされています。遊び感覚ででき、言葉が出にくい子にも自然に取り組める方法です。
実践②:ロールプレイごっこで相手の気持ちを想像する力を育てる
娘はよく「お店屋さんごっこ」や「病院ごっこ」をして遊びました。「甘いりんごです!」「ここが痛いですか?」と役になりきって声をかける姿には、相手の気持ちを思い浮かべる芽が自然に育っているのを感じます。
ごっこ遊びは、大人が教え込まなくても、自分以外の“誰かの気持ち”を考える入り口になります。
親子で役割を交代しながら、気持ちを想像する問いかけを少し加えると、コミュニケーション力の土台が育っていきます。
- 店員さん・お医者さんなど、いろいろな役になりきる
- 「困っている人がいたらどうする?」など気持ちに関する一言を添える
- できばえを評価しない。「今の言い方、やさしかったね」と気持ちに注目する
ロールプレイは、遊びの延長でできる共感・対人スキルの学び。構えずに取り組めるので、忙しい家庭にも取り入れやすい方法です。
実践③:絵本の時間を“感情リレー”に変えて対話を深める
寝る前の読み聞かせは、感情教育に向いた静かな時間です。物語の途中で「この子はどんな気持ちかな?」と一言添えるだけで、子どもは登場人物の心に意識を向けるようになります。
ある夜、主人公を見ながら息子が「この子、悲しいと思う」とつぶやいたことがありました。
「どうして?」と聞くと、「いっぱい怒られると心がしょんぼりするから」と、自分の経験と重ね合わせて話してくれました。物語が心の鏡になり、気持ちを言葉にする練習にもなります。
- 読み聞かせの途中で「どんな気持ち?」と軽く問いかける
- 「もし自分なら?」と無理のない範囲で話してもらう
- 読み終わりに一言だけ感想を交わす
こうした短いやりとりは、他者の心を思い描く力(心の理論)の土台になります。忙しい日でも数分あればできるシンプルな習慣です。
うまくいかなかった日こそ、やり直しのチャンス
ここまでお伝えしてきましたが、私自身、最初からうまくできていたわけではありません。むしろ、失敗から学んだことのほうが多いと感じています。
息子が幼いころ、「もう学校行きたくない」と泣いたとき、忙しかった私は「そんなことで泣かないの。明日になったら平気よ」と言ってしまったことがあります。
その瞬間、息子は口をつぐみ、翌朝も本当の気持ちを話してくれませんでした。
教員として子どもの話を丁寧に聞いていた一方で、自分の子どもには「早く落ち着かせたい」という焦りから、気持ちを否定する言葉を投げかけてしまったのだと後から気づきました。
それ以来、私は「まず3秒、黙って表情を見る」「最初のひと言は『そうだったんだね』にする」というルールを自分の中に作りました。
息子が「もう嫌だ!」と感情的になったときも、ぐっとこらえて「嫌になるくらい、つらかったんだね」とだけ返してみると、しばらくして「だってね……」と話し始めてくれました。
親が「さっきは言いすぎちゃったね」と言い直す姿そのものが、子どもにとって大きな安心材料になります。
今日からできる小さな一歩
感情を言葉や動きで表せることは、友達との関係づくりや、困難を乗り越える粘り強さにつながる、子どもの「生きる力」の土台です。
特別な教材や長い時間は必要ありません。
夕食後の10分の「こころタイム」、寝る前の絵本の一言、「今日はどんな気持ちだった?」というささやかな問いかけ。そんな小さな習慣から、子どもの感情表現は少しずつ育っていきます。
うまくいかなかった日は、「さっきは○○って言ったけれど、本当はこう伝えたかったな」と親の気持ちを言い直してみてください。それも立派な感情教育です。
まずは今日、一つだけでもできそうなことを試してみましょう。お子さんの中に眠っている気持ちのことばが、少しずつ姿を見せ始めるはずです。
【執筆者:まさこ先生】
元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。
→筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら
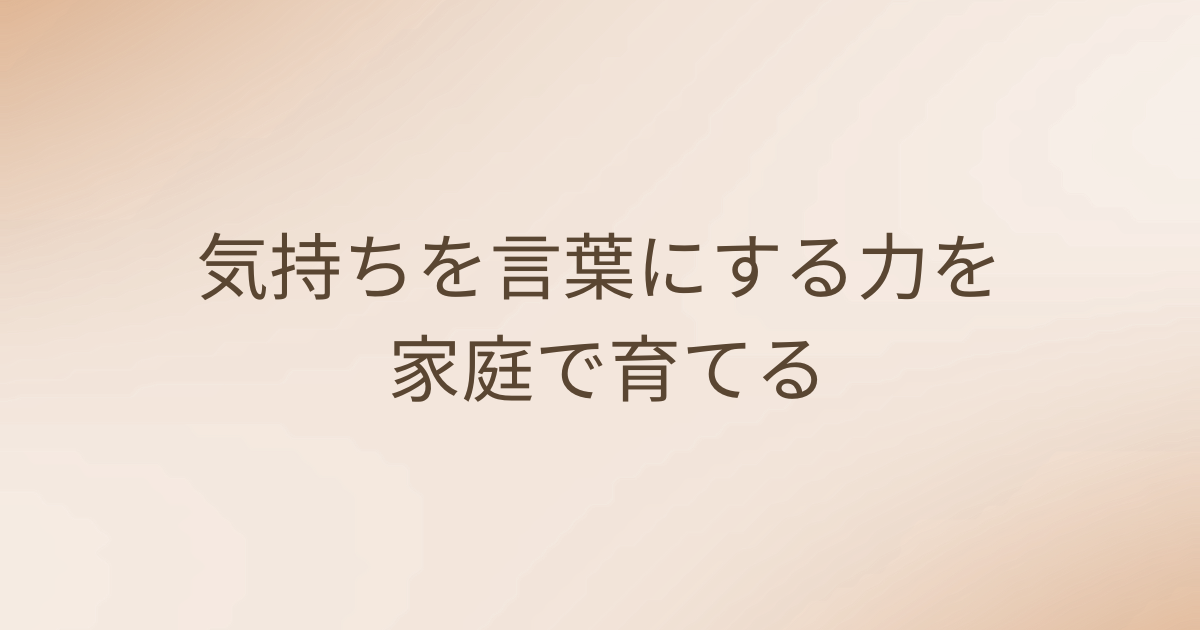

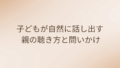
コメント