今やスマホやゲームは、子どもの日常に欠かせない存在です。特に夏休みは時間があるぶん、気づけば何時間も画面を眺めてしまうこともあります。私自身も「最近、息子がずっと動画を見ていて宿題が止まっている」「娘が夜おそくまでSNSをして朝起きられない」と悩んだ経験があります。
そこでわが家では「ただ制限する」よりも「親子で一緒に考える」「自然に切り替えができる工夫」を心がけてきました。
本記事ではその具体的な工夫と体験談を紹介します
スマホ時間を整える“見える化”習慣術
小学生の息子に「ゲームばかりしないで!」と言っても、ケンカになるばかりでした。そこで試したのが“見える化”。リビングにホワイトボードを置き、1日の流れを絵と文字で簡単に書き出したのです。
「朝は宿題」「昼は自由時間」「夕方は散歩」とシンプルに区切り、横にマグネットやキャラクターのシールを貼れるようにすると、息子は自分から動きました。ある日、ゲームに夢中なときに私が、

今は何の時間かな?
と聞くと、本人が

宿題の時間だった!
と自分で気づき、机に向かったのです。
強制で止めさせるよりも、“時間を見えるようにする”ことで自然と切り替えやすくなると実感しました。

小学生は、まだ時間の感覚や自己管理の力が育っている途中です。「今は何をする時間か」「どこまでやったら終わりか」が“見える”ことで、安心して行動できるようになります。
スマホルールより“親子の対話”が効く!わが家の実践と気づき
娘が思春期のころ、私は「1日1時間まで!」と厳しく決めたことがあります。しかしあっという間に守れなくなり、毎日のように火花の散るやりとりになりました。
そこで視点を変え、「ルールを押しつける」のではなく「まず話を聞く」ことから始めました。夜遅くに

最近寝る時間が遅いけど大丈夫?
と声をかけると、娘が、

SNS見てるとつい時間が飛んじゃう。
と正直に話してくれました。その日から、毎週日曜日の夜に

今週どのアプリをよく使った?
楽しかった?疲れた?
と語り合う習慣を追加。娘が自分で使い方を振り返るようになり、ただ禁止するよりもずっと効果がありました。
ルールを守らせるより、「一緒に考える仲間」になることが、親子の信頼関係を深める鍵になるのだと思います。
スマホは心の居場所にもなる。子どもと一緒に考える使い方
大人から見ると「スマホは悪いもの」というイメージを持ってしまいがちですが、子どもにとっては支えになる瞬間も多くあります。
娘が高校生だった頃、帰宅後すぐに音楽アプリでお気に入りの曲を聴いて気持ちを落ち着かせたり、友達とチャットして励まされていました。
彼女が

スマホ見てるとちょっと元気になれる。
と言ったとき、私は、

無理に取り上げるのではなく、どう活用するかを一緒に考えればいいんだ。
と気づきました。
親のスマホ時間が子どもに影響?“見せる背中”が育てる習慣
私は一度、娘に「スマホばかり見ないで!」と注意した直後、自分がSNSをひたすらスクロールしていることに気づきました。その時の娘の冷たい視線に反省し、わが家では夕食後30分は“全員ノースマホタイム”と決めました。
その間はトランプやカードゲーム、時には日中の出来事を語り合うだけ。不思議なことに、私自身も「画面を見ない時間」が気持ちの切り替えになり、子どもからは「ママも一緒に遊んでる感じがしてうれしい」と言われました。
親の姿は、言葉以上に子どもに影響を与えるのだと実感しました。ある保護者の方は、
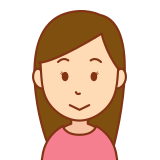
親がスマホを置いたら、子どもも自然と手放すようになりました。
と話してくれました。“見せる背中”は、言葉以上に強いメッセージになるのだと思います。
また、教室で、

おうちの人はスマホをいつ見てる?
と聞くと、

ずっと見てる!

ごはんのときも見てる!
という声がちらほら。その後、

じゃあ、家族でスマホを置いて遊ぶ時間を作ってみよう!
と提案すると、「昨日は一緒に折り紙した!」と嬉しそうに報告してくれる子もいました。
スマホルールは“押しつけ”より“納得感”。親子で育てる3つの約束
「ルールは親が押しつけるもの」ではなく「一緒に育てていくもの」と思っています。そこで娘と一緒に考え出したのが、次の3つ。
・家族で食事中は机の上にスマホを出さない
・使いすぎた次の日は控えめに過ごす
ポイントは「親が決める」のではなく「子が提案したものを取り入れる」ことでした。
わが家の場合は娘が「食事中はやめよう」と自分から言い出したため、納得して守れるようになりました。守れない日もありましたが、「なぜそうなった?」を一緒に振り返る時間が、何より貴重でした。
教員時代、保護者の方から

ルールを守らせるのがつらい。
と相談されたことがありました。

ルールは“育てるもの”ですよ。
とお伝えすると、

一緒に考えるようになって、子どもが自分から工夫するようになりました。
と後日、笑顔で報告してくれました。
スマホなしでも楽しい!親子で育む“オフライン時間”のすすめ
スマホ以外に「楽しみ」を用意することも大切です。休日には子どもと一緒にホットケーキを焼いたり、アイスを手作りして「今日はどんな味にする?」と話しながら楽しみました。出来上がったお菓子を食べる時間は、スマホ以上に盛り上がり、家族の笑顔も増えました。
ほかにも、夜にベランダで星を見たり、近所の公園で虫探しをしたり、小学生の頃の息子は落ち葉を集めて「秋の作品集」を作ったこともあります。
こうしたオフラインの時間の積み重ねが、子どもの「自分はスマホ以外でも楽しめる」という感覚を育ててくれました。
兄弟でスマホルールが違ってもOK!年齢に合わせた納得の工夫
兄弟姉妹がいる家庭では、スマホの使い方に関するルールをどう分けるかが大きな課題になります。私の家庭でも、中学生の妹と高校生の兄でスマホの使い方に差があり、最初は

なんでお兄ちゃんは長く使っていいの?
と妹が不満を漏らすことがありました。そこで私たちは、年齢や発達段階に応じたルールを設けることにしました。
妹には「1日30分まで」「使うときはリビングで」「使った後は一緒に内容を振り返る」といった見守り型のルールを。兄には「1日1時間まで」「自分で時間管理をする」「週末に使い方を振り返る」といった自己管理型のルールを設定しました。
もちろん、きょうだい間で「不公平」と感じさせない工夫も必要です。
娘が小学生の時、

お兄ちゃんばっかりずるい!
と言ったとき私は、

お兄ちゃんは中学生で、学校の調べ学習もあるからね。でも、○○ちゃんも大きくなったら同じように使えるよ
と伝えました。
さらに、娘がスマホを使った後に「こんな動画見たよ」と話してくれたときは、「面白そうだね!今度一緒に見てみようか」と声をかけることで、使い方そのものを肯定的に受け止めるようにしました。
きょうだいそれぞれの成長段階に合わせてルールを柔軟に変えることは、子どもたちの納得感を高めるだけでなく、親子の信頼関係にもつながります。
「うちのルールはこうだから」ではなく、「あなたに合ったルールを一緒に考えよう」という姿勢が、家庭の中に安心感を育ててくれるのです。
家庭と学校が連携すると子どもが変わる!スマホ習慣を育てる対話術
スマホの使い方について悩んでいたある保護者の方が、「学校の先生と話してみたら、子どもが意識するようになった」と話してくれたことがあります。
私自身も教育現場で働く中で、家庭と学校が連携することで子どもの行動が変わる瞬間を何度も見てきました。たとえば、「家庭でのスマホルールを共有するアンケート」を実施し、保護者と先生が情報を交換する場を設けたことがあります。
その結果を受けて、授業中に、

スマホの使い方、みんなはどうしてる?
と話題にすると、子どもたちが、

うちではこうしてるよ!
と自然に話し始めたのです。家庭でのルールが学校でも話題になることで、子どもにとって“スマホの使い方”が自分ごとになっていくのを感じました。
また、面談の際に保護者の方から

スマホの使い方が気になっていて…。
と相談されたこともあります。

学校でも使い方を意識するように声かけしてみますね。
とお話しすると、

どうしたらよいか悩んでいたので助かります。
とのこと。
家庭だけで悩まず、学校とつながることで得られる安心感は大きなものです。学校の先生との対話は、親にとっても「一人で抱え込まなくていいんだ」と感じられる支えになります。
教育現場の視点を活かしながら、家庭と学校が協力して子どものスマホとの付き合い方を育てていく——それこそが、現代の子育てにおいて欠かせないアプローチだと感じています。
スマホとの距離感が親子関係を育てる。夏休みに見直したい習慣
スマホやゲームの使い方を見直すことは、単なる時間制限ではなく「親子の関係を深めるチャンス」だと感じています。
子どもと一緒にルールを作り、時には話し合いながら修正していく過程で、親も子どもも互いの気持ちを理解できるようになります。
この夏休み、親子で「スマホとちょうどいい距離感」を探す実験をしてみてください。ほんの小さな工夫が、家族みんなの生活を心地よく変えてくれるはずです。



コメント