夏休みは、子どもにとって一年の中でもっとも開放感に満ちた季節です。友達と朝から駆け回ったり、家の中で夢中になって遊んだり、子どもは日々を冒険のように楽しみます。
しかしその陰で、親はというと、夏休みの生活を支える大黒柱として、料理や宿題の声かけ、遊びの計画、送迎、さらには仕事との両立が重なり、息つく暇がないのが現実です。「今日は自分の昼ごはんをまともに食べただろうか」と夜になってから思い出すこともしばしば。
加えて、夏の灼熱の陽射しは、体力をあっという間に奪っていきます。冷たい飲み物ばかりに手が伸び、夕食の時間になっても子どもたちからは「食べたくない」「疲れた」という声がもれてくる。親の私まで同じように体がだるくなり、頭が重く、何もする気が起きなくなる日もありました。
そうしたとき、笑い声の少ない家の空気を感じて、「このままでは夏休みそのものが辛い思い出になってしまう」と不安になったのです。
そこで見直したのが「作りおき」でした。作りおきと聞くと、時間を節約する小技のように思えるかもしれません。しかし私にとってはそれ以上の意味を持ちました。冷蔵庫に彩りのある料理が一つでも並んでいるだけで、子どもが「これなら食べてみようかな」と言えたり、自分も安心して「少し食べておこう」と思えたりするのです。
この記事では、実際にわが家で役立った作りおきと、それが親子の心と体をどう支えたか、自分の体験をもとに詳しく綴っていきます。
親子で夏バテしたわが家のエピソード
もう20年も前の夏休みのことです。仕事の締切に追われていた私は、パソコンに向かいながら子どもの昼食を急いで用意し、自分はパンの一切れとコーヒーで済ませるような毎日を送っていました。
気温は35度を超える酷暑の日々。扇風機の前に座っていても汗は止まらず、午後になると頭がくらくらし、文字を眺めていても頭に入らなくなるような状態でした。
子どもたちも例外ではなく、息子は外でボール遊びを続けて帰宅すると、そのまま床に寝そべり

なんだか体が重い…。
と力なく話しました。娘もアイスやジュースばかり欲しがり、夕食時には

もう要らない…。
と首を振るばかり。
食卓に家族がそろっていても、会話はほとんどなく、ただ時間だけが過ぎていく。笑い声の少ない食卓を見て、夫が

最近家の空気が暗いな…。
とぽつりとつぶやいたとき、私は冷蔵庫を開け、中に入っているのが冷凍麺やゼリーなど冷たいものばかりであることに気づきました。
そのとき初めて背筋が寒くなり、このままでは本当に皆が倒れてしまうかもしれないと心底怖くなったのです。次の日から、私は「親子の体を守る食事」を意識しながら作りおきを始めることにしました。
夏バテ対策に効いた!親子で食べられる作りおきレシピ5選
夏バテ対策には、栄養バランスと食べやすさが鍵とわかっていても、忙しい夏休みの中で毎食それを意識するのは至難の業でした。
そんな時私を助けてくれた親子で食べられる「作りおきレシピ」を5つ紹介します。
ササミときゅうりの梅ポン酢あえ

ササミときゅうりの梅ポン酢あえ
炎天下の公園で友達と走り回り、帰宅後もゲームに夢中になっていた息子は、翌日の朝布団から出てこず、

ごはんいらない…。
と弱々しくつぶやきました。聞けば水分補給もろくにしていなかったよう。
そこで冷蔵庫から前夜に作っておいた梅ポン酢和えを取り出し、冷たい器に盛りつけて、麦茶と一緒にそっと差し出すと、息子はひと口食べて

…これ、さっぱりしてて、食べれる。
その言葉に、私は思わずほっと息をつきました。
材料:鶏むね肉、きゅうり、梅干し、ポン酢
作り方:鶏むね肉を茹でて裂き、きゅうりと梅干しを和えてポン酢で味付け
ポイント:梅の酸味で食欲アップ。冷たくても美味しい
夏野菜のカラフルラタトゥイユ
娘は昔から野菜が苦手で、特にナスやズッキーニは「見た目がイヤ」と言って避けていました。食卓に並べるたびに

これ、ズッキーニ入ってる?
と警戒するような様子で、私もつい控えめに使うようになっていたほどです。
そんなある日、娘は冷蔵庫に作りおきしていたラタトゥイユを見つけて目を輝かせました。トマトの赤、パプリカの黄色、ズッキーニの緑が混ざり合った彩りに惹かれたようで、

自由研究は”野菜の色と栄養”にしよう!
と、さっそくスケッチブックを取り出して色鉛筆で描き始め、野菜の名前や栄養素をメモしていました。
材料:ズッキーニ、なす、トマト、パプリカ、玉ねぎ
作り方:野菜を炒めてトマト缶で煮込むだけ
ポイント:冷やしても美味しく、パンやごはんに合う万能副菜
豆腐と枝豆のごまポン酢サラダ

豆腐をつぶす作業は、娘にとってちょっとした遊びのようで、

ぎゅーって押すのが楽しい!
と笑いながら、小さな手で丁寧に豆腐を崩していく姿は、まるで粘土遊びの延長のよう。指先に力を込めながらも、どこか誇らしげな表情を浮かべていました。
枝豆をゆでて冷ましたあと、

さやに豆が残らないようにね。
と声をかけると、娘は真剣な顔つきで一粒ずつ丁寧にむいていきました。途中で

これ、ちょっと固いかも。
と言いながら、指先で確認するように集中して豆を取り出していました。
完成した豆腐と枝豆のサラダを盛りつけると、

これ、私が作ったんだよ!
と嬉しそうに食卓に並べてくれました。
材料:絹ごし豆腐、枝豆、ポン酢、ごま
作り方:豆腐を水切りし、枝豆とごまを加えてポン酢で和える。
ポイント:火を使わず、たんぱく質とミネラルがしっかり摂れる。
ひじきとツナのマリネ風

ひじきとツナのマリネ風
夏休みのある日、娘が

お腹が痛い…。
と訴え、心配になって病院へ。診察の結果は
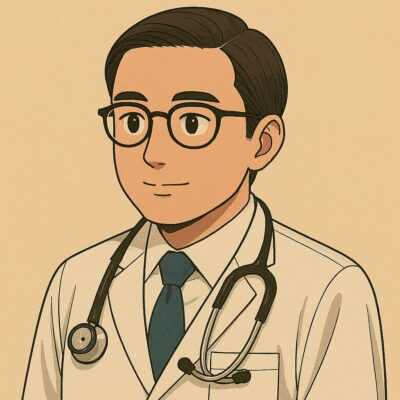
軽い便秘ですね。食物繊維を意識してみてください。
とのこと。
帰り道、スーパーの棚で乾燥ひじきを見つけたとき、私は

これなら鉄分も食物繊維も摂れる!
と思い、迷わずかごへ。
とはいえ、娘は黒っぽい食材が苦手。そこで、彩りににんじんを刻み、娘の好きなツナを加えて、ほんのり甘めの味付けでマリネ風に仕上げました。
器に盛って出すと、娘は

これ、給食みたい!
と笑いながらひと口。いつもなら警戒するはずの黒系の副菜を、すんなり完食してくれました。
材料:乾燥ひじき、ツナ缶、にんじん、酢、醤油、砂糖
作り方:ひじきを戻して茹で、ツナとにんじんを加えて調味料で和える
ポイント:鉄分・食物繊維が豊富で、便秘対策にも◎
ササミとオクラの中華風サラダ

ササミとオクラの中華風サラダ
ある晩、夏バテ気味で食欲が落ちていた夫に、ささみとオクラの中華風サラダを出してみたところ、

これ、ビールに合う!
と目を輝かせて上機嫌に。
普段は黙々と食べるタイプなのに、その日は

これ、また作ってほしいな!
と言いながら、ゆっくり味わっていました。
子どもたちは冷やしうどんにのせて食べるのが定番で、娘は

ネバネバって元気になるんだよね?
と、オクラの断面を見ながら嬉しそうに話していました。

星形の切り口を見て「宇宙みたい!」とスケッチブックに描き始めたこともあり、食卓がちょっとした自由研究の場になりました。
材料:ささみ、オクラ、ごま油、酢、醤油
作り方:ささみを茹でて裂き、オクラと調味料で和える
ポイント:ネバネバ食材で胃腸を整える効果も
作りおきで整える生活リズムとセルフケア
夏休み中は、つい自分の昼食を後回しにしてしまうことがありました。ある日、水分も栄養も不足したまま午後を迎え、頭痛とめまい、視界のぼやけに襲われて

これはまずい…。
と感じたのをきっかけに、「自分のための作りおき」を意識するように。
冷蔵庫に、いつもの副菜があるだけで

とりあえずこれを食べよう!
と思える安心感があるのと、火を使わずにすぐ食べられるものがあることで、食事の準備に負担感を感じることが減りました。
作りおきは、子どもたちにとっても“選べる楽しさ”を生みました。
夏休み中、息子は

今日はお腹すいてない。
と昼食を残すことが増えていましたが、冷蔵庫に並んだ透明容器の副菜を見て、

これ、昨日のやつだよね?さっぱりしてて好き。
と自分で選んで食べるように。
娘は盛りつけを手伝うのが好きで、

今日はオクラの星を並べるね!
とシェフを気取って器にきれいに並べてくれました。
作りおきがもたらす家族の時間
夏休み中、午前は子どもたちの宿題を見て、昼食を作って、午後は仕事の準備。夕方には買い物と夕食の支度…そんなルーティーンに追われていたある日、ふと

あれ?今日、自分のために何かしたかな?
と立ち止まりました。
そこで冷蔵庫からラタトゥイユを取り出して器に盛り、麦茶を注いで静かなキッチンで一人ランチをとりました。
ほんの10分ほどの時間でしたが、「ちゃんと食べた」「自分をいたわった」という感覚が、午後の疲れをぐっと軽くしてくれたのを覚えています。
また、夏休み中は息子が

今日は何食べるの?
と毎日のように聞いてきたのですが、

冷蔵庫にあるやつ、自分で選んでいいよ。
と言ってみたところ、ぱっと表情が明るくなり、

じゃあ、梅ポン酢のやつと、オクラのサラダにする!
と自分で器を出して盛りつけ始めました。
その姿を見て、

自分で選べるとこんなに嬉しんだ…。
と気づきました。
ある週末、予定が詰まっていて

夕食どうしよう…。
と悩んでいたときも、冷蔵庫に作りおきがあることを思い出し、それらを器に並べて夕食に。
内心

手抜きかな…。
とひやひやしていたのですが、食卓に座った夫が

今日は豪華だね!
と言い、子どもたちも

これ、飽きないよね!
と笑顔に。
台所の片付けも楽で、食後には家族でトランプをする“余白”の時間まで生まれました。
作りおき習慣を続けるためのコツと工夫
作りおきは、始めるより「続けること」が難しい。最初は意気込んでも、忙しさや疲れで挫折してしまうこともあります。
私も何度か「もうやめようかな…」と思ったことがありましたが、ちょっとした工夫で「習慣」に変えることができました。
週末にまとめてではなく、すきま時間に1品ずつ作る

昼食づくりの合間にほぐしたササミ
以前は「週末にまとめて5品作るぞ!」と意気込んでいましたが、土曜の午後に疲れ果てて

もう無理…。
と挫折。そこで発想を変え、「平日のすきま時間に1品ずつ作る」スタイルに切り替えました。
例えば、朝の味噌汁を作るついでにひじきを戻しておく、夕食の準備中に鶏むね肉をレンジにかけて、裂いておく。これだけで、気づけば冷蔵庫に3〜4品が自然と揃っているのです。

まとめてやらなくていい。
と思えるだけで、気持ちがぐっと楽になり、続けやすくなりました。
選べる楽しさを演出できる”中身が見える”保存容器

わが家で愛用している中身が見える保存容器
タッパーに詰めて冷蔵庫に入れると、「何が入ってるかわからない」と手をつけないことが多くあったため、ガラスの耐熱性保存容器に変え、ラベルを貼るようにしました。
すると、息子が

今日はこれにする!
と自分で選ぶようになり、娘も

色がきれいだからこれ食べたい。
と言ってくれるように。見える化すると食事は楽しみになるということに気づきました。
アレンジ自在なレシピで飽きない工夫
ラタトゥイユは、冷製パスタ、トースト、オムレツの具材など、何通りにもアレンジできる万能レシピ。
娘は

今日はイタリア風にする!
とトーストにのせてチーズをかけて焼くのが定番。息子は

ごはんにのせて丼にする!
と自分流に楽しんでいます。子どもたちが眠った後は夫婦でワインの肴にすることも。
同じ作りおきでも、食べ方を変えるだけで飽きずに続けられる。家族それぞれの好みに合わせてアレンジできるレシピを選ぶのが、継続のコツです。
「自分のため」のつくりおきを必ず一品常備する
作りおきは、つい「家族のため」に偏りがち。でも、私が一番助けられたのは「自分のための一品」でした。
豆腐と枝豆のサラダや、ひじきのマリネは、私がさっと食べられる“心の栄養”で、娘がよく

おかあさん、これ好きだよね~。
と言って私の分をよそってくれ、その姿を見て

明日もがんばろう!
と思えました。
完璧を目指さず、ゆるく続けることが大切
「毎日作らなきゃ」「栄養バランスを完璧にしなきゃ」と思っていた頃は、プレッシャーで疲れてしまい、続きませんでした。けれど、ある日夫が

冷蔵庫に何かあるだけでありがたいよ。
と言ってくれたことで、肩の力が抜けました。
それ以来、「1品でもあればOK」「昨日の残りでも立派な作りおき」と思うように。完璧を目指さず、ゆるく続けることで、作りおきは“習慣”になっていきました。
まとめ:作りおきは、親子の暮らしを支える“やさしい習慣”
作りおきというと、「時短術」と考えがちですが、実践してみると、忙しさに追われがちな夏休みの中で、親子の体調を整え、心に余裕を生み出す“暮らしの土台”になってくれました。
また、毎日の食事に少しだけ先回りすることで、「今日もちゃんと食べられた」「家族が笑ってくれた」と、私自身、安心することができました。
今年の夏は、作りおきを通して、食卓にほんの少しの余白と、親子の笑顔を増やしてみませんか。忙しい日々の中でも、台所から始まるやさしい習慣が、暮らしの空気をそっと変えてくれるはずです。



コメント