この記事は、小学生の子どもを育てる保護者に向けて、元小学校教員として40年間、子どもの成長を見てきた経験から、家庭で実践できる簡単でおもしろい科学実験について解説します。
猛暑や人混みを避けたい夏休み。「おうち時間をどう過ごそう」と悩んでいませんか。
五感を使って夢中になる実体験は、知識を詰め込むより深く記憶に残り、子どもの探求心を育てます。
たとえば「台所を研究室に変える」――普段の食材が驚きの実験材料に。「どうして膨らむの?」といった身近な疑問を一緒に考えることで、好奇心が自然と引き出されます。
この記事で紹介する内容は、「家庭での学びと体験」の考え方の一部です。親子の関わり方全体の視点については、こちらの記事で詳しくまとめています。
→子ども主体のおうち夏祭り|自己肯定感につながる家庭イベントの工夫
低学年・幼児向け:準備が簡単!「なぜ?」を引き出す科学実験4選
準備も簡単、結果もすぐに見える実験で、小さなお子さんでも楽しく科学に触れられます。観察する習慣を身につけながら、家族みんなで「なるほど!」を体験しましょう。
氷の溶け方くらべ:熱の伝わり方と環境の影響を学ぶ
ある日、子どもが「氷って外と中でどっちが早くとける?」と疑問を口にしたことが、この実験のきっかけでした。
この実験は、熱の伝わり方や周囲の環境(温度、風、日当たり)が物質の状態変化に与える影響を観察するのに最適です。
同じ大きさの氷を二つのコップに入れ、一つを室内、もう一つを庭の日の当たる場所に置くことで、溶けるスピードが大きく異なることがすぐに分かります。
庭のコップに風が吹くと、氷が一気に小さくなる様子が見られ、子どもたちは「風の強さや日当たりでも全然違うね」と、環境要因による変化に自ら気づきをメモしていました。
準備が簡単で失敗のリスクも少ないため、「次はコップの種類を変えてみよう」といった次の工夫案が自然と生まれやすく、探究の連鎖を促します。
観察と記録の習慣を身につけるための最初のステップとしても有効です。
実験の手順は次のとおりです。
- コップを二つ用意する
- それぞれに氷を入れる
- 一つは室内、もう一つは窓辺や日なたに置く
- タイマーや時計で時間を測る
- 氷の大きさの変化を観察してメモする
- 風や日当たりなど条件の違いも比べてみる
葉っぱの形と色さがし:自然の多様性と観察眼を育む
ある蒸し暑い午後、家族で近くの公園にピクニックに出かけた際、娘が夢中で葉を拾い集めていました。
「この葉っぱ、不思議な形!」という娘の声をきっかけに、家に戻るとダイニングテーブルいっぱいに葉っぱを広げ、家族で色や厚み、手触りを比べる研究会に突入しました。
「こっちはギザギザ、あっちは丸いね」と私が声をかけると、娘はルーペで観察しながら「葉脈が星みたい」と、娘ならではの表現で発見を共有してくれました。
集めた葉を厚紙にテープで固定し、裏には発見した特徴や小さなイラストを添えて”オリジナル標本ノート”を作成。
身近な自然素材を使うことで、観察眼と記録力が自然と身につきます。また、形や色の違いを分類・整理する作業は、論理的思考の基礎を養います。
実験の手順は次のとおりです。
- 散歩や庭で葉っぱを集める
- テーブルに並べて色や形、大きさを比べる
- ルーペで葉脈や細かい模様を見る
- 見つけた特徴を声に出して確認する
- 厚紙に貼って簡単なカードや標本にまとめる
水の量で音階を作ろう!コップで学ぶ「音の科学」
娘が小学2年生のとき、キッチンでコップを叩いて遊んでいたのがきっかけです。
「水の量で音が変わるよ」と私が声をかけると、すぐにコップを並べて水を少しずつ入れ、スプーンで叩きながら音の違いを確かめ始めました。
途中で量を間違えて音が揃わず、困惑していた娘に「少しずつ水を調整してみよう」と助言すると、何度も試行錯誤し、最後には「ド・レ・ミ」に近い音階を完成させ、「やったぁ!”チューリップ”の曲に聴こえるよ!」と大喜びしました。
この試行錯誤こそが、学びの鍵です。コップの中の水の量が振動の仕方に影響し、音の高さ(周波数)が変わることを体感できます。
自分で調整を繰り返すことで、原因と結果の関係を論理的に理解する力が育まれます。
実験の手順は次のとおりです。
- 同じ形のコップを数個用意する
- それぞれに水を少しずつ入れる(量を変える)
- スプーンで叩いて音の高さを確かめる
- 音が揃わなければ水を足したり減らしたり調整する
- 音階を紙に記録する
食塩水 vs. 真水のうきしずみ:比重と浮力を体感する
息子が小学4年生の時、ペットボトルに真水と食塩水を作り、卵をそっと入れて浮くか沈むかを試しました。最初は沈んでしまったため、「少しずつ塩を増やしてみよう」とアドバイス。
息子は調整を繰り返し、最終的に卵が浮く条件を見つけ、「塩を入れたら浮くんだ!」と驚きながら観察していました。
この実験は、水溶液の濃度と浮力(比重)の関係を学ぶのに最適です。真水と食塩水の違いから、ものが浮く条件を視覚的に捉えられます。
さらに「もう少し塩を増やしたらどうなる?」と仮説を立て、実験計画を立て直す力が養われます。
実験の手順は次のとおりです。
- コップを二つ用意する
- 一つに真水を入れ、もう一つに食塩を溶かした水を入れる
- 卵や小さなボールをそっと入れる
- どちらが浮くか沈むか観察する
- 必要に応じて塩の量を調整して比べる
中学年向け:不思議が楽しい!台所でできる科学実験
いつものキッチンが実験室に早変わり。色が変わったり、膨らんだり、固まったりする不思議な現象を、五感を使いながら学べる実験をご紹介します。
魔法の色変化!紫キャベツで学ぶ「酸性・アルカリ性(pH)」実験
スーパーで手に入る紫キャベツを煮出したスープへ、息子がレモン汁を一滴垂らした瞬間、「あれ?ピンクになった?!」と本気で驚く姿が印象的でした。
さらに重曹を加えると今度は青色に変化。子どもたちは大はしゃぎし、「まるで絵の具みたいだね!」と歓声をあげました。
紫キャベツは天然のpH指示薬です。色が変化する様子は、酸性とアルカリ性という概念を直感で捉える大きな助けになります。
「どの色が酸性で、どの色がアルカリ性か」を記録・分類することで、科学的な思考の基礎がしっかりと身につきます。
わが家では、このスープをゼリーにして楽しみ、自由研究の発表資料にも使えました。
材料と手順は次のとおりです。
材料(紫キャベツ 2〜3枚/水 300ml/レモン汁 小さじ1〜2/重曹 耳かき1杯程度/ゼラチン(ゼリー用)5g/砂糖(ゼリー用)大さじ1
- 紫キャベツをちぎって水と一緒に鍋で5分ほど煮出す
- キャベツを取り出すと、紫色のスープが残る
- レモン汁を加えるとピンクに、重曹を加えると青に変化
- ゼリーにする場合は、温め直してゼラチンと砂糖を加え、冷蔵庫で2時間冷やす

紫キャベツを入れて煮だし紫色に変わった液体

レモン汁を加えてピンク色に変わった液体

重曹を加えて青色に変わった液体
親子で発見!ホットケーキが膨らむ科学の秘密
実験好きな息子がふと「ホットケーキってどうしてふくらむの?」と聞いてきたことがありました。そこで親子で挑戦したのが「ベーキングパウダーあり/なし」の実験です。
膨らまない方はペタンとしたクレープ風、膨らむ方はふんわり厚みのあるおなじみのホットケーキに。「うわっ、本当に膨らんでる!」と焼きながら息子が歓声をあげた瞬間を、今でもよく覚えています。
この実験の鍵は「対照実験」です。ベーキングパウダーという一つの条件を変えるだけで、結果(膨らみ方)が大きく変わることから、原因物質の役割を明確に理解できます。
日常の調理が「化学変化の観察」になる、素晴らしい学びの機会です。
材料(2枚分)と作り方は次の通りです。
ふくらむ:ホットケーキミックス 150g/牛乳 100ml/卵 1個/サラダ油(焼く用)少々
ふくらまない:薄力粉 100g/砂糖 大さじ1/牛乳 100ml/卵 1個
- ボウルに卵と牛乳を入れてよく混ぜる
- ホットケーキミックス(または比較用の粉)を加えて混ぜる
- フライパンに油をひいて、弱火〜中火で両面を焼く
- 表面に穴が出てきたら裏返す。焼き色がついたら完成
体力勝負!振るだけでアイスができるひんやり実験
夏の定番といえばアイスクリーム。今回は、家庭でできる「ふしぎなアイスクリームづくり」に挑戦しました。
牛乳と砂糖を入れた袋を氷と塩の入った大袋に詰め、タオルに包んで振り続ける作業はまるで小さな運動会。
10分後、袋を開けるとひんやり固まった手作りアイスのお目見え。体力は使いますが、その分完成した時の達成感は格別でした。
塩を混ぜた氷が、ただの氷よりも冷たくなる現象を「凝固点降下」といいます。体温計などで温度を測って数値で記録すると、塩の量と温度低下の関係を定量的に理解できます。
また、物理的な力(振る動作)が状態変化(液状から固体へ)を助ける過程も面白いです。
材料と手順は次のとおりです。
材料(1人分):牛乳 100ml/砂糖 大さじ1/バニラエッセンス 2〜3滴/氷 カップ2杯分
塩 大さじ3/ジップ付き袋(小)1枚/ジップ付き袋(大)1枚/タオルまたは軍手 1枚
- 小袋に牛乳・砂糖・バニラエッセンスを入れて密封
- 大袋に氷と塩を入れ、小袋を中に入れて密封
- タオルで包んで10分間シャカシャカ振る
- 冷たくなってアイス状になったら完成
失敗から生まれた!炭酸ジュースからシュワシュワゼリー
科学実験クッキングは、必ずしもすべてが成功するわけではありません。
娘が「炭酸ジュースでゼリーを作ったら、飲んでもシュワシュワするのでは?」と思いついたのがきっかけでしたが、最初は液体が泡だらけになり大失敗。
しかし「どうして固まらなかったの?」という問いかけから、ゼラチンの性質について少しずつ理解が深まりました。
次に温めて溶かした方法で再挑戦すると、「おお!ちょっとシュワシュワしてる!」と大喜び。
この実験では、炭酸(二酸化炭素)とゼラチン(タンパク質)の性質の違いを学ぶことができます。
「なぜ泡が消えたのか?」「どうすれば固まるのか?」を問い直す過程が、最も重要な科学的思考力を育みます。
材料と手順は次のとおりです。
材料(2人分):炭酸飲料(レモンソーダなど)200ml/ゼラチン 5g/砂糖(お好みで)小さじ1〜2/耐熱容器 1個
1. 炭酸飲料を耐熱容器に入れて、電子レンジでほんのり温める(沸騰させない)。
2. ゼラチンと砂糖を加えてよく混ぜる。
3. 粗熱をとってから冷蔵庫で2〜3時間冷やす。
4. 固まったら完成!ほんのりシュワっとした食感が楽しめます。
ゼラチンは熱湯でしっかり溶かしてから冷やしましょう。また、炭酸は加熱しすぎると泡が飛んでしまうので注意が必要です。
高学年向け:探究心を育てる!本格派実験チャレンジ
より深く考え、工夫し、試行錯誤を重ねる実験に挑戦。失敗から学び、自分なりの発見を見つける喜びを通して、本物の探究心を育てていきましょう。
プリンカップで自家製コンパス:磁石の原理と試行錯誤を学ぶ
「お母さん、電車に乗ると、どっちが北か分からなくなるんだよ」と息子が言ったことがあり、「じゃあ、コンパスを作ってみようか」と提案しました。
実際に針を磁石でこすって水に浮かべましたが、最初は針が北を向かずにぐるぐる回ってしまい、息子は半分あきれ顔。
「磁石でこする回数を増やしてみようか?」「水をもう少し静かに入れたらどうだろう?」と試行錯誤を重ねていくうちに、ついにピタッと北を指した瞬間が訪れました。
その時の息子の喜びは格別で、「おかあさん、これでぼくも探検隊だ!」と目を輝かせました。
この実験は、磁化の仕組みや摩擦・浮力といった複数の原理が関わるため、粘り強い試行錯誤の重要性を学べます。
材料と注意点は次のとおりです。
材料:プリンカップ(透明な容器)/水/縫い針または細い鉄製の針/磁石(ネオジム磁石など強力なものがおすすめ)/発泡スチロールや紙片(針を浮かべる台)
- 針は磁石でしっかりこする(片方向に20回以上)
- 水面が揺れないように静かに水を注ぐ
- 針を浮かべる台は軽くて安定するものを使う
- 周囲に金属や磁石があると方角が狂うので注意
野菜や果物でエコな発電:化学電池の原理と直列つなぎ
娘が理科に興味を持ち始めた頃、「野菜で電気がつくれちゃうんだって!」と目をキラキラさせていました。
じゃがいもとレモンを使い、銅板と亜鉛板を差し込んで豆電球につなぎましたが、最初は全然光らず、子どもたちも「うそー、やっぱり無理じゃない?」と不思議そうな表情。
そこで「電池だって直列にすると強くなるよね」と助言し、レモンを追加して試したところ、豆電球がほんの少し明るく光りました。
「わぁ!光った!レモンってほんとに電池なんだ!」と娘は大喜びし、その後、じゃがいもでもできるか実験を自分から広げていくようになりました。
これは「化学電池」の原理を体感する実験です。イオンになりやすい金属(亜鉛)と、なりにくい金属(銅)が、レモンの電解質によって電力を生み出します。
レモンの数を増やす直列つなぎは、電流と電圧の関係を学ぶ絶好の機会です。また、この実験から、身近な環境問題についても考えることができます。
材料と注意点は次のとおりです。
材料:じゃがいも、レモンなど(電解質を含む野菜・果物)/銅板(または10円玉)/亜鉛板(または釘)/導線/豆電球またはLED
- 銅と亜鉛をしっかり差し込む(接触面を広く)
- 導線の接続は確実に(ゆるみがあると通電しない)
- 電圧が足りない場合は複数の野菜を直列につなぐ
- LEDは豆電球より少ない電力で光るのでおすすめ
油と水が混ざる秘密!「乳化の科学」を体感するマヨネーズ作り
娘が「お菓子作りしたい!」と言ってきたので、マヨネーズ作りに挑戦しました。
「どうして卵と油が混ざるんだろう?」と不思議そうな娘に、「油と水が仲良くなる魔法みたいな現象だよ」と伝えました。
最初、油を一気に入れたため分離してしまい、娘はしょんぼり。
「なんで失敗したんだろう?」と親子で一緒に考えた結果、「油を少しずつ入れるのがポイント」という情報を見つけて再挑戦。とろりとしたマヨネーズが完成し、「わあ、できた!」と娘は大喜びでした。
マヨネーズ作りは、油と水という本来混ざり合わない物質を卵黄の成分(乳化剤)が結びつける「乳化」という化学変化を体感できます。
失敗から原因を考察し、次の計画を立て直すという科学的なプロセスを、調理を通して学ぶことができます。
材料と注意点は次のとおりです。
材料:卵黄/酢またはレモン汁/サラダ油/塩・こしょう(お好みで)/ボウルと泡立て器
- 油は少しずつ加える(乳化が安定する)
- 卵黄と酢をよく混ぜてから油を加える
- 分離しても再挑戦すれば成功しやすい
- 冷たい材料より常温の方が乳化しやすい
草木染めに挑戦!天然染料と媒染剤の化学反応
娘が「草木染めがしてみたいんだ!」と言い出したため、公園で拾った桜の枝で挑戦しました。
桜の枝を煮出すと、淡い桜色のお湯が徐々に立ちのぼり、娘は嬉しそう。その液でガーゼを染めてみると、ほんのり桃色に色づきました。
他にも玉ねぎの皮や紅茶の茶葉で試すと、色合いの違いに「同じ布なのに、全然雰囲気が違う!」と感動していました。
草木染めは、天然染料と媒染剤(色を定着させる物質)の化学反応を、色彩として楽しむ実験です。
さらに、環境問題や伝統文化への興味にも繋がります。色の濃淡を定量的に記録し、色の変化の条件を考察することで、多角的な視点が養われます。
材料と注意点は次のとおりです。
材料:桜の枝、玉ねぎの皮など(染料になる植物)/鍋/水/布(綿や絹がおすすめ)/
ミョウバンなどの媒染剤(色を定着させる)
- 植物はしっかり煮出して色素を抽出
- 布は事前に水洗いして汚れを落とす
- 媒染剤を使うと色が長持ちしやすい
- 煮出し時間や布の種類で色が変わる
太陽の熱で料理!ソーラークッカー:再生可能エネルギーの原理
息子が夏休みにキャンプに行きたいと言い出し、「じゃあ、太陽の光だけで料理ができるか試してみようか」と、この実験を提案しました。
息子と一緒に段ボールでソーラークッカーを工作し、黒いお皿に卵を置いて実験を開始。
開始から1時間ほどで「まだ全然固まってないよ!」と半信半疑だった息子ですが、3時間後には卵がしっかりと温まり、白身が固まり始めていました。
息子は大喜びし、その後「これならホットケーキもできる?」と夢を膨らませていました。
この実験は、熱の集中や保温といった物理的な原理を理解すると同時に、再生可能エネルギーや環境問題について考えるきっかけになります。
親が「もう少し反射板の角度を工夫してみようか?」と次の改善点を示唆することで、試行錯誤の思考サイクルを身につけることができます。
材料と注意点は次のとおりです。
材料:段ボール/アルミホイル/黒い紙または黒い鍋/ラップまたは透明ビニール袋/ゆで卵など加熱する食材
- アルミホイルはしわなく貼ると反射効率UP
- 食材は中央に置き、ラップで密閉すると温度が上がりやすい
- 晴れた日の昼間がベストタイミング
- 直射日光を扱うため、親が必ず付き添い、目を保護する
イースト菌でパンを焼く:微生物の働きと化学変化
息子が「お母さん、パン屋さんみたいに、ふわふわのパン作ってみたい!」と言い出しました。私はすぐに材料を準備するのではなく、まず「どうしてパンは膨らむと思う?」と問いかけてみました。
「イースト菌っていう生き物が、中にいるんだよ」と伝えると、生地がどんどん膨らんでいく様子を見て「ほんとに生きているみたい!」と驚いていました。
イースト菌が二酸化炭素を出すことで生地が膨らむという発酵(化学変化)の原理を説明すると、パン作りの奥深さに興味を持つきっかけとなりました。
材料と注意点は次のとおりです。
材料:強力粉/ドライイースト/砂糖/塩/水/ボウル/ラップ/オーブン
- イーストはぬるま湯で活性化(約35〜40℃)させる
- 発酵時間はしっかりと(生地が2倍に膨らむまで)
- 室温が低いと発酵が遅れるので暖かい場所で
自由研究を「学び」に変える親のサポートガイド
単に実験をすることだけでなく、その過程で子どもの主体的な探究心をどう引き出し、失敗からどう学ぶかが最も重要です。
元教員として、わが家で実践していた具体的なサポートのヒントをご紹介します。
失敗こそ最高の教材!成功にとらわれない姿勢
自由研究は必ずしも成功するとは限りませんが、失敗から学ぶことこそが、知的好奇心の土台になります。
マヨネーズ作りで失敗した時、「なんで失敗したんだろう?」「次はどうすればうまくいくかな?」と親子で考えたように、失敗の原因を突き止め、再挑戦するプロセスが重要です。
思いついたらすぐ始めるのが成功のコツです。たとえば台所で氷を見つめる子に「どこに置いたら早く溶けると思う?」と一言そえるだけで、実験が自然に動き始めます。道具は家にあるもので十分です。
結果が出たら、「ここまでやったら今日はおしまい!」と区切り、ノートに短い言葉と簡単な図を残しましょう。失敗もそのまま残すのが大切です。
この思考のプロセスを可視化することが、真の問題解決能力を育む最高の教材になります。
水の量を間違えた音実験で娘が「音がばらばら」と記録したおかげで、翌日の再挑戦がスムーズに進みました。
子どもの主体性を引き出す親の「伴走」の姿勢
保護者の役割は「先回りして手を出す人」ではなく、「安心して挑戦できる場を整える人」です。
教員時代に「保護者のための自由研究」というプリントを配布し、いくつかのポイントを意識してもらうようお願いしたところ、子どものレポートが見違えるように”自分の研究”になった経験があります。
親がほんの少し伴走の姿勢を意識するだけで、子どもは驚くほど主体的に取り組めるのです。
具体的には、次の点を意識してみてください。
- 安全と確認を促す声掛け
塩と砂糖を取り違えそうな場面では、調味料のラベルを本人に読ませてから渡しました。子どもが「こっちが塩であれが砂糖!」と自分の判断で安全に進められるよう、そっと環境を整えるイメージです。 - テーマの入口では「問い」を引き出す
研究テーマを決めるときに「何が気になる?」「どうしてそう思ったの?」と問いかけ、子どもの言葉を引き出すことが大切です。 - 大きなリアクションで認める
子どもの行動を具体的に認め、成功した時は本気で驚いてみせると、やる気がぐっと上がります。 - まとめの段階では「本人の言葉」を最大限尊重する
レポートや発表のまとめでは、親の言葉を入れず、子どもが感じたことや気づいたことをそのまま大切にします。「〜と思った」「〜に気づいた」といった子どもの視点が研究の核心になります。
安全に楽しく続けるための注意点
観察や実験は子どもにとってとても刺激的ですが、「楽しい!」だけで進めてしまうと、思わぬケガや事故につながることもあるので、親の配慮は欠かせません。
わが家ではオーブンからパンを出した途端、息子は「わーっ!パンだ!おいしそう!」と駆け寄り、危うく素手で触りかけました。
研究室のような専門設備がないからこそ、親が安全面をしっかり見守ることが大切です。
実験の際に気をつけることは次のとおりです。
- 破損・転倒防止:ガラスは安定した平面に。小さな子どもが触れない場所で
- 誤飲対策:食べ物と実験材料を明確に分け、味見は禁止にする
- 衛生管理:観察後は石けんで手洗いを徹底
- やり直しの上限:疲れが出る前に切り上げる。「今日はここまで」を合図に
記録とまとめの工夫:「家族科学ノート」の活用
実験を記録する目的は、結果を残すことだけではありません。「予想」や「失敗の会話」を記録することで、探究の軌跡や思考のプロセスを可視化できます。
わが家では「家族科学ノート」を作り、以下の3ステップで記録していました。
- 表紙と予想
家族全員のサイン入りの表紙に、「今日は何色になると思う?」といった予想も追加。予想が外れても楽しい時間です。 - 会話メモと過程
家族の会話メモや失敗写真、描いた表やイラストをたっぷり記録。「あ、泡が出てきた!」「失敗も大事な発見だよ」といった、その場の生きた言葉を残します。 - 次のテーマリスト
実験中に出た「もっとこうしたら?」という意見や、次回に挑戦したいテーマリストを自由に書き込みます。「次は光る実験がやりたい!」など、次のモチベーションにつなげます。
このプロセスこそが、真の問題解決能力を育てる最高の教材になります。
また、記録・まとめのポイントは次のとおりです。
- 写真は1テーマ3枚以内:「比較」「測定」「結果」を代表するものに絞る
- 一言考察を必ず:「次は△△を変える」の2文だけでも探究が伝わる
- キャプション活用:写真の下に短い説明をつける
学びを広げるステップ:「体験→疑問→知識の探求」のサイクル
身近なものでできる実験を通して、「もっと深く知りたい!」「どうしてこうなるんだろう?」と、お子さんの探究心に火がつくこともあるかもしれません。
五感をフル活用した実体験こそが、学びの土台です。そして、その体験から生まれた「なぜ?」を専門的な知識(科学館や本)で裏付けていく過程が大切です。
この体験→疑問→知識の探求のサイクルを繰り返すことで、自ら学ぶ力(生涯学習能力)が育まれます。
科学館や博物館のワークショップを利用し、プロの解説に耳を傾けることも大切です。
わが家では液体窒素の実験で、子どもたちが「なんで?なんで?」大興奮。驚きと疑問こそが学びの原動力です。
体験を通じて生まれた「なぜ?」を、プロの解説や図書館で借りた専門の本で裏付けていく過程が大切です。
結び:子どもの知的好奇心を育む!おうち時間を特別な学びの時間に変える方法
わが家では最後に写真とコメントをまとめた「実験アルバム」を作っておきました。数年経って見返しても、あの日のワクワクや笑い声が鮮明によみがえります。
子どもたちの「どうしてだろう?」という小さなつぶやきが、やがて大きな学びの芽となり、将来の可能性を広げていきます。
この夏、ぜひご家庭で「研究者」としての一歩を踏み出してみてください。
【執筆者:まさこ先生】
元小学校教員。教諭歴40年。教育相談や保護者対応を通して、延べ4,000人以上の児童と関わってきました。家庭で実践できる親子の関わり方を発信しています。
→筆者の詳しい紹介・教育理念はこちら
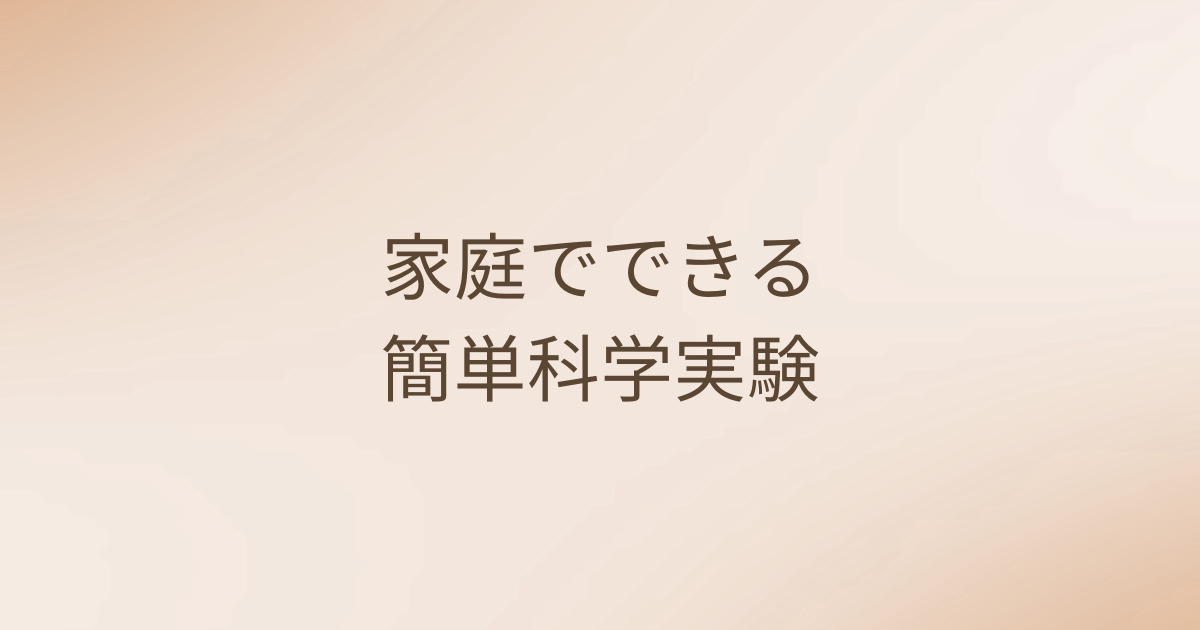
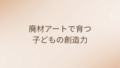
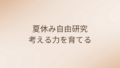
コメント